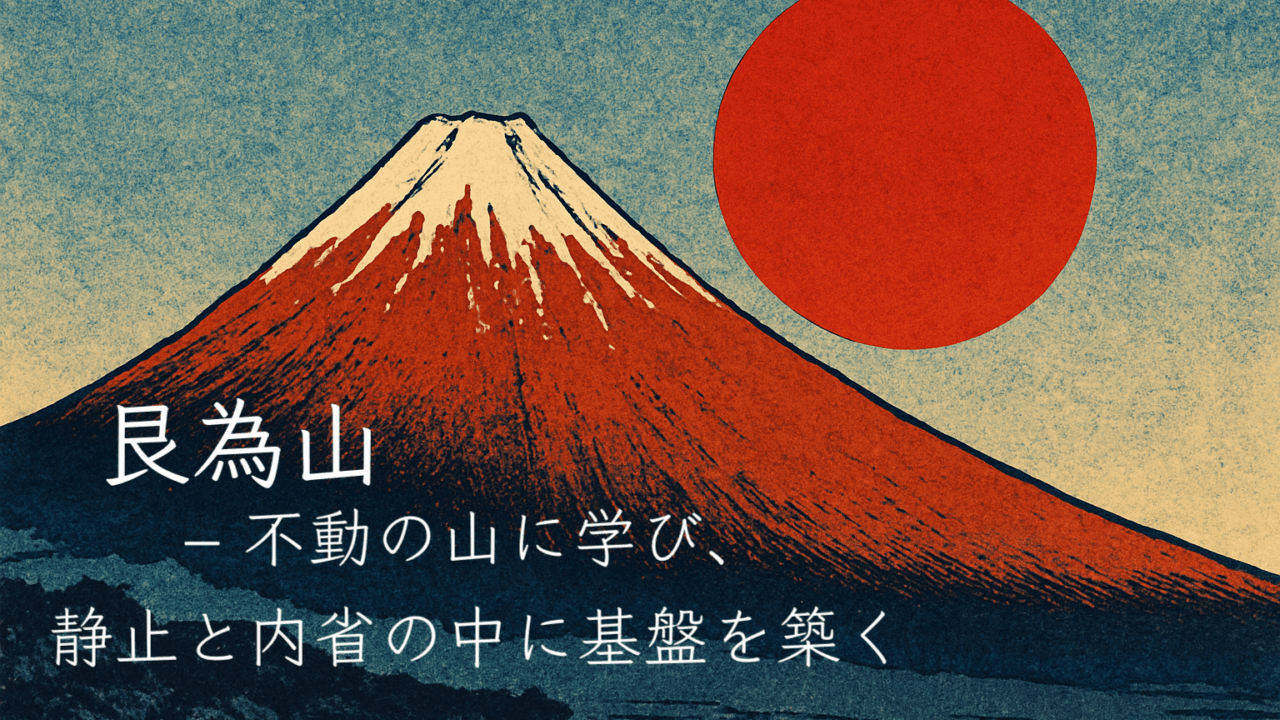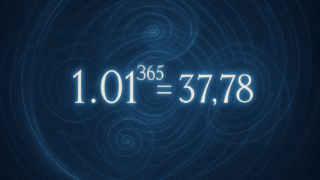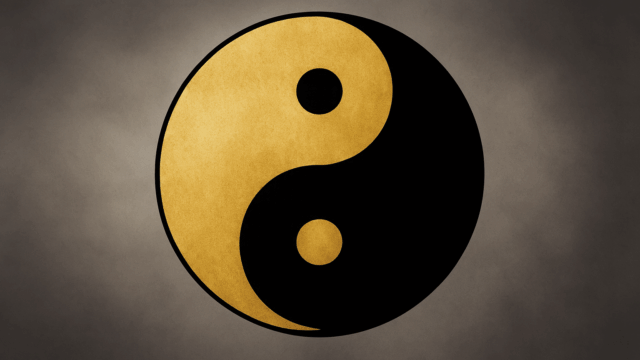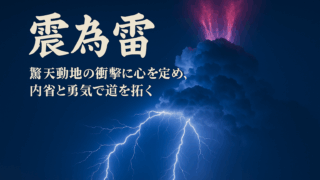【易経】 第52卦「艮為山(ごんいさん)」– 不動の山に学び、静止と内省の中に基盤を築く
1. 卦象(かしょう): ䷳

2. 名称(めいしょう): 艮為山(ごんいさん)
3.【この卦のメッセージ】
* 上卦(じょうか):艮(ごん) – 山、止まる、篤実、静止、少男
下卦(かか):艮(ごん) – 山、止まる、篤実、静止、少男
全体のイメージ: 山(艮)が、さらにその上に山(艮)を重ねる。この「艮為山」の姿は、どこまでも続く山々が、互いに連なり、どっしりと動かずに静止している、雄大で不動の風景を象徴しています。「艮」という文字は、人が背を向けて止まっている形とも言われ、「止まる」「静止する」「とどまる」といった意味合いを持ちます。 この卦は、わたしたちが外に向かって活動するのではなく、むしろ内面に向かって意識を集中し、心を静め、動くべきではない時には動かず、自分のいるべき場所にとどまることの重要性を示しています。それは、決して消極的な停滞ではなく、来るべき時に備えて内なる力を養い、自己を見つめ直し、精神的な安定と深い洞察を得るための、積極的で意味のある「静止」なのです。
卦辞(かじ)– この卦全体のテーマ
原文(漢文):艮其背、不獲其身。行其庭、不見其人。无咎。
書き下し文:其(そ)の背(せ)に艮(とどま)りて、其(そ)の身(み)を獲(え)ず。其(そ)の庭(にわ)に行(ゆ)きて、其(そ)の人(ひと)を見(み)ず。咎(とが)なし。
現代語訳:意識を)その背中(自分の直接見えない部分、無意識の領域)に止めて、自分自身の肉体(欲望や衝動)を意識しないようにする。自分の家の庭を歩いても、そこにいる人々の姿さえ目に入らない(ほどに、心を外界から遮断し、内面に集中している)。そうすれば咎めはない。
ポイント解説:
この卦辞は、「艮」の時の理想的な心のあり方を、非常に象徴的に描写しています。「其の背に艮まりて、其の身を獲ず」とは、意識を自分の背後に置くように、自己中心的で衝動的な欲望(身)から心を離し、それにとらわれない状態を目指すことを意味します。さらに、「其の庭に行きて、其の人を見ず」とは、たとえ身近な場所にいても、外界の刺激や他者の存在に心を乱されることなく、深く内面に集中し、精神的な静寂を保っている様を表します。このような、徹底した「止まるべき時に止まる」という姿勢は、心の平安を保ち、無用な過ち(咎)を避けるための、最善の方法であると教えています。
爻辞(こうじ)– 各爻(こう)が示す変化の機微と物語
「艮為山」の爻辞は、身体の各部分を「止める」ことに喩えて、それぞれの段階における「止まり方」とその意味を示しています。
初六(しょりく):
其(そ)の趾(あし)に艮(とどま)る。咎(とが)なし。永(なが)く貞(てい)に利(よろ)し。
原文:艮其趾。无咎。利永貞。
書き下し文:其(そ)の趾(し)に艮(とどま)る。咎(とが)なし。永(なが)く貞(てい)にす るに利(よろ)し。
現代語訳:その足指(行動の第一歩)を止める。咎めはない。長く正しい道を守り続けるのが良い。
ポイント解説:
「艮」の始まり。まだ行動を起こす前の、足指(趾)の段階で、軽率な動きを止め、慎重であるべき時です。早まって行動に移さず、まずはしっかりと足元を固め、静かに状況を見極める。そのような慎重な「止まり方」は、咎めなく、そして長期的に正しい道(永く貞に利し)を守る上で非常に有益です。
六二(りくじ):
其(そ)の腓(こむら)に艮(とどま)る。其(そ)の隨(したが)うを拯(すく)わず。其(そ)の心(こころ)快(こころよ)からず。
原文:艮其腓。不拯其隨。其心不快。
書き下し文:其(そ)の腓(ひ)に艮(とどま)る。其(そ)の隨(ずい)する所(ところ)を拯(すく)わず。其(そ)の心(こころ)快(かい)ならず。
現代語訳:そのふくらはぎ(進むための力)を止める。そのため、自分が従おうとしていたもの(あるいは、自分に従ってくるもの)を助けることができない。その心は不快である。
ポイント解説:
ふくらはぎ(腓)は、足を動かすための重要な筋肉です。それを止めるということは、進むべき時に進めず、あるいは助けるべき相手を助けられず、もどかしい思いをしている状態です。心は不快(快からず)ですが、この爻は陰爻であり、上の九三の陽爻(艮の主)の意向に従って、今は動くべきではないと判断し、自制しているのかもしれません。時には、自分の感情や衝動を抑え、全体の状況に従って「止まる」ことも必要です。
九三(きゅうさん):
其(そ)の限(こし)に艮(とどま)る。其(そ)の夤(せにく)を列(さ)く。厲(あやう)うして心(こころ)を薰(や)く。
原文:艮其限。列其夤。厲薰心。
書き下し文:其(そ)の限(げん)に艮(とどま)る。其(そ)の夤(いん)を列(れつ)す。厲(れい)にして心(しん)を薰(くん)ず。
現代語訳:その腰(身体の中心、動きの要)を無理に止める。そのため、背中の肉が引き裂かれるようだ。非常に危険な状態で、心が燻(いぶ)るように苦しい。
ポイント解説:
この爻は、身体の中心であり、動きの要である腰(限)を、無理やり止めている非常に苦しい状態です。その結果、背中の肉が裂けるような(其の夤を列す)激しい緊張と痛みを伴い、心は燻るように苦しんでいます(心を薰く)。これは、動きたいという強い衝動や、変革への欲求を、無理に抑圧している状態かもしれません。あるいは、非常に重要な決断を迫られ、身動きが取れないほどのプレッシャーを感じているのかもしれません。非常に危険で、精神的に追い詰められた状況です。
六四(りくし):
其(そ)の身(み)に艮(とどま)る。咎(とが)なし。
原文:艮其身。无咎。
書き下し文:其(そ)の身(み)に艮(とどま)る。咎(とが)なし。
現代語訳:その身体全体(私欲や衝動)を止める。咎めはない。
ポイント解説:
九三の苦しい状態とは対照的に、この爻は、身体全体(身)、つまり、自分自身の個人的な欲望や衝動、感情的な動きを、適切に制御し、静止させている状態です。これは、無用な争いや過ちを避け、心の平静を保つための賢明な「止まり方」であり、何の咎めもありません。自己を客観視し、適切にコントロールできていることを示します。
六五(りくご):
其(そ)の輔(ほお)に艮(とどま)る。言(げん)序(じょ)有(あ)り。悔(くい)亡(ほろ)ぶ。
原文:艮其輔。言有序。悔亡。
書き下し文:其(そ)の輔(ほ)に艮(とどま)る。言(げん)序(じょ)有(あ)り。悔(くい)亡(ほろ)ぶ。
現代語訳:その頬(口先、言葉)を止める。そのため、発する言葉に秩序が保たれる。後悔は消え去る。
ポイント解説:
君主の位にあり、ここでは「輔(頬、口)」、つまり言葉を慎重に選び、軽率な発言を止めている状態です。その結果、発せられる言葉には秩序があり(言序有り)、思慮深く、人々からの信頼を得ます。無用な失言や誤解を避けることができるため、後悔することもありません(悔亡ぶ)。言葉を慎むことの重要性と、それがもたらす良い結果を示しています。
上九(じょうきゅう):
敦(あつ)く艮(とどま)る。吉(きち)。
原文:敦艮。吉。
書き下し文:敦(とん)く艮(ごん)ず。吉(きち)。
現代語訳:篤く、誠実に止まるべき時に止まる。吉である。
ポイント解説:
「艮」の時の最終段階であり、完成された「止まり方」です。「敦く艮る」とは、ただ止まるだけでなく、その止まり方が篤実で、誠意があり、そして完全に安定している状態を表します。もはや何の迷いもなく、心の底から納得して、止まるべき時に止まり、静けさの中に身を置いている。このような完成された「艮」の境地は、大きな吉(吉)をもたらします。
【艮為山(ごんいさん)の「彖伝」】〜全体像〜
原文 彖曰。艮、止也。時止則止、時行則行。動靜不失其時、其道光明。艮其止、止其所也。上下敵應、不相與也。是以不獲其身、行其庭不見其人、无咎也。
書き下し文 彖(たん)に曰(いわ)く、艮(ごん)は、止(とど)まるなり。時(とき)止(とど)まるべきは則(すなわち)止(とど)まり、時(とき)行(ゆ)くべきは則(すなわち)行(ゆ)く。動靜(どうせい)其(そ)の時(とき)を失(うしな)わざれば、其(そ)の道(みち)光明(こうみょう)なり。其(そ)の止(とど)まるに艮(とど)まるとは、其(そ)の所(ところ)に止(とど)まるなり。上下(じょうげ)敵應(てきおう)して、相(あい)與(くみ)せざるなり。是(ここ)を以(もっ)て其(そ)の身(み)を獲(え)ず、其(そ)の庭(にわ)に行(ゆ)きて其(そ)の人(ひと)を見(み)ず、咎(とが)无(な)きとは也(なり)。
現代語訳 彖伝は言う。艮とは、止まることである。(しかし、それは常に止まっているのではなく)止まるべき時には止まり、行くべき時には行く。動きと静けさ、そのどちらも適切なタイミングを失わないならば、その人の歩む道は光り輝くだろう。「その止まるべきところに止まる」というのは、それぞれが自分のいるべき場所、本分に止まるということである。(この卦は)上下の爻が互いに反発し合い、応じ合っていない。だから、互いに関わり合わないのである。このようなわけで、(卦辞にある)「自分自身の肉体を意識せず、自分の家の庭を歩いてもそこにいる人々さえ目に入らない(ほどに内面に集中する)。そうすれば咎めはない」ということなのだ。
大象伝(たいしょうでん)– この卦の形から学ぶ、理想のあり方
原文(漢文):象曰。兼山、艮。君子以思不出其位。
書き下し文:象(しょう)に曰(いわ)く、兼(か)ぬる山(やま)は艮(ごん)なり。君子(くんし)以(もっ)て思(おもい)其(そ)の位(くらい)を出(い)でず。
現代語訳:象伝は言う。山が幾重にも連なり、どっしりと静止しているのが艮の形である。君子(人格者)はこれに倣(なら)い、その思い(思考)を、自分自身の置かれた立場や役割(位)の範囲から逸脱させないようにする。
ポイント解説:
山々が重なり合って、雄大に、そして微動だにせず静止している。これが「艮」の象徴です。これを見た君子は、「思其の位を出でず」、つまり、自分自身の思考や関心を、現在の自分の立場や役割、責任の範囲内に留め、みだりにその範囲を超えたことに心を囚われたり、口出ししたりしない、というあり方を学びます。これは、自分の本分をわきまえ、足元をしっかりと見つめ、今ここでなすべきことに集中することの重要性を示しています。心の散漫を防ぎ、内なる安定を保つための、深い教えです。
【むすび】
艮為山の卦は、わたしたちが目まぐるしく変化する現代社会において、いかにして「止まる」ことの価値を見出し、その静寂の中から真の力と知恵、そして心の平安を育んでいくかという、非常に重要な示唆を与えてくれます。
- 1. 「思(おもい)其(そ)の位(くらい)を出(い)でず」 – あなたの「今、ここ」に、心を集中する勇気: わたしたちの心は、過去の後悔や未来への不安、あるいは自分にはコントロールできない他者の問題など、様々な場所へとさまよいがちです。艮為山は、大象伝が教えるように、まずは自分の思考を「今の自分の立場や役割」にしっかりと繋ぎ止め、目の前のなすべきことに心を集中させることの大切さを教えています。その「今、ここ」への集中が、わたしたちの心を穏やかにし、確かな行動を生み出すのです。
- 2. 「其(そ)の背(せ)に艮(とどま)りて、其(そ)の身(み)を獲(え)ず」 – 内なる静寂の中で、真の自己と繋がる: 卦辞が示すように、時には外界の刺激や自分自身の欲望(身)から意識を離し、心を内側へと向け、深い静寂の中に身を置くことが、わたしたちにとって非常に有益な時間となります。それは、瞑想や内省の時間かもしれませんし、ただ静かに自然と向き合う時間かもしれません。その静けさの中でこそ、わたしたちは普段聞こえない内なる声に耳を澄ませ、真の自己と繋がり、深い洞察を得ることができるのです。
- 3. 「敦(あつ)く艮(とどま)る」 – あなたの「止まる」は、篤実で誠意に満ちていますか?: 上九の爻が示すように、最も理想的な「止まり方」は、篤実で、誠意があり、そして完全に安定した「敦艮」です。わたしたちも、何かを一時的に中断したり、休息したりする際には、ただ怠惰に過ごすのではなく、その「止まる」という行為自体に、自分自身への誠実さや、次への準備という積極的な意味を持たせたいものです。その質の高い「静止」が、やがて大きな吉(吉)へと繋がります。
- 4. 「言(げん)序(じょ)有(あ)り」 – 言葉を慎み、内なる秩序を保つ: 六五の爻が教えるように、口(言葉)を慎重に選び、軽率な発言を止めることは、心の平静を保ち、人間関係の調和を築く上で非常に重要です。わたしたちも、日々のコミュニケーションにおいて、感情的な言葉や不必要な批判を控え、思慮深く、秩序ある言葉(言序有り)を用いることを心がけることで、後悔のない、より建設的な関係を育むことができるでしょう。それもまた、日々よくなるための美しいあり方です。
艮為山の時は、わたしたちが外へ外へと向かいがちな意識を、静かに内側へと向け、自分自身の足元を見つめ直し、そして内なる力を養い育てる、かけがえのない機会です。それは、決して停滞ではなく、次なる大きな飛躍のための、最も確実で、最も賢明な準備なのです。この山のような不動の落ち着きと、その静寂の中に満ちる豊かな智慧を、わたしたちもまた、日々の生活の中で少しずつ育んでいきましょう。その先に、真の境地が待っているはずですから。