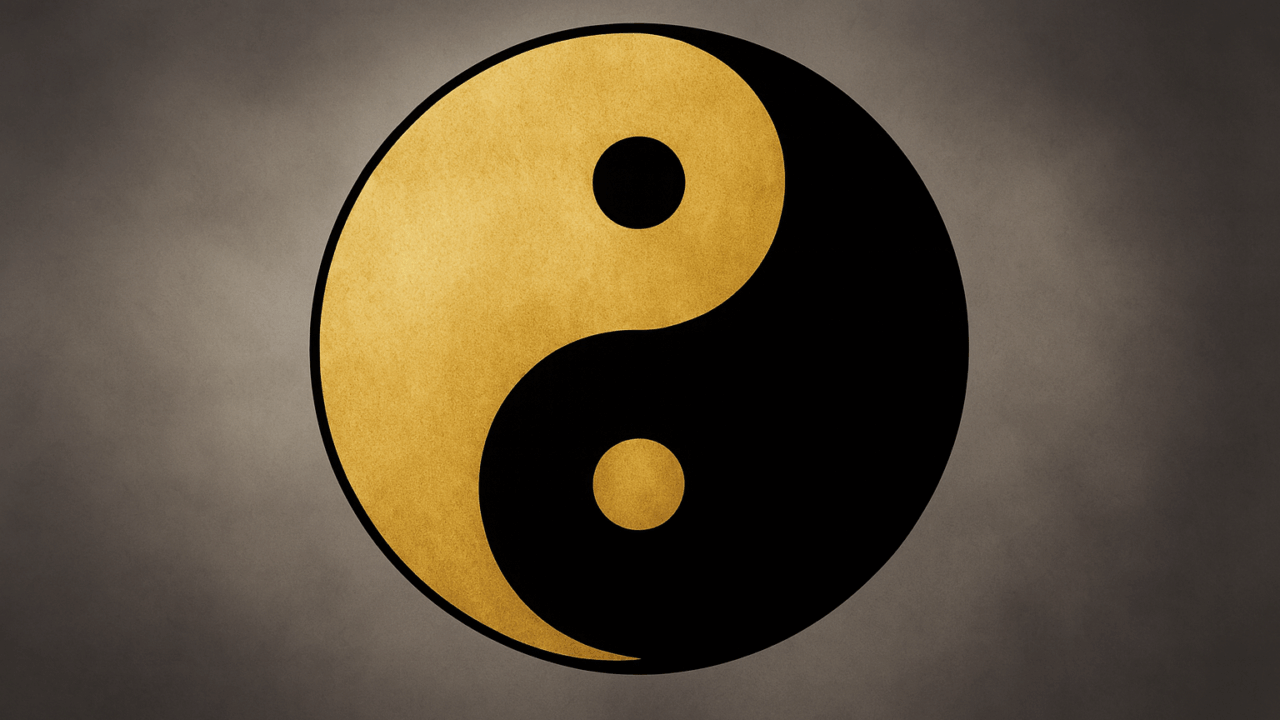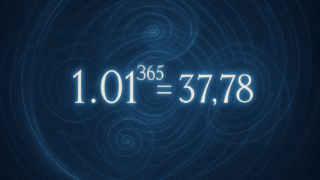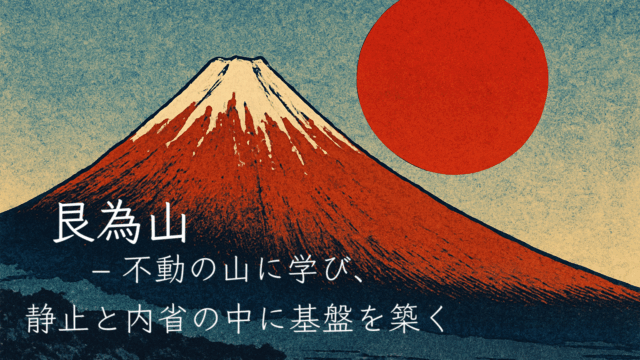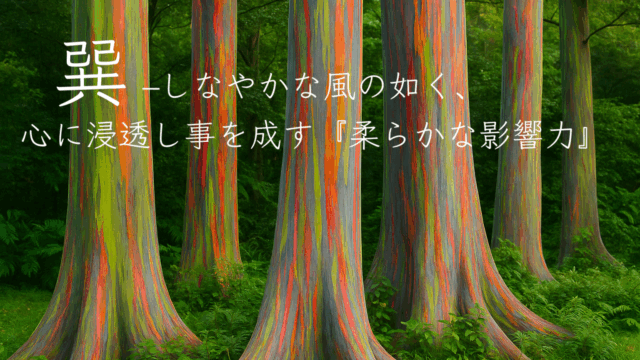【易経】「繫辞下伝」– 変化を創造し、徳を積む
宇宙の法則を、わたしたちの「行動」へ
ブログを訪れてくださり、ありがとうございます。 前回、わたしたちは「繫辞上伝」を通して、易経が示す宇宙の根本原理や、変化の法則、そして聖人が何を思ってこの深遠な智慧を形にしたのかを探求しました。
今回探求する「繫辞下伝(けいじかでん)」は、その壮大な宇宙観を、さらにわたしたち人間の具体的な生活、社会の成り立ち、そして歴史の中での実践へと繋げてくれる、いわば「応用編」であり「実践編」です。
そこには、わたしたちが「日々新たに、益々よくなる」ための、非常に具体的で、力強いヒントが満ち溢れています。
【「繫辞下伝」】
第一章 八卦成列、象在其中矣。因而重之、爻在其中矣。剛柔相推、變在其中矣。繫辭焉而理其辭、動在其中矣。吉凶悔吝者、生乎動者也。剛柔者、立本者也。變通者、趣時者也。吉凶者、貞勝者也。天地之道、貞觀者也。日月之道、貞明者也。天下之動、貞夫一者也。夫乾、確然示人易矣。夫坤、隤然示人簡矣。爻也者、效此者也。象也者、像此者也。爻象動乎内、吉凶見乎外。功業見乎變、聖人之情見乎辭。天地之大德曰生。聖人之大寶曰位。何以守位、曰仁。何以聚人、曰財。理財正辭、禁民為非、曰義。
第二章 古者包犧氏之王天下也、仰則觀象於天、俯則觀法於地。觀鳥獸之文、與地之宜。近取諸身、遠取諸物。於是始作八卦、以通神明之德、以類萬物之情。作結繩而為網罟、以佃以漁。蓋取諸離。包犧氏沒、神農氏作。斲木為耜、揉木為耒。耒耨之利、以教天下。蓋取諸益。日中為市、致天下之民、聚天下之貨。交易而退、各得其所。蓋取諸噬嗑。神農氏沒、黃帝堯舜氏作。通其變、使民不倦。神而化之、使民宜之。易窮則變、變則通、通則久。是以自天祐之、吉无不利。黃帝堯舜、垂衣裳而天下治。蓋取諸乾坤。刳木為舟、剡木為楫。舟楫之利、以濟不通、致遠以利天下。蓋取諸渙。服牛乘馬、引重致遠、以利天下。蓋取諸隨。重門擊柝、以待暴客。蓋取諸豫。斷木為杵、掘地為臼。臼杵之利、萬民以濟。蓋取諸小過。弦木為弧、剡木為矢。弧矢之利、以威天下。蓋取諸睽。上古穴居而野處。後世聖人易之以宮室。上棟下宇、以待風雨。蓋取諸大壯。古之葬者、厚衣之以薪、葬之中野、不封不樹、喪期无数。後世聖人易之以棺槨。蓋取諸大過。上古結繩而治。後世聖人易之以書契。百官以治、萬民以察。蓋取諸夬。
第三章 是故易者、象也。象也者、像也。彖者、材也。爻也者、效天下之動者也。是故吉凶生而悔吝著也。
第四章 陽卦多陰、陰卦多陽。其故何也。陽卦奇、陰卦耦。其德行何也。陽一君而二民、君子之道也。陰二君而一民、小人之道也。
第五章 易曰、憧憧往來、朋從爾思。子曰、天下何思何慮。天下同歸而殊塗、一致而百慮。天下何思何慮。日往則月來、月往則日來、日月相推而明生焉。寒往則暑來、暑往則寒來、寒暑相推而歲成焉。往者屈也、來者信也。屈信相感而利生焉。尺蠖之屈、以求信也。龍蛇之蟄、以存身也。精義入神、以致用也。利用安身、以崇德也。過此以往、未之或知也。窮神知化、德之盛也。
第六章 易曰、困于石、據于蒺藜。入于其宮、不見其妻。凶。子曰、非所困而困焉、名必辱。非所據而據焉、身必危。既辱且危、死期將至。妻其可得見邪。易曰、公用射隼于高墉之上。獲之、无不利。子曰、隼者、禽也。弓矢者、器也。射之者、人也。君子藏器於身、待時而動。何不利之有。動而不括、是以出而有獲。語成器而動者也。子曰、小人不恥不仁、不畏不義。不見利不勸、不威不懲。小懲而大誡、此小人之福也。易曰、履校滅趾、无咎。此之謂也。善不積不足以成名、惡不積不足以滅身。小人以小善為无益而弗為也、以小惡為无傷而弗去也。故惡積而不可掩、罪大而不可解。易曰、何校滅耳、凶。
第七章 子曰、危者、安其位者也。亡者、保其存者也。亂者、有其治者也。是故君子安而不忘危、存而不忘亡、治而不忘亂。是以身安而國家可保也。易曰、其亡其亡、繋于苞桑。
第八章 子曰、德薄而位尊、知小而謀大、力小而任重、鮮不及矣。易曰、鼎折足、覆公餗。其形渥、凶。言不勝其任也。子曰、知幾其神乎。君子上交不諂、下交不瀆。其知幾乎。幾者、動之微、吉之先見者也。君子見幾而作、不俟終日。易曰、介于石、不終日、貞吉。介如石焉、寧用終日、斷可識矣。君子知微知彰、知柔知剛。萬夫之望。
第九章 子曰、顏氏之子、其殆庶幾乎。有不善未嘗不知。知之未嘗復行也。易曰、不遠復、无祗悔、元吉。天地絪縕、萬物化醇。男女構精、萬物化生。易曰、三人行則損一人、一人行則得其友。言致一也。子曰、君子安其身而後動、易其心而後語、定其交而後求。君子脩此三者、故全也。危以動、則民不與也。懼以語、則民不應也。无交而求、則民不與也。莫之與、則傷之者至矣。易曰、莫益之、或擊之。立心勿恆、凶。
【書き下し文】
第一章 八卦(はっけ)列(つら)なりて、象(しょう)其(そ)の中(うち)に在(あ)り。因(よ)りて之(これ)を重(かさ)ぬれば、爻(こう)其の中に在り。剛柔(ごうじゅう)相(あい)推(お)して、変(へん)其の中に在り。辭(じ)を繫(か)けて其の理(り)を言(い)えば、動(どう)其の中に在り。吉凶悔吝(きっきょうかいりん)は、動(どう)に生(しょう)ずる者(もの)なり。剛柔は、本(もと)を立(た)つる者なり。変通(へんつう)は、時(とき)に趣(おもむ)く者なり。吉凶は、貞(てい)勝(か)つ者なり。天地の道は、貞(てい)にして観(み)るべき者なり。日月(じつげつ)の道は、貞にして明(めい)らかなる者なり。天下の動(どう)は、貞にして一(いつ)なる者なり。夫(そ)れ乾(けん)は、確然(かくぜん)として人(ひと)に易(い)を示(しめ)す。夫れ坤(こん)は、隤然(たいぜん)として人に簡(かん)を示す。爻なる者は、此(これ)に效(なら)う者なり。象なる者は、此に像(かたど)る者なり。爻象(こうしょう)内(うち)に動(うご)き、吉凶(きっきょう)外(そと)に見(あら)わる。功業(こうぎょう)変(へん)に見(あら)われ、聖人(せいじん)の情(じょう)辭(じ)に見わる。天地の大德(たいとく)を生(せい)と曰(い)う。聖人の大寶(たいほう)を位(くらい)と曰う。何(なに)を以(もっ)て位を守(まも)る、仁(じん)と曰う。何を以て人を聚(あつ)む、財(ざい)と曰う。財を理(おさ)め辭を正(ただ)し、民(たみ)の非(ひ)を為(な)すを禁(きん)ずる、義(ぎ)と曰う。
第二章 古(いにしえ)者(は)包犧氏(ほうきし)の天下(てんか)に王(おう)たるや、仰(あお)いでは則(すなわち)象(しょう)を天(てん)に観(み)、俯(ふ)しては則ち法(のり)を地(ち)に観る。鳥獣(ちょうじゅう)の文(ぶん)、地(ち)の宜(ぎ)とを観る。近(ちか)くは諸(これ)を身(み)に取(と)り、遠(とお)くは諸を物(もの)に取る。是(ここ)に於(おい)て始(はじ)めて八卦(はっけ)を作(つく)り、以て神明(しんめい)の德(とく)に通(つう)じ、以て万物(ばんぶつ)の情(じょう)を類(るい)す。結繩(けつじょう)して網罟(もうこ)を為(つく)り、以て佃(かり)し以て漁(りょう)す。蓋(けだ)し諸(これ)を離(り)に取(と)る。包犧氏(ほうきし)沒(ぼっ)し、神農氏(しんのうし)作(おこ)る。木(き)を斲(けず)りて耜(し)と為し、木を揉(たわ)めて耒(らい)と為す。耒耨(らいどう)の利(り)、以て天下に教(おし)う。蓋し諸を益(えき)に取る。日中(にっちゅう)を市(いち)と為し、天下の民(たみ)を致(いた)し、天下の貨(か)を聚(あつ)む。交易(こうえき)して退(しりぞ)き、各(おのおの)其(そ)の所(ところ)を得(う)。蓋し諸を噬嗑(ぜいこう)に取る。神農氏沒し、黃帝(こうてい)堯(ぎょう)舜(しゅん)氏(し)作る。其の変に通じ、民をして倦(う)まざらしむ。神(しん)にして之を化し、民をして之に宜(よろ)しからしむ。易(えき)は窮(きわ)まれば則ち変(へん)じ、変ずれば則ち通(つう)じ、通ずれば則ち久(ひさ)し。是を以て天より之を祐(たす)けられ、吉にして利しからざるなし。黃帝堯舜、衣裳(いしょう)を垂(た)れて天下治(おさ)まる。蓋し諸を乾坤(けんこん)に取る。木を刳(えぐ)りて舟(ふね)と為し、木を剡(けず)りて楫(かじ)と為す。舟楫(しゅうしゅう)の利、以て通ぜざるを濟(すく)い、遠きを致(いた)して以て天下を利す。蓋し諸を渙(かん)に取る。牛(うし)に服(ふく)し馬(うま)に乘(じょう)じ、重(おも)きを引(ひ)き遠きを致し、以て天下を利す。蓋し諸を隨(ずい)に取る。門(もん)を重(かさ)ね柝(たく)を撃(う)ち、以て暴客(ぼうかく)を待(ま)つ。蓋し諸を豫(よ)に取る。木を斷(た)ちて杵(きね)と為し、地を掘(ほ)りて臼(うす)と為す。臼杵(きゅうしょ)の利、万民(ばんみん)以て濟(すく)わる。蓋し諸を小過(しょうか)に取る。木を弦(は)りて弧(こ)と為し、木を剡りて矢(や)と為す。弧矢(こし)の利、以て天下を威(い)す。蓋し諸を睽(けい)に取る。上古(じょうこ)は穴居(けっきょ)して野處(やしょ)す。後世(こうせい)の聖人(せいじん)、之に易(か)うるに宮室(きゅうしつ)を以てす。上(かみ)に棟(むなぎ)下(しも)に宇(のき)、以て風雨(ふうう)を待つ。蓋し諸を大壯(たいそう)に取る。古の葬(ほうむ)る者(もの)は、之に衣(い)するに厚(あつ)く薪(たきぎ)を以てし、之を中野(ちゅうや)に葬(ほうむ)り、封(ほう)ぜず樹(じゅ)せず、喪期(そうき)數(かぞ)うること无(な)し。後世の聖人、之に易うるに棺槨(かんかく)を以てす。蓋し諸を大過(たいか)に取る。上古は結繩(けつじょう)して治(おさ)む。後世の聖人、之に易うるに書契(しょけい)を以てす。百官(ひゃっかん)以て治まり、万民(ばんみん)以て察(あき)らかなり。蓋し諸を夬(かい)に取る。
第三章 是(こ)の故(ゆえ)に易(えき)とは、象(しょう)なり。象とは、像(ぞう)なり。彖(たん)とは、材(ざい)なり。爻(こう)とは、天下(てんか)の動(どう)に效(なら)う者なり。是の故に吉凶(きっきょう)生(しょう)じて悔吝(かいりん)著(あらわ)るるなり。
第四章 陽卦(ようか)は陰(いん)多(おお)く、陰卦(いんか)は陽(よう)多し。其(そ)の故(ゆえ)は何(なん)ぞ。陽卦は奇(き)、陰卦は耦(ぐう)。其の德行(とくこう)は何ぞ。陽は一君(いっくん)にして二民(にみん)、君子(くんし)の道なり。陰は二君(にくん)にして一民(いちみん)、小人(しょうじん)の道なり。
第五章 易(えき)に曰(いわ)く、憧憧(しょうしょう)として往来(おうらい)すれば、朋(とも)爾(なんじ)の思(おもい)に従(したが)う。子(し)曰(いわ)く、天下(てんか)何(なに)をか思い何(なに)をか慮(おもんぱか)らん。天下(てんか)は帰(き)する所(ところ)を同(おな)じうして塗(みち)を殊(こと)にし、致(いた)る所(ところ)を一(いつ)にして慮(おもんぱか)りを百(ひゃく)にす。天下何(なに)をか思い何(なに)をか慮らん。日(ひ)往(ゆ)けば則(すなわち)月(つき)来(きた)り、月往けば則ち日来り、日月(じつげつ)相(あい)推(お)して明(めい)生(しょう)ず。寒(かん)往けば則ち暑(しょ)来り、暑往けば則ち寒来り、寒暑(かんしょ)相推して歲(さい)成(な)る。往く者は屈(くっ)するなり、来(きた)る者は信(しん)ずるなり。屈信(くっしん)相(あい)感(かん)じて利(り)生(しょう)ず。尺蠖(せきかく)の屈(くっ)するは、以て信(の)びんことを求(もと)むるなり。龍蛇(りゅうだ)の蟄(ちっ)するは、以て身(み)を存(そん)せんとするなり。義(ぎ)を精(くわ)しくして神(しん)に入(い)るは、以て用(よう)を致(いた)さんがためなり。用を利(り)して身(み)を安(やす)んずるは、以て德(とく)を崇(たっと)ばんがためなり。此(これ)を過(す)ぎて以(もっ)て往(ゆ)くは、未(いま)だ之(これ)或(あるい)は知(し)らざるなり。神を窮(きわ)め化(か)を知(し)るは、德(とく)の盛(さか)んなるなり。
第六章 易(えき)に曰(いわ)く、石(いし)に困(くる)しみ、蒺藜(しつれい)に據(よ)る。其(そ)の宮(きゅう)に入(い)りて、其(そ)の妻(つま)を見(み)ず。凶(きょう)。子(し)曰(いわ)く、困(くる)しむ所に非(あら)ずして困しむ、名(な)必ず辱(はずかし)めらる。據(よ)る所に非ずして據る、身(み)必ず危(あや)うし。既(すで)に辱められ且(か)つ危うし、死期(しき)將(まさ)に至(いた)らんとす。妻(つま)其(そ)れ見る可(べ)けんや。易に曰く、公(こう)用(もっ)て隼(はやぶさ)を高墉(こうよう)の上(うえ)に射(い)る。之を獲(う)、利しからざるなし。子曰く、隼は禽(とり)なり。弓矢(きゅうし)は器(うつわ)なり。之を射る者は、人(ひと)なり。君子(くんし)は器(き)を身(み)に藏(かく)し、時(とき)を待(ま)ちて動(うご)く。何(なん)の利(り)あらざるの有(あ)らん。動(うご)きて括(くく)られず、是(ここ)を以て出(い)でて獲(う)る有(あ)り。器(き)を成(な)して語(かた)り動(うご)く者なり。子曰く、小人(しょうじん)は不仁(ふじん)を恥(は)じず、不義(ふぎ)を畏(おそ)れず。利(り)を見(み)ざれば勸(すす)まず、威(い)せざれば懲(こ)りず。小(ちい)さく懲(こ)らして大(おお)いに誡(いまし)むる、此(こ)れ小人(しょうじん)の福(さいわい)なり。易に曰く、履校(りこう)して趾(あし)を滅(めっ)す、咎(とが)なし、とは此の之を謂うなり。善(ぜん)積(つ)まざれば以て名(な)を成(な)すに足(た)らず、惡(あく)積まざれば以て身(み)を滅(ほろ)ぼすに足らず。小人(しょうじん)は小善(しょうぜん)を以て益(えき)无(な)しと為(な)して為(な)さざるなり、小惡(しょうあく)を以て傷(きず)无しと為して去(さ)らざるなり。故(ゆえ)に惡(あく)積(つ)もりて掩(おお)う可(べか)からず、罪(つみ)大(だい)にして解(と)く可からず。易に曰く、何校(かこう)して耳(みみ)を滅(めっ)す、凶(きょう)。
第七章 子(し)曰(いわ)く、危(あや)うき者(もの)は、其(そ)の位(くらい)に安(やす)んずる者なり。亡(ほろ)ぶる者は、其の存(そん)するを保(たも)たんとする者なり。乱(みだ)るる者は、其の治(ち)を有(たも)つ者なり。是(こ)の故(ゆえ)に君子(くんし)は安(やす)んじて危(あやう)きを忘(わす)れず、存(そん)して亡(ほろ)ぶるを忘れず、治(おさ)まりて乱(みだ)るるを忘れず。是(ここ)を以て身(み)安(やす)くして国家(こっか)は保(たも)つ可(べ)きなり。易(えき)に曰(いわ)く、其(そ)れ亡びん其れ亡びんとて、苞桑(ほうそう)に繋(か)く。
第八章 子(し)曰(いわ)く、德(とく)薄(うす)くして位(くらい)尊(たっと)く、知(ち)小(ちい)さくして謀(はかりごと)大(だい)に、力(ちから)小くして任(にん)重(おも)きは、鮮(すく)なくして及(およ)ばざるなし。易(えき)に曰(いわ)く、鼎(かなえ)足(あし)を折(お)り、公(こう)の餗(そく)を覆(くつがえ)す。其(そ)の形渥(あく)たり、凶(きょう)、とは其の任(にん)に勝(た)えざるを言(い)うなり。子曰く、幾(き)を知(し)るは其(そ)れ神(しん)か。君子(くんし)は上(かみ)に交(まじ)わりて諂(へつら)わず、下(しも)に交わりて瀆(けが)さず。其(そ)れ幾(き)を知るか。幾とは、動(どう)の微(び)にして、吉(きち)の先(さき)に見(あら)わるる者なり。君子(くんし)は幾(き)を見(み)て作(た)ち、終日(しゅうじつ)を俟(ま)たず。易(えき)に曰(いわ)く、石(いし)に介(かい)す、日を終えず、貞(てい)にして吉(きち)。石に介するが如(ごと)し、寧(なん)ぞ終日を用いん、斷(だん)じて識(し)る可(べ)し。君子(くんし)は微(び)を知(し)り彰(あきら)かなるを知り、柔(じゅう)を知り剛(ごう)を知る。万夫(ばんぷ)の望(のぞみ)なり。
第九章 子(し)曰(いわ)く、顏氏(がんし)の子(し)、其(そ)れ殆(ほとん)ど庶幾(ちか)きか。善(ぜん)ならざる有(あ)れば未(いま)だ嘗(かつ)て知(し)らずんばあらず。之を知りて未だ嘗て復(ま)た行(おこな)わず。易(えき)に曰(いわ)く、遠(とお)からずして復(かえ)る、祗(おお)いに悔(く)ゆるなし、元吉(げんきつ)。天地(てんち)絪縕(いんうん)として、万物(ばんぶつ)化醇(かじゅん)す。男女(だんじょ)精(せい)を構(かま)え、万物化生(かせい)す。易に曰く、三人(さんにん)行(ゆ)けば則(すなわち)一人(いちにん)を損(そん)ず、一人行けば則ち其(そ)の友(とも)を得(う)、とは一(いつ)に致(いた)すを言(い)うなり。子曰く、君子(くんし)は其(そ)の身(み)を安(やす)んじて然(しか)る後(のち)に動(うご)き、其の心(こころ)を易(やす)んじて然る後に語(かた)り、其の交(まじ)わりを定(さだ)めて然る後に求(もと)む。君子(くんし)此(こ)の三者(さんしゃ)を脩(おさ)むる、故(ゆえ)に全(まっと)きなり。危うくして以て動けば、則ち民(たみ)與(くみ)せざるなり。懼(おそ)れて以て語れば、則ち民應(おう)ぜざるなり。交わり无(な)くして求むれば、則ち民與せざるなり。之に與する莫(な)ければ、則ち之を傷(そこな)う者(もの)至(いた)る。易に曰く、之を益(ま)すこと莫(な)く、或(あるい)は之を撃(う)つ。心(こころ)を立(た)つること恒(つね)勿(な)からしむれば、凶(きょう)。
【現代語訳】
第一章 八卦が列として並ぶことで、その中に(天地自然の)象徴が示される。それをさらに重ね合わせる(六十四卦とする)ことで、変化の様相を示す爻がその中に示される。剛と柔が互いに作用し合うことで、変化がその中に生まれる。そして、言葉(辞)を繫(つ)けてその道理を明らかにすることで、行動の指針がその中に示される。吉凶悔吝(人生の様々な出来事)は、行動から生まれるものである。剛と柔は、(陰陽という)根本を確立するものである。変化し、それに通じることは、時に順応することである。吉と凶は、正しい道を守り抜けるかどうかにかかっている。天地の道とは、常に正しくあることで、その真価が示されるものである。日月(じつげつ)の道とは、常に明るくあることで、その価値が明らかになるものである。天下の全ての動きは、一つの正しい原理に帰着するのである。そもそも乾というものは、確固としたあり方で人々に変化の易しさを示し、坤というものは、ゆったりとしたあり方で人々に物事の単純さを示す。爻というものは、この乾坤の働きに倣ったものである。象というものは、この乾坤の形にかたどったものである。爻と象が内面で動き、吉凶は外面に現れる。功業は変化の中に現れ、聖人の心は言葉(辞)の中に現れる。天地の最も大いなる徳は、生命を生み育むこと(生)である。聖人にとっての最も大きな宝は、その役割や地位(位)である。どのようにしてその位を守るのかといえば、それは「仁」である。どのようにして人々を集めるのかといえば、それは「財」である。財を正しく管理し、言葉を正し、人々が不正を行うのを禁じること、これを「義」という。
第二章 古代、聖人である包犧(ほうき)氏が天下の王であった時、仰いでは天の様々な現象を観察し、俯いては地の様々な法則を観察した。鳥や獣の模様、それぞれの土地のありさまを観察した。身近なところでは、自分自身の身体から道理を取り、遠いところでは、様々な事物から道理を取った。こうして初めて八卦を作り、それによって神明(人知を超えた働き)の徳に通じ、万物の情(ありさま)を分類したのである。(八卦の離の形をヒントに)縄を結んで網を作り、狩猟や漁労に用いた。これはおそらく離の卦から取ったものである。包犧氏が亡くなり、神農氏が現れた。木を削って鋤(すき)の刃を作り、木を曲げて鋤の柄を作った。この鋤の便利さを、天下の人々に教えた。これはおそらく益の卦から取ったものである。日中(正午)に市を開き、天下の人々を集め、天下の財貨を集めた。交易が終わるとそれぞれ帰り、各々が求めるものを手に入れた。これはおそらく噬嗑の卦から取ったものである。神農氏が亡くなり、黃帝・堯・舜の時代が来た。彼らは変化によく通じ、人々を飽きさせることがなかった。神秘的な徳によって人々を感化し、人々がそれに安んじるようにした。易は、窮まれば変化し、変化すれば通じ、通じれば長く久しく続く。だからこそ、天からの助けを得て、何事も吉であり、不利益なことはなくなるのである。黃帝・堯・舜は、ただ衣裳を垂れているだけで(無為自然の政治を行い)、天下は良く治まった。これはおそらく乾坤の卦から取ったものである。木を刳り抜いて舟とし、木を削って楫(かじ)とした。舟と楫の便利さによって、これまで通れなかった場所を救い、遠くまで行くことを可能にし、天下に利益をもたらした。これはおそらく渙の卦から取ったものである。牛を飼いならし、馬に乗り、重いものを引き、遠くまで行くことで、天下に利益をもたらした。これはおそらく隨の卦から取ったものである。門を二重にし、夜警が拍子木を打つことで、侵入者に備えた。これはおそらく豫の卦から取ったものである。木を断ち切って杵(きね)とし、地面を掘って臼(うす)とした。臼と杵の便利さによって、多くの人々が救われた。これはおそらく小過の卦から取ったものである。木に弦を張って弓とし、木を削って矢とした。弓矢の便利さによって、天下に威信を示した。これはおそらく睽の卦から取ったものである。大昔の人々は、洞穴や野原に住んでいた。後の時代の聖人は、これを宮殿や家屋に変えた。上には棟木があり、下には軒があって、風雨をしのげるようにした。これはおそらく大壯の卦から取ったものである。古代の葬儀では、遺体を多くの薪で厚く覆い、野原の真ん中に葬り、墓標も立てず、木も植えず、喪の期間も定まっていなかった。後の時代の聖人は、これを棺と外棺(棺槨)を用いる方式に変えた。これはおそらく大過の卦から取ったものである。大昔は、縄を結んで記録とし、政治を行っていた。後の時代の聖人は、これを文字(書契)に変えた。それによって、多くの役人たちの仕事は治まり、多くの人々の生活は明らかになった。これはおそらく夬の卦から取ったものである。
第三章 このようなわけで、易とは、象(かたち)である。象とは、像(かたどる)ことである。彖とは、(卦の)材(材料、本質)を述べたものである。爻とは、天下の動きに倣(なら)ったものである。これによって、吉凶が生じ、悔吝が現れるのである。
第四章 陽の卦(震・坎・艮)は陰の爻が多く、陰の卦(巽・離・兌)は陽の爻が多い。それはなぜか。陽の卦は奇数(一陽)であり、陰の卦は偶数(一陰)だからである。その徳のあり方はどうだろうか。陽の卦は一人の君主と二人の民という構成で、君子の道である。陰の卦は二人の君主と一人の民という構成で、小人の道である。
第五章 易(沢山咸の卦)に、「心が定まらず、あれこれと思い悩んでいても、友人たちはあなたの真意に従うだろう」とある。孔子は言う、「天下は一体何を思い、何を慮っているのだろうか。天下は、結局は同じところに帰着するが、そこに至る道は様々であり、行き着くところは一つだが、その思慮は無数にある。天下は一体何を思い、何を慮っているというのか」。日が去れば月が来て、月が去れば日が来る。日月が互いに押し合うことで、明るさが生まれる。寒さが去れば暑さが来て、暑さが去れば寒さが来る。寒暑が互いに押し合うことで、一年が形成される。過ぎ去るものは屈することであり、やって来るものは伸びることである。屈することと伸びることが互いに感応し合うことで、利益が生まれる。尺取虫が身を屈めるのは、後に伸びるためである。龍や蛇が冬ごもりするのは、自らの身を存続させるためである。義理を深く探求し、神妙の域にまで入るのは、その智慧を実践で用いるためである。その用を利して我が身を安定させるのは、その徳を高く尊ぶためである。これ以上の深遠な理については、わたしにもうかがい知ることはできない。神の働きを窮め、変化の道理を知ることこそ、徳の盛んなあり方なのである。
第六章 易(水山蹇の卦)に、「石に困しみ、イバラに據る。その宮に入りて、その妻を見ず。凶」とある。孔子は言う、「困しむべきでないことで困しむような者は、その名誉は必ず辱められる。據るべきでないものに據るような者は、その身は必ず危険に陥る。名誉を辱められ、身も危険となれば、死期はまさに迫っている。どうして妻の顔を見ることなどできようか」。易(雷水解の卦)に、「君主が高い城壁の上の隼を射る。これを獲て、利しからざるなし」とある。孔子は言う、「隼は獲物である。弓矢は道具である。これを射る者は、人間である。君子は、優れた道具(才能や能力)を我が身に隠し持ち、時を待って行動する。どうして利益がないことがあろうか。行動して、その動きが滞ることがないからこそ、外に出て獲物を得ることができるのだ。これは、道具(能力)を完成させてから語り、行動する者のことを言っている」。孔子は言う、「徳の低い小人物は、不仁を恥じることなく、不義を畏れない。利益がなければ善行に励まず、威光を示さなければ懲りることがない。小さく懲らしめることで、大きな悪を戒める。これこそが小人にとっての幸福である」。易(火雷噬嗑の卦)に、「足枷をはめられ足の指を滅する、咎なし」とあるのは、このことを言っているのだ。「善は積まなければ名を成すに足りず、悪は積まなければ身を滅ぼすに足りない」。小人物は、小さな善行は利益がないと考えて行わず、小さな悪行は傷にならないと考えてやめようとしない。だから、悪が積もって覆い隠せなくなり、罪が大きくなって解決できなくなるのだ。易(火雷噬嗑の卦)に、「首枷をはめられ耳を滅する、凶」とある。
第七章 孔子は言う、「危うい状態にある者とは、(平穏な)その地位に安んじている者のことである。滅びる者とは、その生存を(永遠に)保とうとする者のことである。乱れる者とは、その治世を(永遠に)有していると思い込んでいる者のことである」。このようなわけで、君子は平穏な時にも危険を忘れず、生存している時にも滅びる可能性を忘れず、世が治まっている時にも乱れる可能性を忘れない。こうして、我が身は安泰で、国家も保つことができるのである。易(地天泰の卦)に、「其れ亡びん其れ亡びんとて、堅固な桑の木に繋ぎ止める」とある。
第八章 孔子は言う、「徳が薄いのに地位が尊く、知恵が小さいのに計画が大きく、力が小さいのに責任が重い者は、滅多に災いを免れることはない」。易(火風鼎の卦)に、「鼎の足が折れ、君主の食事をひっくり返してしまう。その様は見るも無残で、凶」とあるのは、その任務に耐えられないことを言っているのだ。孔子は言う、「物事の兆し(幾)を知ることは、なんと神妙なことであろうか」。君子は、目上の者と交わってもへつらわず、目下の者と交わっても見下さない。それは、まさに兆しを知っているからであろうか。兆しとは、動きの微細な現れであり、吉兆が先んじて現れるものである。君子は、兆しを見て行動を起こし、一日中待つようなことはしない。易(雷地豫の卦)に、「石に介す(石のように堅固である)、日を終えず(一日中待たず)、貞にして吉」とある。「石に介するが如し」、どうして一日中待つ必要があろうか、断じて機を察知することができるのだ。君子は、微細な兆候を知り、明らかになったことを知り、柔を知り、剛を知る。だからこそ、多くの人々の望みを担う存在となるのだ。
第九章 孔子は言う、「顔回(孔子の一番弟子)は、その境地がほとんど聖人に近いだろうか。彼は、自分に善くないことがあれば必ずそれに気づき、それに気づけば二度とそれを行うことはなかった」。易(地雷復の卦)に、「遠からずして復る、祗いに悔ゆるなし、元吉」とある。天地の気が深く交わり、万物は純粋に化成する。男女が精を交わし、万物は生命を生み出す。易(山沢損の卦)に、「三人行けば則ち一人を損ず、一人行けば則ち其の友を得」とあるのは、心を一つにすることの重要性を言っているのだ。孔子は言う、「君子は、まず我が身を安定させてから行動し、自分の心を安らかにしてから言葉を発し、その交際関係を定めてから人にものを求める。君子はこの三つを修めているからこそ、全てを全うできるのだ。危険な状態で行動すれば、民衆はついてこない。恐れながら語れば、民衆は応じない。交際もないのに求めれば、民衆は与えてくれない。誰からの協力も得られなければ、やがては自分を傷つける者が現れる」。易(風雷益の卦)に、「之を益すこと莫く、或は之を撃つ。心を立つること恒勿からしむれば、凶」とある。
繫辞下伝が示す「変革を興し、徳を積む道」
「繫辞下伝」は、上伝で示された宇宙の法則を、わたしたち人間の具体的な「行動」と「心のあり方」に結びつけ、いかにしてこの世界をより善きものへと創造していくかという、実践的な智慧に満ち溢れています。その中から、わたしたちの「益々善成」の旅を力強く後押ししてくれる、いくつかの重要なヒントを読み解いていきましょう。
1. わたしたちは、易の智慧を用いて「未来を創造する」ことができる
- 繫辞伝の言葉: 「古者包犧氏之王天下也…於是始作八卦…作結繩而為網罟、以佃以漁。蓋取諸離。」(古者包犧氏の天下に王たるや…是に於て始めて八卦を作り…結繩して網罟を為り、以て佃し以て漁す。蓋し諸を離に取る。)
- わたしたちへのヒント: 第二章で語られる、古代の聖人たちが八卦の形から舟や臼、弓矢といった文明の利器を発明していった物語は、易経が単なる「運命を知る」ためのものではなく、**「より良い未来を能動的に創造するための、インスピレーションの源泉」**であることを力強く示しています。わたしたちも、易の智慧に触れる時、ただ受け身でその意味を解釈するだけでなく、「この卦の形から、今の自分の生活や仕事に、どんな新しい工夫や発明を生み出せるだろうか?」と、創造的に問いかけてみること。その姿勢こそが、「益々善成」の精神そのものなのです。
2. どんな時も「安きに危うきを忘れず」 – 順境における心の備え
- 繫辞伝の言葉: 「是故君子安而不忘危、存而不忘亡、治而不忘亂。是以身安而國家可保也。(是の故に君子は安んじて危うきを忘れず、存して亡ぶるを忘れず、治まりて乱るるを忘れず。是を以て身安くして国家は保つ可きなり。)」
- わたしたちへのヒント: 第七章で語られるこの教えは、物事が順調で、平穏な時にこそ、わたしたちが心に刻むべき、非常に重要な智慧です。わたしたちの人生もまた、常に安泰ではありません。平穏な時にこそ、将来起こりうる困難や危機を想定し、そのための備えをしておく。心身を健やかに保ち、学びを怠らず、人間関係を大切にしておく。その「患を思いて豫め防ぐ」(水火既済)姿勢が、いざという時にわたしたち自身を守り、困難を乗り越える力となります。「益々善成」とは、順境の時にこそ、その真価が問われるのかもしれません。
3. 「小善は益なしとせず、小悪は傷なしとせず」 – 日々の小さな積み重ねの力
- 繫辞伝の言葉: 「善不積不足以成名、惡不積不足以滅身。小人以小善為无益而弗為也、以小惡為无傷而弗去也。(善積まざれば以て名を成すに足らず、惡積まざれば以て身を滅ぼすに足らず。小人は小善を以て益无しと為して為さざるなり、小惡を以て傷无しと為して去らざるなり。)」
- わたしたちへのヒント: 第六章のこの言葉は、わたしたちの「日々新たに、益々よくなる」という歩みが、日々の「小さな選択」の積み重ねであることを、厳しくも優しく教えてくれます。「こんな小さな善いことをしても意味がない」と見過ごさず、「こんな小さな悪いことくらいは大丈夫だろう」と見逃さない。その一つひとつの誠実な選択が、やがては大きな徳となり、わたしたちの人格を形作り、そして人生を善き方向へと導いていくのです。大きな成果を急ぐのではなく、まず目の前の「小善」を、心を込めて積み重ねていきましょう。
4. 「幾を知るは其れ神か」 – 変化の「兆し」を捉える感受性を磨く
- 繫辞伝の言葉: 「幾者、動之微、吉之先見者也。君子見幾而作、不俟終日。(幾とは、動の微にして、吉の先に見わるる者なり。君子は幾を見て作ち、終日を俟たず。)」
- わたしたちへのヒント: 第八章で語られる「幾(き)」とは、物事が変化しようとする、ごく微細な「兆し」のことです。この兆しを敏感に察知し、好機を逃さずに行動を起こすことができるかどうかが、人生の大きな分かれ目となることがあります。わたしたちも、日々の生活の中で、自分の心の微細な動きや、周囲の状況のわずかな変化に、もっと注意を払ってみませんか。瞑想や内省の時間を持つこと、あるいは自然の変化に心を寄せること。そうした習慣が、わたしたちの感受性を磨き、人生の好機(幾)を逃さず捉え、「益々善成」の流れに乗るための、素晴らしい力を与えてくれるでしょう。
5. 「身を安んじて然る後に動く」 – 全ては、まず自分を整えることから
- 繫辞伝の言葉: 「君子安其身而後動、易其心而後語、定其交而後求。(君子は其の身を安んじて然る後に動き、其の心を易んじて然る後に語り、其の交わりを定めて然る後に求む。)」
- わたしたちへのヒント: 第九章のこの教えは、わたしたちが何か行動を起こそうとする際の、最も基本的で、最も重要な心構えを示しています。まず、自分自身の心身の状態を安定させ(身を安んじ)、心を穏やかに整え(心を易んじ)、そして人間関係の基盤をしっかりと定める(交わりを定む)。この三つの土台が整って初めて、わたしたちの行動や言葉、そして願いは、スムーズに、そして力強く、世界に受け入れられていくのです。「益々善成」を急ぐあまり、自分自身のケアを怠ったり、足元がおろそかになってはいないか。この言葉は、常にわたしたちにそう問いかけてくれます。
「繫辞下伝」は、宇宙の法則が、決して遠い世界の話ではなく、わたしたちの日々の選択、行動、そして心のあり方の中に、生き生きと脈づいていることを教えてくれます。この深遠な智慧を羅針盤として、わたしたちもまた、自分自身の人生という場で、小さな善を積み、変化の兆しを捉え、そして内なる徳を磨きながら、より善き未来を、自らの手で創造していきましょう。