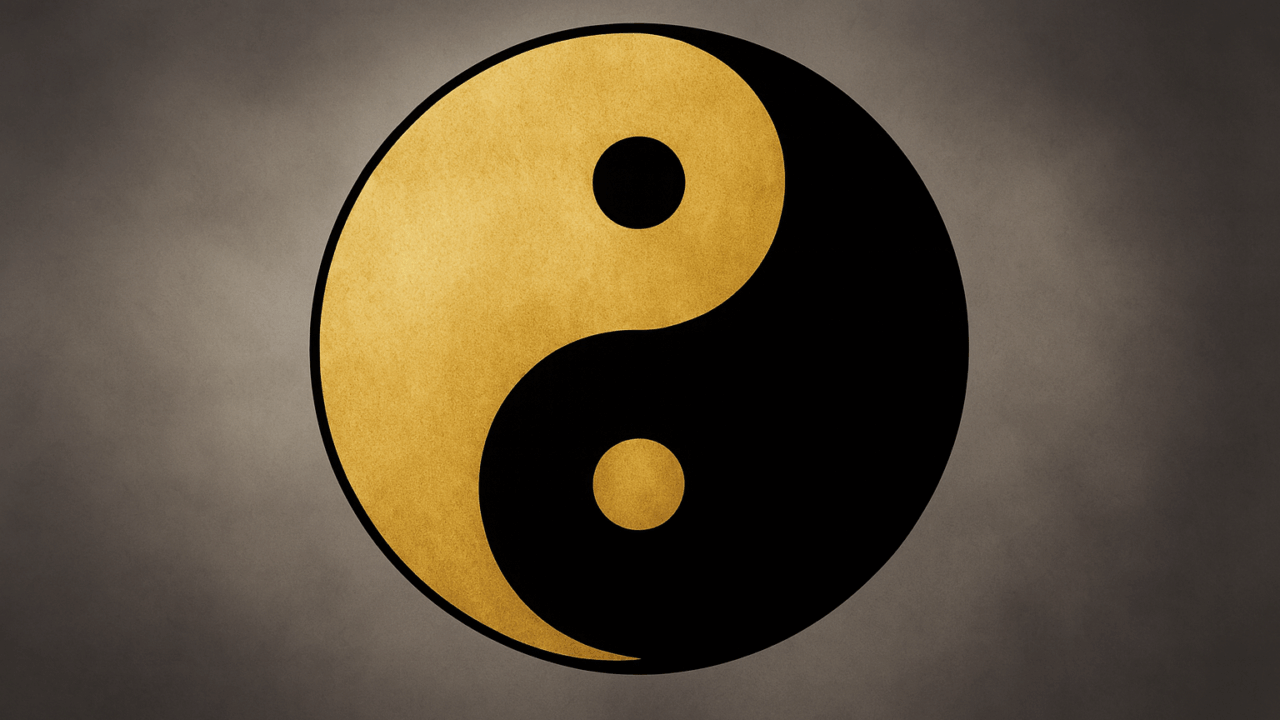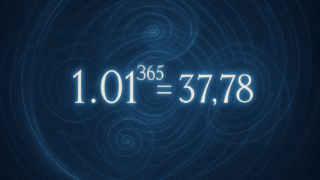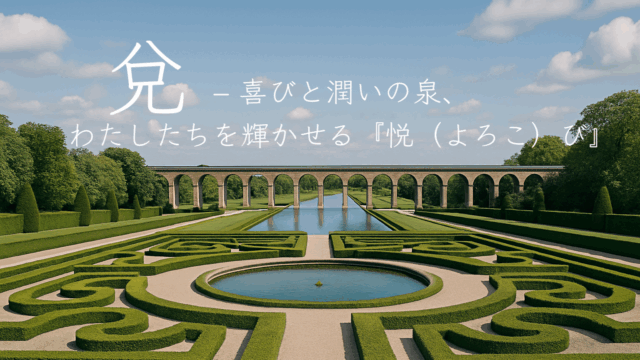【易経】「繫辞上伝」– 宇宙と人生の理(ことわり)を知る
易経の「心臓部」へ – 「繫辞伝」の扉を開く
ブログを訪れてくださり、ありがとうございます。
これまで、易経の根源である「八卦」、そしてその展開である「六十四卦」の世界を探求してきました。
この記事では、まず「繫辞上伝」の全文を、「原文」「書き下し文」「現代語訳」の形で、その壮大で深遠な世界観をありのままに感じていただきます。
「繫辞伝」は、上伝と下伝に分かれており、今回はその前半である「繫辞上伝」の世界を探求します。ここには、宇宙の成り立ち、陰陽の変化の法則、吉凶が生じる理由、そしてわたしたち人間が、この大いなる宇宙のリズムと調和しながら、いかにしてよりよく生きていくべきかという、普遍的な叡智が凝縮されています。
そして最後に、この普遍的な教えの中から、わたしたちが「日々新たに、益々よくなる」ための、かけがえのないヒントを一緒に読み解いていきましょう。
【「繫辞上伝」原文】
第一章 天尊地卑、乾坤定矣。卑高以陳、貴賤位矣。動靜有常、剛柔斷矣。方以類聚、物以群分、吉凶生矣。在天成象、在地成形、變化見矣。是故剛柔相摩、八卦相盪。鼓之以雷霆、潤之以風雨。日月運行、一寒一暑。乾道成男、坤道成女。乾知大始、坤作成物。乾以易知、坤以簡能。易則易知、簡則易從。易知則有親、易從則有功。有親則可久、有功則可大。可久則賢人之德、可大則賢人之業。易簡而天下之理得矣。天下之理得、而成位乎其中矣。
第二章 聖人設卦、觀象、繫辭焉而明吉凶。剛柔相推而生變化。是故吉凶者、失得之象也。悔吝者、憂虞之象也。變化者、進退之象也。剛柔者、晝夜之象也。六爻之動、三極之道也。是故君子所居而安者、易之序也。所樂而玩者、爻之辭也。是故君子居則觀其象而玩其辭、動則觀其變而玩其占。是以自天祐之、吉无不利。
第三章 彖者、言乎象者也。爻者、言乎變者也。吉凶者、言乎其失得也。悔吝者、言乎其小疵也。无咎者、善補過也。是故列貴賤者、存乎位。齊小大者、存乎卦。辨吉凶者、存乎辭。憂悔吝者、存乎介。震无咎者、存乎悔。是故卦有小大、辭有險易。辭也者、各指其所之。
第四章 易與天地準、故能彌綸天地之道。仰以觀於天文、俯以察於地理、是故知幽明之故。原始反終、故知死生之說。精氣為物、遊魂為變、是故知鬼神之情狀。與天地相似、故不違。知周乎萬物而道濟天下、故不過。旁行而不流、樂天知命、故不憂。安土敦乎仁、故能愛。範圍天地之化而不過、曲成萬物而不遺、通乎晝夜之道而知、故神无方而易无體。
第五章 一陰一陽之謂道。繼之者善也、成之者性也。仁者見之謂之仁、知者見之謂之知。百姓日用而不知。故君子之道鮮矣。顯諸仁、藏諸用。鼓萬物而不與聖人同憂。盛德大業至矣哉。富有之謂大業、日新之謂盛德。生生之謂易。成象之謂乾、效法之謂坤。極數知來之謂占、通變之謂事。陰陽不測之謂神。
第六章 夫易、廣矣大矣。以言乎遠、則不禦。以言乎邇、則靜而正。以言乎天地之間、則備矣。夫乾、其靜也專、其動也直。是以大生焉。夫坤、其靜也翕、其動也闢。是以廣生焉。
第七章 子曰、易其至矣乎。夫易、聖人所以崇德而廣業也。知崇禮卑。崇效天、卑法地。天地設位、而易行乎其中矣。成性存存、道義之門。
第八章 聖人有以見天下之賾、而擬諸其形容、象其物宜、是故謂之象。聖人有以見天下之動、而觀其會通、以行其典禮、繫辭焉以斷其吉凶、是故謂之爻。言天下之至賾而不可惡也。言天下之至動而不可亂也。擬之而後言、議之而後動。擬議以成其變化。鳴鶴在陰、其子和之。我有好爵、吾與爾靡之。子曰、君子居其室、出其言善、則千里之外應之、況其邇者乎。居其室、出其言不善、則千里之外違之、況其邇者乎。言出乎身、加乎民。行發乎邇、見乎遠。言行、君子之樞機。樞機之發、榮辱之主也。言行、君子之所以動天地也。可不愼乎。
第九章 同人、先號啕而後笑。子曰、君子之道、或出或處、或默或語。二人同心、其利斷金。同心之言、其臭如蘭。乾、元者、善之長也。亨者、嘉之會也。利者、義之和也。貞者、事之幹也。君子體仁足以長人、嘉會足以合禮、利物足以和義、貞固足以幹事。君子行此四德者、故曰、乾、元亨利貞。
第十章 初九曰、潛龍勿用。何謂也。子曰、龍德而隱者也。不易乎世、不成乎名。遯世无悶、不見是而无悶。樂則行之、憂則違之。確乎其不可拔、潛龍也。九二曰、見龍在田、利見大人。何謂也。子曰、龍德而正中者也。庸言之信、庸行之謹。閑邪存其誠、善世而不伐、德博而化。易曰、見龍在田、利見大人。君德也。九三曰、君子終日乾乾、夕惕若厲无咎。何謂也。子曰、君子進德脩業。忠信、所以進德也。脩辭立其誠、所以居業也。知至至之、可與幾也。知終終之、可與存義也。是故居上位而不驕、在下位而不憂。故乾乾因時而惕、雖厲无咎矣。九四曰、或躍在淵、无咎。何謂也。子曰、上下无常、非為邪也。進退无恆、非離群也。君子進德脩業、欲及時也、故无咎。九五曰、飛龍在天、利見大人。何謂也。子曰、同聲相應、同氣相求。水流濕、火就燥。雲從龍、風從虎。聖人作而萬物覩。本乎天者親上、本乎地者親下。則各從其類也。上九曰、亢龍有悔。何謂也。子曰、貴而无位、高而无民、賢人在下位而无輔、是以動而有悔也。
第十一章 潛龍勿用、下也。見龍在田、德施普也。終日乾乾、反復道也。或躍在淵、進无咎也。飛龍在天、大人造也。亢龍有悔、窮之災也。乾元用九、天下治也。潛龍勿用、陽氣潛藏。見龍在田、天下文明。終日乾乾、與時偕行。或躍在淵、乾道乃革。飛龍在天、乃位乎天德。亢龍有悔、與時偕極。乾元用九、乃見天則。
第十二章 乾、元者、始而亨者也。利貞者、性情也。乾始能以美利利天下、不言所利、大矣哉。大哉乾乎、剛健中正、純粹精也。六爻發揮、旁通情也。時乘六龍、以御天也。雲行雨施、天下平也。君子以成德為行、日可見之行也。潛之為言也、隱而未見、行而未成、是以君子弗用也。君子學以聚之、問以辨之、寬以居之、仁以行之。易曰、見龍在田、利見大人。君德也。九三重剛而不中、上不在天、下不在田。故乾乾因其時而惕、雖厲无咎。九四重剛而不中、上不在天、下不在田、中不在人。故或之。或之者、疑之也、故无咎。夫大人者、與天地合其德、與日月合其明、與四時合其序、與鬼神合其吉凶。先天而天弗違、後天而奉天時。天且弗違、而況於人乎、況於鬼神乎。亢之為言也、知進而不知退、知存而不知亡、知得而不知喪。其唯聖人乎。知進退存亡而不失其正者、其唯聖人乎。
【書き下し文】
第一章 天(てん)は尊(たっと)く地(ち)は卑(ひく)くして、乾坤(けんこん)定(さだ)まる。卑高(ひこう)以(もっ)て陳(つら)なり、貴賤(きせん)位(くらい)す。動靜(どうせい)常(つね)有(あ)り、剛柔(ごうじゅう)斷(さだ)まる。方(ほう)は類(るい)を以て聚(あつ)まり、物(もの)は群(ぐん)を以て分(わか)れ、吉凶(きっきょう)生(しょう)ず。天(てん)に在(あ)りては象(しょう)を成(な)し、地(ち)に在りては形(けい)を成し、変化(へんか)見(あら)わる。是(こ)の故(ゆえ)に剛柔(ごうじゅう)相(あい)摩(ま)し、八卦(はっけ)相(あい)盪(うご)く。之(これ)を鼓(こ)するに雷霆(らいてい)を以てし、之を潤(うるお)すに風雨(ふうう)を以てす。日月(じつげつ)運行(うんこう)し、一(ひと)たびは寒(かん)く一(ひと)たびは暑(しょ)し。乾道(けんどう)は男(だん)を成し、坤道(こんどう)は女(じょ)を成す。乾(けん)は大始(たいし)を知(つかさど)り、坤(こん)は成物(せいぶつ)を作(な)す。乾(けん)は易(い)を以て知(し)り、坤(こん)は簡(かん)を以て能(あた)う。易(やす)ければ則(すなわち)知(し)り易(やす)く、簡(かん)なれば則ち從(したが)い易(やす)し。知り易ければ則ち親(した)しみ有り、從い易ければ則ち功(こう)有り。親しみ有れば則ち久(ひさ)しき可(べ)く、功有れば則ち大(だい)なる可し。久しき可ければ則ち賢人(けんじん)の德(とく)、大なる可ければ則ち賢人の業(ぎょう)。易簡(いかん)にして天下(てんか)の理(り)得(え)らる。天下の理得られ、而(しか)して位(くらい)を其中(そのうち)に成(な)す。
第二章 聖人(せいじん)卦(か)を設(もう)け、象(しょう)を観(み)、辭(じ)を繫(か)けて吉凶(きっきょう)を明(あきら)かにす。剛柔(ごうじゅう)相(あい)推(お)して変化(へんか)を生(しょう)ず。是(こ)の故(ゆえ)に吉凶とは、失得(しっとく)の象(しょう)なり。悔吝(かいりん)とは、憂虞(ゆうぐ)の象なり。変化とは、進退(しんたい)の象なり。剛柔とは、晝夜(ちゅうや)の象なり。六爻(りくこう)の動(どう)は、三極(さんきょく)の道(みち)なり。是の故に君子(くんし)の居(お)りて安(やす)んずる所(ところ)の者(もの)は、易(えき)の序(じょ)なり。樂(たの)しんで玩(もてあそ)ぶ所の者の者は、爻(こう)の辭(じ)なり。是の故に君子(くんし)は居(お)っては則ち其(そ)の象(しょう)を観(み)て其の辭(じ)を玩(がん)し、動(うご)いては則ち其の変(へん)を観て其の占(うらない)を玩す。是(ここ)を以て天(てん)より之(これ)を祐(たす)けられ、吉(きち)にして利(よろ)しからざるなし。
第三章 彖(たん)とは、象(しょう)を言(い)う者(もの)なり。爻(こう)とは、変(へん)を言う者なり。吉凶(きっきょう)とは、其(そ)の失得(しっとく)を言うなり。悔吝(かいりん)とは、其の小(ちい)さき疵(きず)を言うなり。咎(とが)无(な)きとは、善(よ)く過(あやま)ちを補(おぎな)うなり。是(こ)の故(ゆえ)に貴賤(きせん)を列(つら)ぬるは、位(くらい)に存(そん)す。小大(しょうだい)を齊(ととの)うるは、卦(か)に存す。吉凶(きっきょう)を辨(わきま)うるは、辭(じ)に存す。悔吝(かいりん)を憂(うれ)うるは、介(かい)に存す。咎(とが)无(な)きを震(ふる)うは、悔(くい)に存(そん)す。是の故に卦に小大有り、辭に險易(けんい)有り。辭なる者は、各(おのおの)其(そ)の之(ゆ)く所(ところ)を指(さ)す。
第四章 易(えき)は天地(てんち)と準(ひと)し、故(ゆえ)に能(よ)く天地(てんち)の道(みち)を彌綸(びりん)す。仰(あお)いでは以て天文(てんもん)を観(み)、俯(ふ)しては以て地理(ちり)を察(さっ)す、是(ここ)を以て幽明(ゆうめい)の故(ゆえ)を知(し)る。始(はじめ)を原(たず)ね終(おわり)に反(かえ)る、故に死生(しせい)の説(せつ)を知る。精氣(せいき)は物(もの)と為(な)り、遊魂(ゆうこん)は変(へん)と為る、是の故に鬼神(きしん)の情狀(じょうじょう)を知る。天地(てんち)と相似(あいに)たり、故に違(たが)わず。知(ち)は万物(ばんぶつ)に周(あまね)くして道(みち)は天下(てんか)を濟(すく)う、故に過(あやま)たず。旁(あまね)く行(おこな)われて流(なが)れず、天(てん)を樂(たの)しみ命(めい)を知(し)る、故に憂(うれ)えず。土(つち)に安(やす)んじ仁(じん)に敦(あつ)し、故に能く愛(あい)す。天地(てんち)の化(か)を範囲(はんい)して過(す)ぎず、万物(ばんぶつ)を曲成(きょくせい)して遺(のこ)さず、晝夜(ちゅうや)の道(みち)に通(つう)じて知(し)る、故(ゆえ)に神(しん)は方(ほう)无(な)くして易(えき)は體(たい)无(な)し。
第五章 一陰一陽(いちいんいちよう)、之(これ)を道(みち)と謂(い)う。之を繼(つ)ぐ者(もの)は善(ぜん)なり、之を成(な)す者は性(せい)なり。仁者(じんじゃ)は之を見(み)て之を仁(じん)と謂い、知者(ちしゃ)は之を見て之を知(ち)と謂う。百姓(ひゃくせい)は日(ひ)に用(もち)いて知(し)らず。故(ゆえ)に君子(くんし)の道(みち)は鮮(すく)なし。仁(じん)を顯(あら)わし用(よう)を藏(かく)す。万物(ばんぶつ)を鼓(こ)して聖人(せいじん)と憂(うれい)を同(おな)じうせず。盛德(せいとく)大業(たいぎょう)至(いた)れりかな。有(ゆう)を富(とみ)とす之を大業(たいぎょう)と謂い、日(ひ)に新(あら)たなる之を盛德(せいとく)と謂う。生(せい)を生(しょう)ずる之を易(えき)と謂う。象(しょう)を成(な)す之を乾(けん)と謂い、法(のり)に效(なら)う之を坤(こん)と謂う。數(すう)を極(きわ)め来(らい)を知(し)る之を占(せん)と謂い、変(へん)に通(つう)ずる之を事(じ)と謂う。陰陽(いんよう)測(はか)る可(べか)らざる之を神(しん)と謂う。
第六章 夫(そ)れ易(えき)は、廣(ひろ)くして大(だい)なり。以て遠(とお)きを言(い)えば、則(すなわち)禦(ふせ)がず。以て邇(ちか)きを言えば、則ち静(しず)かにして正(ただ)し。以て天地(てんち)の間(かん)を言えば、則ち備(そな)われり。夫れ乾(けん)は、其(そ)れ静(しず)かなるや專(もっぱ)ら、其れ動(うご)くや直(なお)し。是(ここ)を以て大(だい)生(しょう)ず。夫れ坤(こん)は、其れ静かなるや翕(と)じ、其れ動くや闢(ひら)く。是を以て廣(こう)生(しょう)ず。
第七章 子(し)曰(いわ)く、易(えき)は其(そ)れ至(いた)れるか。夫(そ)れ易(えき)は、聖人(せいじん)の德(とく)を崇(たっと)びて業(ぎょう)を廣(ひろ)むる所以(ゆえん)なり。知(ち)は崇(たか)く禮(れい)は卑(ひく)し。崇(たか)きは天(てん)に效(なら)い、卑(ひく)きは地(ち)に法(のっと)る。天地(てんち)位(くらい)を設(もう)けて、易(えき)其(そ)の中(うち)に行(おこな)わる。性(せい)を成(な)し存存(そんそん)するは、道義(どうぎ)の門(もん)なり。
第八章 聖人(せいじん)以(もっ)て天下(てんか)の賾(ふか)きを見(み)て、諸(これ)を其(そ)の形容(けいよう)に擬(ぎ)し、其(そ)の物(もの)の宜(よろ)しきに象(かたど)る、是(こ)の故(ゆえ)に之(これ)を象(しょう)と謂(い)う。聖人(せいじん)以て天下(てんかか)の動(どう)を見て、其(そ)の会通(かいつう)を観(み)、以て其(そ)の典禮(てんれい)を行(おこな)い、辭(じ)を繫(か)けて以て其(そ)の吉凶(きっきょう)を斷(だん)ず、是の故に之を爻(こう)と謂う。天下の至賾(しせき)を言(い)えども惡(にく)む可(べか)からず。天下の至動(しどう)を言えども乱(みだ)る可からず。之に擬(ぎ)して然(しか)る後(のち)に言(い)い、之を議(はか)りて然る後に動(うご)く。擬議(ぎぎ)して以て其(そ)の変化(へんか)を成(な)す。「鳴鶴(めいかく)陰(いん)に在(あ)り、其(そ)の 子(こ)之(これ)に和(わ)す。我(われ)に好爵(こうしゃく)有(あ)り、吾(われ)爾(なんじ)と之(これ)を靡(ともに)せん」とは、子(し)曰(いわ)く、君子(くんし)其(そ)の室(しつ)に居(お)り、其の言(げん)を出(いだ)して善(よ)ければ、則(すなわち)千里(せんり)の外(そと)も之(これ)に應(おう)ず、況(いわ)んや其(そ)の邇(ちか)き者(もの)をや。其の室(しつ)に居り、其の言を出して善からざれば、則ち千里の外も之に違(たが)う、況んや其の邇き者をや。言(げん)は身(み)より出でて、民(たみ)に加(くわ)わる。行(おこない)は邇きより発(はっ)して、遠(とお)きに見(あら)わる。言行(げんこう)は、君子(くんし)の樞機(すうき)なり。樞機の発するは、榮辱(えいじょく)の主(しゅ)なり。言行は、君子の以て天地を動かす所以(ゆえん)なり。愼(つつし)まざる可(べ)けんや。
第九章 「同人(どうじん)、先(さき)には號啕(ごうとう)し後(のち)には笑(わら)う」とは、子(し)曰(いわ)く、君子(くんし)の道(みち)は、或(あるい)は出(い)で或(あるい)は処(お)り、或は黙(もく)し或は語(かた)る。二人(ににん)心(こころ)を同(おな)じうすれば、其(そ)の利(り)金(きん)を斷(た)つ。同心(どうしん)の言(げん)は、其(そ)の臭(かおり)蘭(らん)の如(ごと)し。「乾(けん)の元(げん)とは、善(ぜん)の長(ちょう)なり。亨(こう)とは、嘉(か)の会(かい)なり。利(り)とは、義(ぎ)の和(わ)なり。貞(てい)とは、事(こと)の幹(かん)なり。」君子(くんし)仁(じん)を體(たい)して以て人(ひと)に長(ちょう)たるに足(た)り、嘉会(かかい)以て禮(れい)に合(がっ)するに足り、物(もの)を利(り)して以て義(ぎ)を和(わ)するに足り、貞固(ていこ)にして以て事(こと)を幹(つかさど)るに足る。君子(くんし)此(こ)の四德(しとく)を行(おこな)う者(もの)、故(ゆえ)に曰く、乾は元亨利貞(げんこうりてい)、と。
第十章 「初九(しょきゅう)曰(いわ)く、潜龍(せんりゅう)用(もち)うる勿(なか)れ」とは、何(なに)をか謂(い)う。子(し)曰(いわ)く、龍德(りゅうとく)有(あ)りて隱(かく)るる者(もの)なり。世(よ)に易(か)えられず、名(な)を成(な)さず。世(よ)を遯(のが)れて悶(うれ)うること无(な)く、是(ぜ)とせられざるを見(み)ても悶うること无し。樂(たの)しめば則(すなわち)之(これ)を行(おこな)い、憂(うれ)うれば則ち之に違(たが)う。確乎(かくこ)として其(そ)れ抜(ぬ)く可(べか)からざるは、潜龍(せんりゅう)なり。「九二(きゅうじ)曰く、見龍(けんりゅう)田(でん)に在(あ)り、大人(たいじん)を見(み)るに利(よろ)し」とは、何をか謂う。子曰く、龍德有りて正中(せいちゅう)なる者なり。庸言(ようげん)之(これ)を信(しん)にし、庸行(ようこう)之を謹(つつし)む。邪(じゃ)を閑(ふせ)ぎて其(そ)の誠(まこと)を存(そん)し、世(よ)を善(よ)くして伐(ほこ)らず、德(とく)博(ひろ)くして化(か)す。易(えき)に曰(いわ)く、見龍(けんりゅう)田に在り、大人を見るに利し、とは君德(くんとく)なり。「九三(きゅうさん)曰く、君子(くんし)終日(しゅうじつ)乾乾(けんけん)し、夕(ゆうべ)に惕若(てきじゃく)たれば厲(あやう)うけれども咎(とが)无(な)し」とは、何をか謂う。子曰く、君子(くんし)は德(とく)を進(すす)め業(ぎょう)を脩(おさ)む。忠信(ちゅうしん)は、德を進むる所以(ゆえん)なり。辭(じ)を脩(おさ)め其(そ)の誠(まこと)を立(た)つるは、業(ぎょう)に居(お)る所以なり。至(いた)るを知(し)りて之に至(いた)るは、與(とも)に幾(き)す可(べ)きなり。終(おわ)るを知りて之に終るは、與に義(ぎ)を存(そん)す可きなり。是(こ)の故(ゆえ)に上位(じょうい)に居(お)りて驕(おご)らず、下位(かい)に在(あ)りて憂(うれ)えず。故(ゆえ)に乾乾(けんけん)として時(とき)に因(よ)りて惕(おそ)るれば、厲(あやう)うしと雖(いえど)も咎(とが)无(な)し。「九四(きゅうし)曰く、或(あるい)は躍(おど)りて淵(ふち)に在(あ)り、咎(とが)无(な)し」とは、何をか謂う。子曰く、上下(じょうげ)常(つね)无(な)きは、邪(じゃ)を為(な)すに非(あら)ざるなり。進退(しんたい)恆(つね)无(な)きは、群(ぐん)を離(はな)るるに非ざるなり。君子(くんし)は德を進め業を脩め、時(とき)に及(およ)ばんことを欲(ほっ)す、故に咎无し。「九五(きゅうご)曰く、飛龍(ひりゅう)天(てん)に在(あ)り、大人(たいじん)を見るに利し」とは、何をか謂う。子曰く、同聲(どうせい)相(あい)應(おう)じ、同氣(どうき)相求(あいもと)む。水(みず)は濕(うるお)えるに流(なが)れ、火(ひ)は燥(かわ)けるに就(つ)く。雲(くも)は龍(りゅう)に從(したが)い、風(かぜ)は虎(とら)に從う。聖人(せいじん)作(おこ)りて万物(ばんぶつ)覩(み)る。天(てん)に本(もと)づく者(もの)は上(かみ)に親(した)しみ、地(ち)に本づく者は下(しも)に親しむ。則(すなわち)各(おのおの)其(そ)の類(るい)に從うなり。「上九(じょうきゅう)曰く、亢龍(こうりゅう)悔(くい)有(あ)り」とは、何をか謂う。子曰く、貴(たっと)くして位(くらい)无(な)く、高(たか)くして民(たみ)无く、賢人(けんじん)下位(かい)に在(あ)りて輔(たす)け无(な)し、是(ここ)を以て動(うご)けば悔(くい)有(あ)るなり。
第十一章 「潜龍(せんりゅう)用(もち)うる勿(なか)れ」とは、下(しも)なればなり。「見龍(けんりゅう)田(でん)に在(あ)り」とは、德施(とくし)普(あまね)ければなり。「終日(しゅうじつ)乾乾(けんけん)」とは、道(みち)に反復(はんぷく)すればなり。「或(あるい)は躍(おど)りて淵(ふち)に在(あ)り」とは、進(すす)みて咎(とが)无(な)ければなり。「飛龍(ひりゅう)天(てん)に在(あ)り」とは、大人(たいじん)の造(な)すところなればなり。「亢龍(こうりゅう)悔(くい)有(あ)り」とは、窮(きわ)まればの災(わざわい)なればなり。「乾元(けんげん)用九(ようきゅう)」とは、天下(てんか)治(おさ)まればなり。「潜龍(せんりゅう)用うる勿れ」とは、陽氣(ようき)潜藏(せんぞう)すればなり。「見龍田に在り」とは、天下(てんか)文明(ぶんめい)なればなり。「終日乾乾」とは、時(とき)と偕(とも)に行(ゆ)けばなり。「或は躍りて淵に在り」とは、乾道(けんどう)乃(すなわち)革(あらた)まればなり。「飛龍天に在り」とは、乃ち天德(てんとく)に位(くらい)すればなり。「亢龍悔有り」とは、時と偕に極(きわ)まればなり。「乾元用九」とは、乃ち天(てん)の則(のり)を見(み)るなり。
第十二章 乾(けん)の元(げん)とは、始(はじ)にして亨(とお)る者(もの)なり。利貞(りてい)とは、性情(せいじょう)なり。乾(けん)は始(はじ)めて能(よ)く美利(びり)を以て天下(てんか)を利(り)す、利(り)する所(ところ)を言(い)わず、大(だい)なるかな。大(だい)なるかな乾(けん)や、剛健(ごうけん)中正(ちゅうせい)、純粹(じゅんすい)精(せい)なり。六爻(りくこう)發揮(はっき)し、旁(あまね)く情(じょう)に通(つう)ず。時(とき)に六龍(りくりゅう)に乘(じょう)じ、以て天(てん)を御(ぎょ)す。雲(くも)行(ゆ)き雨(あめ)施(ほどこ)し、天下(てんか)平(たい)らかなり。君子(くんし)は德(とく)を成(な)すを以て行(おこない)と為(な)す、日(ひ)に行(おこない)を見る可(べ)きなり。潜(せん)とは之(これ)を言(い)うなり、隱(かく)れて未(いま)だ見(あら)われず、行(おこない)て未だ成(な)らず、是(ここ)を以て君子(くんし)は用(もち)いざるなり。君子(くんし)は學(まな)びて以て之を聚(あつ)め、問(と)いて以て之を辨(わきま)え、寬(かん)を以て之に居(お)り、仁(じん)を以て之を行(おこな)う。易(えき)に曰(いわ)く、見龍(けんりゅう)田(でん)に在(あ)り、大人(たいじん)を見(み)るに利(よろ)し、とは君德(くんとく)なり。九三(きゅうさん)は重剛(ちょうごう)にして中(ちゅう)ならず、上(かみ)天に在らず、下(しも)田に在らず。故(ゆえ)に乾乾(けんけん)として其(そ)の時(とき)に因(よ)りて惕(おそ)るれば、厲(あやう)しと雖(いえど)も咎(とが)无(な)し。九四(きゅうし)は重剛にして中ならず、上天に在らず、下田に在らず、中(ちゅう)人(ひと)に在らず。故に或(あるい)はす。或るはすとは、之を疑(うたが)うなり、故に咎无し。夫(そ)れ大人(たいじん)とは、天地(てんち)と其(そ)の德(とく)を合(がっ)し、日月(じつげつ)と其の明(めい)を合し、四時(しいじ)と其の序(じょ)を合し、鬼神(きしん)と其の吉凶(きっきょう)を合す。天(てん)に先(さき)んじても天(てん)違(たが)わず、天(てん)に後(おく)れても天(てん)の時(とき)を奉(ほう)ず。天(てん)すら且(か)つ違(たが)わず、而(しか)るを況(いわ)んや人(ひと)に於(おい)てをや、況んや鬼神(きしん)に於てをや。亢(こう)とは之(これ)を言うなり、進(すす)むを知(し)りて退(しりぞ)くを知(し)らず、存(そん)するを知りて亡(ほろ)ぶを知らず、得(う)るを知りて喪(うしな)うを知らず。其(そ)れ唯(た)だ聖人(せいじん)か。進退存亡(しんたいそんぼう)を知(し)りて其(そ)の正(せい)を失(うしな)わざる者(もの)は、其れ唯だ聖人か。
【現代語訳】
第一章 天は尊く、地は卑しい。この関係によって、創造の原理(乾)と受容の原理(坤)という根本が定まる。卑しいものと高いものが順に並ぶことで、尊いものと賤しいものの位置づけがなされる。動きと静けさには常に定まった法則があり、それによって剛なるものと柔なるものの区別がはっきりする。物事はその方針や性質によって仲間と集まり、種類によって群れをなして分かれる。こうして吉と凶が生じる。天においては様々な現象(象)として現れ、地においては具体的な形(形)として現れ、この世の万般の変化が見えるようになる。このようなわけで、剛と柔のエネルギーが互いに摩擦し合い、八つの卦(八卦)が互いに作用し合うのである。これを奮い立たせるものとして雷があり、これを潤すものとして風と雨がある。太陽と月が運行し、寒さと暑さが交互に訪れる。乾の道は男性的なものを生み出し、坤の道は女性的なものを生み出す。乾は万物の大いなる始まりを司り、坤は具体的な物を生成する働きをする。乾は変化(易)によって物事を指し示し、坤は単純さ(簡)によって物事を成し遂げる。変化(易)は知りやすく、単純(簡)は従いやすい。知りやすければ親しみが生まれ、従いやすければ功績が上がる。親しみがあれば長く続き、功績があれば大きくなることができる。長く続くのは賢人の徳であり、大きくなるのは賢人の事業である。易しく単純であることによって、天下の道理は会得されるのだ。天下の道理が会得されてこそ、その道理の中に自分のいるべき位置が定まるのである。
第二章 聖人は卦を設け、その象(かたち)を観察し、言葉(辞)を繫(つ)けて、吉と凶を明らかにした。剛と柔が互いに押し合うことで、変化が生まれる。このようなわけで、吉と凶とは、成功と失敗の象徴である。悔(くい)と吝(ちぢかむこと)とは、憂いや心配事の象徴である。変化とは、進むことと退くことの象徴である。剛と柔とは、昼と夜の象徴である。六つの爻の動きは、天・地・人という三つの根源的な道筋を示しているのである。だから、君子がその身を置いて安らかでいられるのは、易の示す秩序に従っているからである。楽しんで味わうべきものは、爻に付けられた言葉である。だから君子は、平穏な時にはその象(かたち)を観察してその言葉を味わい、行動する時にはその変化を観察してその占いの結果を味わう。こうして、天からの助けを得て、何事も吉であり、不利益なことはなくなるのである。
第三章 彖(たん)とは、卦全体の象(かたち)について述べたものである。爻(こう)とは、変化について述べたものである。吉凶とは、その成功と失敗について述べたものである。悔吝(かいりん)とは、その小さな欠点や過ちについて述べたものである。咎(とが)なしとは、過ちをうまく補い、改善できるということである。このようなわけで、貴賤の序列があるのは、それぞれの爻位によるものである。小さな卦と大きな卦を区別するのは、卦そのものの構造による。吉凶を判断するのは、そこに付けられた言葉(辞)による。悔吝を憂えるのは、物事の微細な兆候(介)による。咎めなき状態へと奮い立つのは、後悔する心があるからである。このようなわけで、卦には大小の区別があり、言葉には険しいものと易しいものがある。言葉というものは、それぞれが指し示す方向性を持っているのである。
第四章 易は天地の法則と同じ基準で作られている。だから、天地の道理をあまねく覆い、秩序立てることができる。仰いでは天の文様を観察し、俯いては地の理を観察する。これによって、目に見えない世界(幽)と目に見える世界(明)の理屈を知ることができる。物事の始まりを根源まで探求し、その終わりに立ち返る。だから、死と生の道理を知ることができる。精妙な気が集まって物となり、魂がさまようことが変化となる。これによって、鬼神(人知を超えた霊的な存在)のありさまを知ることができる。易は天地と相似ているので、その法則に違うことがない。その知恵は万物に行き渡り、その道は天下を救うので、間違うことがない。あまねく行き渡りながらも、常軌を逸することがなく、天の理を楽しみ、自らの天命を知っているので、憂えることがない。大地に安んじ、仁の徳に篤いので、万物を愛することができる。天地の変化の法則をその範囲に収めて行き過ぎることがなく、万物をそれぞれの性質に応じて曲げ成して、一つとして見過ごすことがない。昼と夜の道理に通じているので、全てを理解している。だから、神は特定の形を持たず、易もまた固定した体を持たない、自由自在な働きなのである。
第五章 陰と陽が交互に現れること、これを「道」という。その道を受け継ぐものが「善」であり、それを個々のものとして完成させるのが「性(本性)」である。仁の徳を持つ者(仁者)はこれを見て「仁」といい、知恵ある者(知者)はこれを見て「知」という。一般の人々は毎日その道を使っているが、その存在に気づかない。だから、君子の道というものは、それを実践する者が少ないのである。その働きは、仁として外に現れ、その機能は内に秘められている。万物を奮い立たせながらも、聖人のように(天下のことを)共に憂えることはない。盛大な徳と偉大な事業とは、ここに至れり、といったところか。豊かに所有することを「大業」といい、日々新しくなっていくことを「盛徳」という。生命が生命を生み出していくこと、これを「易(変化)」という。象(かたち)を成すこと、これを「乾」といい、法則に倣うこと、これを「坤」という。数を極め、未来を知ること、これを「占」といい、変化に通じること、これを「事(事業)」という。陰陽の働きが人知では測りきれないこと、これを「神」という。
第六章 そもそも易というものは、広く、そして大きいものである。遠いことについて言えば、際限がない。近いことについて言えば、静かにして正しい。天地の間にある全ての事象について言えば、その道理は完全に備わっている。そもそも乾というものは、静止している時は専一であり、動く時は直進的である。だからこそ、大いなるものが生まれるのだ。そもそも坤というものは、静止している時は力を内に収めて閉じ、動く時は万物を生み出すために開く。だからこそ、広大なものが生まれるのだ。
第七章 孔子(あるいは、易の作者)は言う、「易というものは、その境地がなんと至高なものであろうか」。そもそも易とは、聖人がそれによって徳を尊び、事業を広げるためのものである。知恵は高く尊び、礼儀においては謙虚であるべきだ。高く尊ぶのは天に倣い、謙虚であるのは地に法(のっと)る。天と地がその位置を定め、易の法則はその中で行われる。生まれ持った本性を完成させ、それを保存し続けることこそが、道義の入り口なのである。
第八章 聖人は、天下の深遠な理を見出し、それを具体的な形に擬(なぞら)え、万物のありさまを象徴で示した。だから、それを「象」という。聖人は、天下の様々な動きを見て、それらがどのように会合し、通じ合うかを観察し、それに基づいて儀式や法則(典禮)を定め、言葉(辞)を繫(つ)けてその吉凶を判断した。だから、それを「爻」という。天下の最も深遠なことについて語っても、人々はそれを嫌悪することがない。天下の最も激しい動きについて語っても、人々はそれで混乱することがない。形に擬してから言葉にし、よく議論してから行動する。このように擬議することで、変化を成就させるのである。「鳴く鶴が日陰にいても、その子がこれに和する。わたしに良い酒盃がある、わたしはあなたと共にこれを分かち合おう」とは、孔子が言う、「君子が自分の部屋にいて、発する言葉が善いものであれば、千里の外までもがそれに呼応する。ましてや、その近くにいる者はなおさらだ。自分の部屋にいて、発する言葉が善くないものであれば、千里の外までもがそれに背く。ましてや、その近くにいる者はなおさらだ」。言葉は我が身から出て、人々に影響を与える。行いは身近なところから始まり、遠くまでその影響が現れる。言行は、君子にとって物事を動かす枢(かなめ)であり、機械の軸である。枢機の発動は、栄誉と恥辱の主である。言行は、君子が天地をも動かす所以(ゆえん)である。どうして慎まずにいられようか。
第九章 「同人(天火同人)は、最初は泣き叫ぶが後には笑う」とは、孔子が言う、「君子の道は、ある時は世に出て活動し、ある時は家にいて隠処し、ある時は沈黙を守り、ある時は語る。二人が心を同じくすれば、その鋭さは金属をも断ち切る。心を同じくした者同士の言葉は、その香りが蘭のようである」。「乾の卦辞にある元とは、善の長である。亨とは、美徳が集まることである。利とは、義が調和したものである。貞とは、物事の根本となる幹である」。君子は、仁を体得して人々の長となるに足り、美徳の集まりをもって礼儀に合致するに足り、万物を利することで義と調和するに足り、堅固な正しさをもって物事を担当するに足りる。君子とは、この四つの徳を行う者である。だから、(乾の卦辞は)「乾は元亨利貞」というのである。
第十章 「初九に曰く、潜龍用うる勿れ」とは、どういう意味か。孔子が言う、「龍の徳を持ちながらも、まだ隠れている者のことである。世の中の変化に動じず、名声を立てようともしない。世間から隠れても悩みはなく、正しいと認められなくても悩みはない。楽しければそれを行い、憂うべき状況であればそれに従わない。その志は確固としていて、引き抜くことはできない。これが潜龍である」。「九二に曰く、見龍田に在り、大人を見るに利し」とは、どういう意味か。孔子が言う、「龍の徳を持ち、正しく中庸の道にある者のことである。普段の言葉は誠実であり、普段の行いは慎み深い。邪(よこしま)なことを防いで、その誠実さを保ち、世の中を善くしてもその功績を誇らず、その徳は広大で人々を感化する。易に『見龍田に在り、大人を見るに利し』とあるのは、君子の徳のことである」。「九三に曰く、君子終日乾乾し、夕に惕若たれば厲うけれども咎无し」とは、何をか謂う。子曰く、君子は徳を進め、業を修める。忠と信は、徳を進めるためのものである。言葉を修め、その誠実さを確立することは、事業を安定させる所以である。至るべき時を知ってそこに至る者は、共に物事の兆しについて語ることができるだろう。終わるべき時を知ってそれに終わる者は、共に義理を保つことができるだろう。このようなわけで、高い地位にいても驕らず、低い地位にいても憂えることがない。だから、勤勉に励み、時に応じて警戒すれば、危うい状況であっても咎めはないのである。「九四に曰く、或は躍りて淵に在り、咎无し」とは、何をか謂う。子曰く、上の位と下の位を行き来して定まらないのは、邪なことをするためではない。進んだり退いたりして一定しないのは、仲間から離反するためではない。君子は徳を進め業を修め、時機を逃さず行動したいと願っているのだ。だから咎めはない。「九五に曰く、飛龍天に在り、大人を見るに利し」とは、何をか謂う。子曰く、同じ声は互いに応じ合い、同じ気は互いに求め合う。水は湿ったところへ流れ、火は乾いたところへ就く。雲は龍に従い、風は虎に従う。聖人が現れると万物はその徳を見る。天に本づく者は上に親しみ、地に本づく者は下に親しむ。すなわち、各々はその類に従うのである。「上九に曰く、亢龍悔有り」とは、何をか謂う。子曰く、地位は貴いが、その身を置くべき位がなく、高く昇りつめて民意もなく、賢人が下の位にいても補佐する者がいない。このようなわけで、動けば後悔があるのだ。
第十一章 「潜龍用うる勿れ」とは、まだ低い地位にいるからである。「見龍田に在り」とは、その徳の施しが普(あまね)く行き渡るからである。「終日乾乾」とは、正しい道を繰り返し行うからである。「或は躍りて淵に在り」とは、進んでも咎めがないからである。「飛龍天に在り」とは、徳の高い大人が事を成すからである。「亢龍悔有り」とは、窮まった時の災いだからである。「乾元用九」とは、天下が治まるからである。「潜龍用うる勿れ」とは、陽の気がまだ潜み隠れているからである。「見龍田に在り」とは、天下が文明の光で照らされるからである。「終日乾乾」とは、時と共に進んでいくからである。「或は躍りて淵に在り」とは、乾の道がここに革(あらた)まるからである。「飛龍天に在り」とは、すなわち天の徳の位にあるからである。「亢龍悔有り」とは、時と共に極まってしまうからである。「乾元用九」とは、すなわち天の法則を見るからである。
第十二章 乾の元とは、物事を始めさせ、そして成就させるものである。利と貞とは、人間の本性そのものである。乾は、初めによく美しい利益をもって天下を利するが、その利する所を自ら語ることはない。なんと偉大なことであろうか。偉大なるかな乾は、剛健で中正、純粋で精妙である。六つの爻がその働きを発揮し、あまねく万物の情に通じている。時に応じて六頭の龍に乗り、天を治める。雲がゆき雨が施され、天下は平らかになる。君子は、徳を完成させることを自らの行いとし、その行いは日々に現れるものである。「潜む」という言葉は、隠れてまだ現れず、行ってもまだ完成しない状態を言う。だから君子は、この段階では行動しないのである。君子は、学ぶことによって知識を聚(あつ)め、問うことによって物事を弁別し、寛容さをもってその境遇に安んじ、仁の心をもってそれを行う。易に「見龍田に在り、大人を見るに利し」とあるのは、君子の徳のことである。九三は、陽が重なり中庸を得ていない。上にいても天の位ではなく、下にいても田の位ではない。だから、勤勉に励み、その時に応じて警戒すれば、危うい状況であっても咎めはないのである。九四は、陽が重なり中庸を得ていない。上は天の位ではなく、下は田の位ではなく、中は人の位ではない。だから「或(あるい)は」と言うのである。「或は」と言うのは、疑い迷うことである。だから咎めはない。そもそも大人とは、天地と その徳を合わせ、日月とその明るさを合わせ、四季とその秩序を合わせ、鬼神とその吉凶を合わせるような人物である。天の運行より先に動いても天の理に違うことなく、天の運行より後に動いても天の時に従う。天でさえ違うことがないのだから、ましてや人間においてをや、鬼神においてをや(違うことがあろうか)。「亢(いきすぎ)」という言葉の意味は、進むことを知っていて退くことを知らず、存在することを知っていて滅びることを知らず、得ることを知っていて失うことを知らず、ということである。そのようなことができるのは、ただ聖人だけであろうか。進退存亡を知り、その上で正しさを失わない者、それこそがただ聖人なのである。
繫辞上伝が示す「宇宙と調和し、自らを変革する道」
「繫辞上伝」は、単なる易経の解説書ではありません。それは、宇宙の根本原理と、わたしたち人間の生きるべき道が、いかに深く響き合っているかを明らかにする、壮大な「人生の哲学書」です。この叡智の海から、わたしたちの「益々善成」の船旅を導く、いくつかの光る羅針盤を見つけ出すことができます。
1. 「変化」こそが生命の本質であると知り、その波を乗りこなす
- 繫辞伝の言葉: 「一陰一陽之謂道(一陰一陽、之を道と謂う)」「生生之謂易(生を生ずる、之を易と謂う)」
- わたしたちへのヒント: 繫辞伝は、この世界の根本原理が「変化し続けること(易)」そのものであると教えています。陰と陽が交互に現れ、絶えず新しい生命が生まれては変化していく。わたしたちの人生もまた、この大きな変化の流れの中にあります。良い時もあれば、悪い時もある。喜びもあれば、悲しみもある。大切なのは、その変化を恐れたり、逆らったりするのではなく、むしろそれを生命の自然なリズムとして受け入れ、その波に賢明に、そしてしなやかに乗っていくことです。「日々新たに、益々よくなる」とは、この絶え間ない変化の中で、常に自分自身を更新し、成長させていく、積極的な生き方そのものなのです。
2. 天地自然の法則に学び、それに倣(なら)うことで、道は開ける
- 繫辞伝の言葉: 「仰以觀於天文、俯以察於地理(仰いでは以て天文を観、俯しては以て地理を察す)」「與天地合其德(天地と其の德を合す)」
- わたしたちへのヒント: 繫辞伝は、聖人が常に「天地自然」を師としていたことを示しています。天の運行の確かさ、大地の包容力、四季の巡りの秩序…。わたしたちも、日々の生活の中で、自然の大きな智慧に耳を澄ませてみませんか。自然の法則に逆らわない生き方は、わたしたちの心に安定と調和をもたらします。自分自身の内なる徳を、この大いなる天地の徳と響き合わせる時、わたしたちの歩みは、宇宙からの力強い応援を得て、より確かで、より豊かなものとなるでしょう。
3. 言葉と行い(言行)を慎み、その絶大な影響力を自覚する
- 繫辞伝の言葉: 「言行、君子之樞機也。樞機之發、榮辱之主也(言行は、君子の樞機なり。樞機の発するは、榮辱の主なり)」
- わたしたちへのヒント: 第八章で孔子の言葉として語られるように、わたしたちが発する「言葉」と、日々積み重ねる「行い」は、自分自身の栄誉や恥辱を決定づけるだけでなく、千里の外にまで影響を及ぼし、時には天地をも動かすほどの、絶大な力を持っています。わたしたちは、この「言行」という、人生の最も重要な「枢(かなめ)」を、いかに慎重に、そして誠実に扱わなければならないかを、深く心に刻む必要があります。あなたのその一つの言葉、一つの行動が、あなた自身と、あなたの周りの世界を創造しているのです。
4. 自分の内なる「神明(しんめい)」、すなわち直感と誠実さを信頼する
- 原文: 「神无方而易无體(神は方无くして易は體无し)」「陰陽不測之謂神(陰陽測る可からざる、之を神と謂う)」
- わたしたちへのヒント: 繫辞伝は、人知を超えた働きである「神」は、特定の場所や形を持たず、陰陽の変化の、その測り知れない奥深さの中にこそ存在すると説きます。これは、わたしたちが「益々善成」の道を進む上で、論理や知識だけで全てを解決しようとするのではなく、自分自身の内なる直感、言葉では説明できない「感覚」、そして何よりも「真心」といった、目には見えないけれど確かな力を信頼することの重要性を示唆しています。頭で考えるだけでなく、心で感じ、魂の導きに従う。その時、わたしたちは人知を超えた、大いなる流れと繋がることができるのかもしれません。
5. 易の智慧を、「未来を拓くための道具」として積極的に活用する
- 繫辞伝の言葉: (聖人が易を作ったのは)「以通天下之志、以定天下之業、以斷天下之疑(以て天下の志を通じ、以て天下の業を定め、以て天下の疑いを斷ぜんがためなり)」
- わたしたちへのヒント: 易経は、単なる哲学書や占い本ではありません。それは、聖人が、わたしたちが人生における様々な「志」を成就させ、「事業」を安定させ、そして「疑い」や「迷い」を断ち切るために創り出した、非常に実践的な「智慧の道具」なのです。このブログでの学びもまた、その一環です。わたしたちも、この易の智慧を、ただ知るだけでなく、日々の生活の中で積極的に活用し、自分自身の未来をより善き方向へと創造していくための、力強いパートナーとしていきましょう。