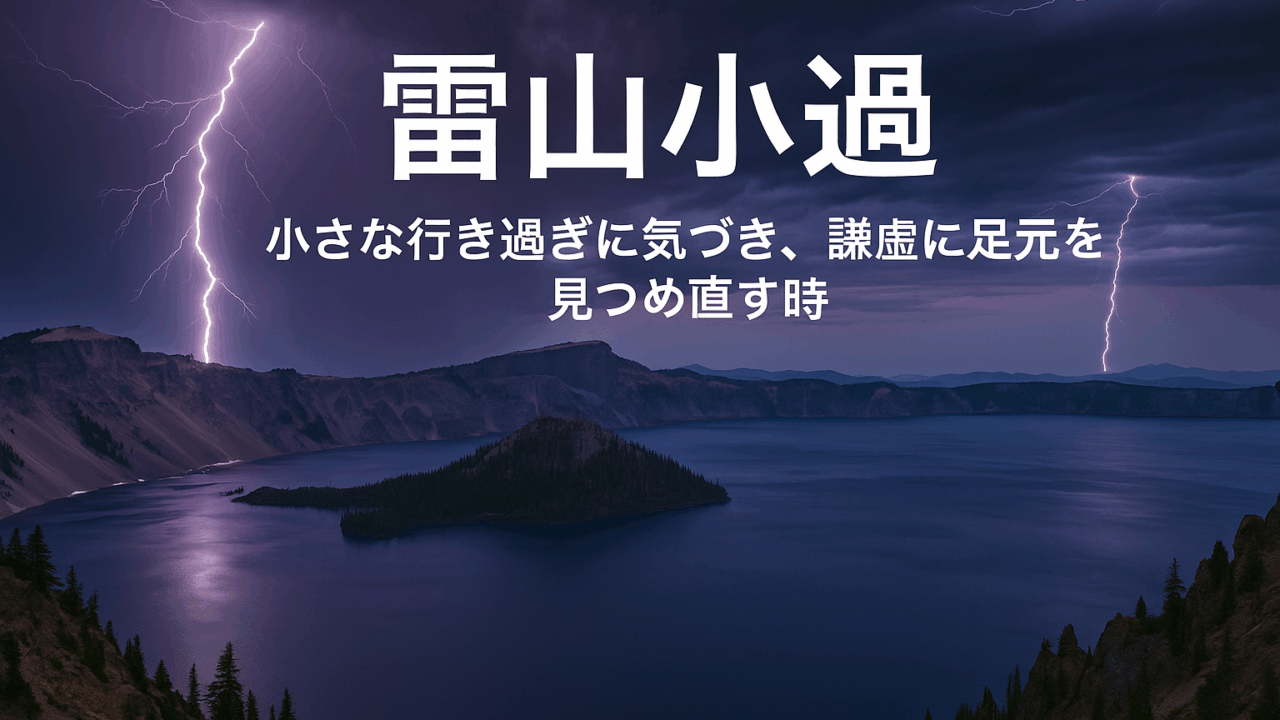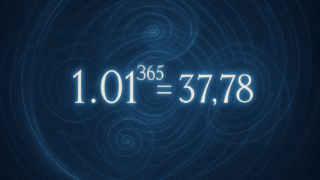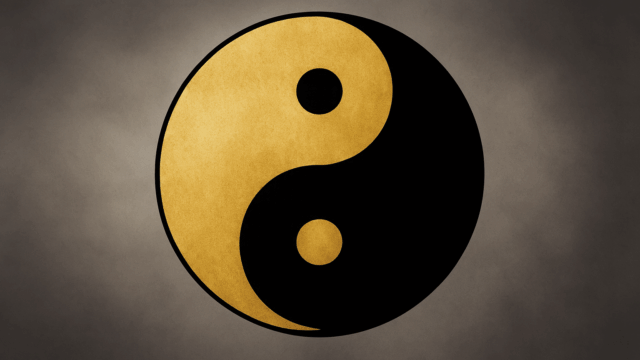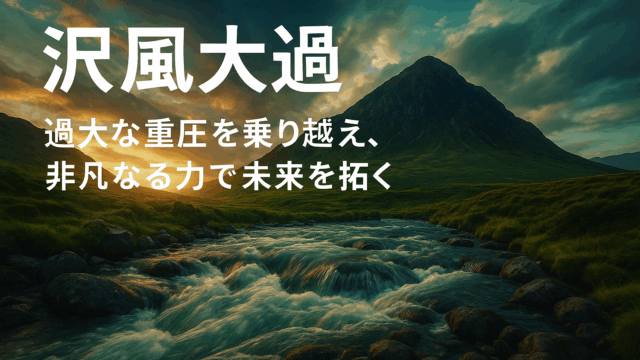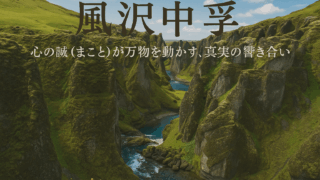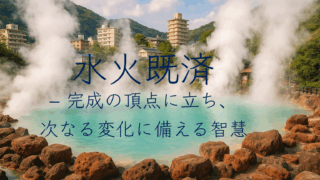【易経】 第62卦「雷山小過(らいざんしょうか)」– 小さな行き過ぎに気づき、謙虚に足元を見つめ直す時
1. 卦象(かしょう): ䷽

2. 名称(めいしょう): 雷山小過(らいざんしょうか)
3.【この卦のメッセージ】
上卦(じょうか):震(しん) – 雷、動く、奮い立つ、長男
下卦(かか):艮(ごん) – 山、止まる、篤実、少男
全体のイメージ: どっしりと静かに止まる山(艮)の上を、活発に動く雷(震)が轟き渡っている。この「雷山小過」の姿は、まるで鳥がその小さな体に不釣り合いなほど大きな翼(中央の二陽爻)を広げ、山の頂きを越えてさらに高く飛び立とうとするものの、上下の陰爻(弱い支え)のために不安定で、どこか危なっかしい様子を象徴しています。「小過」とは、「小さいものが過ぎる」、あるいは「少しだけ行き過ぎる」という意味です。 これは、大きな理想や目標に向かって勇み足になったり、些細な事柄にこだわり過ぎて本質を見失ったり、あるいは自分の実力以上のことをしようとして無理が生じている状況を示唆します。力強い陽のエネルギーが内側に過剰にあり、それを支える陰の要素が外側で弱いというアンバランスさが、この卦の核心です。しかし、この「小過」は、必ずしも大凶を意味するのではなく、その「行き過ぎ」に気づき、謙虚に、そして慎重に行動することで、かえって良い結果に繋がる可能性も秘めています。
卦辞(かじ)– この卦全体のテーマ
原文(漢文):小過。亨。利貞。可小事、不可大事。飛鳥遺之音。不宜上、宜下。大吉。
書き下し文:小過(しょうか)は亨(とお)る。貞(ただ)しきに利(よろ)し。小事(しょうじ)には可(か)なり、大事(だいじ)には可(べか)らず。飛鳥(ひちょう)之(これ)に音(おと)を遺(のこ)す。上(のぼ)るに宜(よろ)しからず、下(くだ)るに宜(よろ)し。大吉(だいきち)。
現代語訳:小過(少し行き過ぎる時)は、(慎重に対処すれば)願いは通る。正しい道を守ることが大切である。小さな事を行うのは良いが、大きな事を行うべきではない。飛び行く鳥がその鳴き声を残していくように、(今は大きな飛翔の時ではなく、戒めの声に耳を傾けるべきである)。上へ昇ろうとするのは良くない、むしろ下へ降りて謙虚に事に当たるのが良い。そうすれば大いに吉である。
ポイント解説:
この卦辞は、「小過」の時が、大きな野心や大事業には向かないものの、謙虚に、そして慎重に「小さな事」に取り組むならば、成功の可能性がある(亨る、貞しきに利し)と教えています。「飛鳥之に音を遺す」とは、高く飛び去る鳥が鳴き声を残していくように、今は大きな飛躍の時ではなく、むしろ天からの警告や、慎むべきであるというメッセージに耳を傾けるべきである、という比喩です。そして最も重要なのが「上るに宜しからず、下るに宜し、大吉」。つまり、高望みしたり、実力以上を求めたりする(上る)のではなく、むしろ謙虚に低い位置に身を置き(下る)、足元を固め、分相応の行動を心がけることが、この時期に大きな幸運(大吉)を掴む鍵であると、力強く示しています。
爻辞(こうじ)– 各爻(こう)が示す変化の機微と物語
初六(しょりく):
飛鳥(ひちょう)以(もっ)て凶(きょう)。
原文:飛鳥以凶。
書き下し文:飛鳥(ひちょう)以(もっ)て凶(きょう)。
現代語訳:鳥が(準備不足のまま)飛び立とうとする。これでは凶である。
ポイント解説:
「小過」の始まり。まだ力が弱く、準備も整っていないのに、いきなり高く飛び立とうとする(飛鳥)のは、無謀であり、必ず失敗し凶となります。自分の力量や状況を顧みず、焦って行動することの危険性を警告しています。まずは足元を固めることが先決です。
六二(りくじ):
其(そ)の祖(そ)に過(す)ぎ、其(そ)の妣(ひ)に遇(あ)う。其(そ)の君(きみ)に及(およ)ばず、其(そ)の臣(しん)に遇(あ)う。咎(とが)なし。
原文:過其祖、遇其妣。不及其君、遇其臣。无咎。
書き下し文:其(そ)の祖(そ)に過(す)ぎ、其(そ)の妣(ひ)に遇(あ)う。其(そ)の君(くん)に及(およ)ばず、其(そ)の臣(しん)に遇(あ)う。咎(とが)なし。
現代語訳:祖父を通り過ぎて、祖母に出会う。君主に直接会うことはできないが、その家臣には会うことができる。咎めはない。
ポイント解説:
この爻は、直接の目標(祖、君)には到達できないものの、それに準ずる身近な存在(妣、臣)とは適切に関わることができる、という状況を示しています。高望みせず、自分の分をわきまえ、身近なところでできる限りのことを誠実に行えば、大きな過ち(咎なし)はありません。分相応の行動と、身近な関係を大切にすることの重要性を示唆しています。
九三(きゅうさん):
之(これ)を過(す)ぎざれば防(ふせ)ぐ。從(したが)えば或(あるい)は之(これ)を戕(そこな)う。凶(きょう)。
原文:弗過防之。從或戕之。凶。
書き下し文:之(これ)を過(す)ぎざれば防(ふせ)ぐ。從(したが)えば或(あるい)は之(これ)を戕(そこな)う。凶(きょう)。
現代語訳:行き過ぎないようにと警戒しすぎる。しかし、そのためにかえって(下の者の進言などに)従ってしまうと、害を受けることがある。凶である。
ポイント解説:
九三は陽爻で力はありますが、過剰に警戒し、行き過ぎを恐れるあまり、かえって判断を誤りやすい時です。「之を過ぎざれば防ぐ」とは、慎重であることは良いのですが、それが度を越すと、柔軟性を失い、かえって下の者(陰爻)の甘言や誤った意見に従ってしまい(從えば或は之を戕う)、凶運を招きます。過度な警戒心や猜疑心は、正しい判断を妨げるという戒めです。
九四(きゅうし):
咎(とが)なし。之(これ)を過(す)ぎずして之(これ)に遇(あ)う。往(ゆ)けば厲(あやう)し必ず戒(いまし)めよ。永(なが)く貞(てい)に用(もち)うる勿(なか)れ。
原文:无咎。弗過遇之。往厲必戒。勿用永貞。
書き下し文:咎(とが)なし。之(これ)を過(す)ぎずして之(これ)に遇(あ)う。往(ゆ)けば厲(あやう)し必ず戒(いまし)む。永(なが)く貞(てい)に用(もち)うる勿(なか)れ。
現代語訳:咎めはない。行き過ぎることなく、適切に対処する。しかし、これ以上進んでいけば危険なので、必ず警戒しなければならない。この状態を長く続けてはならない。
ポイント解説:
この爻は、陽爻が陰位にあり、慎重さをもって行動するため、大きな過ち(咎なし)はありません。行き過ぎることなく(之を過ぎずして)、適切に状況に対応(之に遇う)できています。しかし、これ以上積極的に進んでいく(往けば)のは危険(厲し)が伴うため、常に警戒心(必ず戒む)が必要です。そして、この慎重な状態(あるいは、この時期のやり方)を、いつまでも続ける(永く貞に用うる勿れ)べきではない、という注意も含まれています。状況の変化に応じて、柔軟に対応を変える必要性を示唆しています。
六五(りくご):
密雲(みつうん)雨(あめ)ふらず、我(わ)が西郊(せいきょう)よりす。公(こう)弋(いぐるみ)して彼(か)の穴(あな)に在(あ)るを取(と)る。
原文:密雲不雨、自我西郊。公弋取彼在穴。
書き下し文:密雲(みつうん)雨(あめ)ふらず、我(わ)が西郊(せいきょう)よりす。公(こう)弋(よく)して彼(か)の穴(けつ)に在(あ)るを取(と)る。
現代語訳:厚い雲が空を覆っているが、まだ雨は降ってこない。それは我が西の郊外から次第に近づいてきている。君主が弓矢で、穴の中に隠れている獲物を捕らえる。
ポイント解説:
君主の位にあり、柔順中正の徳を備えています。「密雲雨ふらず」は、前の卦「風天小畜」の卦辞と同じで、恵みの雨(良い結果)が間近に迫っているが、まだその時ではない、という状況です。しかし、ここでは君主(公)が、巧みな手段(弋=いぐるみ、糸をつけた矢)を用いて、穴の中に隠れている獲物(解決すべき問題や、登用すべき人材の比喩)を的確に捕らえる、という積極的な側面も示されています。好機を待ちつつも、的確な手段で成果を得る知恵です。
上六(じょうりく):
之(これ)に遇(あ)わずして之(これ)を過(す)ぐ。飛鳥(ひちょう)之(これ)を離(はな)る。凶(きょう)。是(これ)を災眚(さいせい)と謂(い)う。
原文:弗遇過之。飛鳥離之。凶。是謂災眚。
書き下し文:之(これ)に遇(あ)わずして之(これ)を過(す)ぐ。飛鳥(ひちょう)之(これ)を離(り)す。凶(きょう)。是(こ)れを災眚(さいせい)と謂(い)う。
現代語訳:出会うべきものに出会わず、行き過ぎてしまう。飛び行く鳥が網にかかってしまうように、凶である。これを災難、過ちという。
ポイント解説:
「小過」の時の極点。もはや適切な限度を大きく超えてしまい、出会うべき大切なもの(好機や正しい道)にも出会えず(之に遇わずして)、ただ行き過ぎてしまう(之を過ぐ)状態です。それは、まるで鳥が不用意に網にかかってしまうように、自ら災難(凶、災眚)を招き寄せてしまうことを意味します。度を越した行動や、状況判断の誤りが、取り返しのつかない結果を招くことへの、最も強い警告です。
【雷山小過(らいざんしょうか)の「彖伝」】
原文 彖曰。小過、小者過而亨也。過以利貞、與時行也。柔得中、是以小事吉也。剛失位而不中、是以不可大事也。有飛鳥之象焉。飛鳥遺之音、不宜上、宜下、大吉。上逆而下順也。
書き下し文 彖(たん)に曰(いわ)く、小過(しょうか)は、小(しょう)なる者(もの)過(す)ぎて亨(とお)るなり。過(す)ぎて貞(てい)に利(よろ)しとは、時(とき)と與(とも)に行(おこな)えばなり。柔(じゅう)中(ちゅう)を得(う)、是(ここ)を以(もっ)て小事(しょうじ)には吉(きち)なるなり。剛(ごう)は位(くらい)を失(うしな)い中(ちゅう)ならず、是を以て大事(だいじ)には可(べか)らざるなり。飛鳥(ひちょう)の象(しょう)焉(これ)に有(あ)り。飛鳥(ひちょう)之(これ)に音(おと)を遺(のこ)す、上(のぼ)るに宜(よろ)しからず、下(くだ)るに宜(よろ)し、大吉(だいきち)とは、上(のぼ)れば逆(さか)らい下(くだ)れば順(じゅん)なればなり。
現代語訳 彖伝は言う。小過とは、小さいもの(陰爻)が(陽爻よりも)多く、行き過ぎているが、それでも願いは通るということである。「行き過ぎてはいるが、正しい道を守ることが大切である」というのは、時の流れと共に適切に行動するからである。(六五の)柔順なものが中心の徳を得ている。だから「小さな事柄においては吉」なのである。(九三、九四の)剛健なものは、その正しい位を失い、中心にもいない。だから「大きな事柄は成し遂げられない」のである。この卦には、飛び行く鳥の象徴がある。(卦辞の)「飛び行く鳥がその鳴き声を残していくように、上へ昇るのは良くない、下へ降りて謙虚にするのが良い、そうすれば大いに吉である」というのは、上へ行こうとすれば時の流れに逆らい、下へ行こうとすれば時の流れに順うからである。
ポイント解説「彖伝」は、この時の本質が、陰という「小なるもの」が、陽という「大なるもの」よりも「過ぎている」アンバランスな状態にあると説きます。
わたしたちの道においても、時に、細部へのこだわりが本質を見失わせたり、過剰な心配や配慮が、大胆な行動を妨げたりすることがあります。
まずは、自分自身の生活や心の中に、そのような「小さな行き過ぎ」がないか、正直に見つめてみましょう。そのアンバランスに気づくことこそが、軌道修正への第一歩です。
雷山小過の時には、大きな事業や、大胆な改革(大事)には向かない時であることを明確に示しています。なぜなら、それを支えるべき力(剛)が、正しい位置にいないからです。しかし、柔順な徳が中心にあるため、「小さな事」においては、むしろ吉なのです。常に大きな成果を目指すことだけが重要なことではありません。この「小過」の時のように、今は大きな目標を一旦脇に置き、目の前にある日々の小さな仕事、家族とのささやかな時間、自分自身の心のケアといった「小事」に、心を込めて丁寧に取り組む。その積み重ねが、結果として「大吉」という、この上ない幸運をもたらすのです。
大象伝(たいしょうでん)– この卦の形から学ぶ、理想のあり方
原文(漢文):象曰。山上有雷、小過。君子以行過乎恭、喪過乎哀、用過乎儉。
書き下し文:象(しょう)に曰(いわ)く、山(やま)の上(うえ)に雷(らい)有(あ)るは小過(しょうか)なり。君子(くんし)以(もっ)て行(おこない)は恭(きょう)に過(す)ぎ、喪(そう)は哀(あい)に過(す)ぎ、用(よう)は儉(けん)に過(す)ぐ。
現代語訳:** 象伝は言う。山の上に雷が鳴り響いているのが小過の形である(雷は本来天高くにあるべきもので、山の上にあるのは少し行き過ぎている)。君子(人格者)はこれに倣(なら)い、行動においては恭(うやうや)しさに過ぎるほど丁寧にし、喪に服する時は哀(かな)しみに過ぎるほど深く悲しみ、費用を抑える時は儉(けんやく)に過ぎるほど質素にする。
ポイント解説:
山の上に雷があるのは、雷の力が本来あるべき場所(天)よりも低い位置で、しかしそれでも山よりは高いという、アンバランスで「少し行き過ぎた」状態を象徴します。これを見た君子は、この「過ぎる」という性質を、ネガティブな方向ではなく、むしろポジティブな方向で意識的に実践します。つまり、「行動は恭しさに過ぎる(謙虚すぎるほど謙虚に)」「喪は哀しみに過ぎる(心からの悲しみを十分に表現する)」「費用は倹約に過ぎる(質素倹約を徹底する)」。これは、自己中心的で傲慢な「行き過ぎ」を戒め、むしろ謙虚さ、誠実さ、質素さといった美徳の側へ「少し過ぎる」くらいに身を処することが、この「小過」の時を賢明に乗り切る道である、という深い智慧です。
【むすび】
雷山小過の卦は、わたしたちが人生において、つい「行き過ぎて」しまいそうになる時、あるいは「小さなこと」に囚われてしまう時に、いかにして謙虚さを保ち、本質を見失わず、そしてその状況を「益々善成」の糧としていくかという、繊細で重要な智慧を授けてくれます。
- 1. 「上(のぼ)るに宜(よろ)しからず、下(くだ)るに宜(よろ)し」 – 高望みせず、まず足元を固める謙虚さを: わたしたちが何か大きな目標に向かう時、あるいは自分の実力以上のことに挑戦しようとする時、雷山小過は「上るに宜しからず、下るに宜し」と、まずは高望みをせず、謙虚に自分の足元を見つめ直し、基礎を固めることの重要性を教えています。わたしたちの道もまた、地道な一歩の積み重ねから始まるのです。焦らず、分相応のところから始める勇気を持ちましょう。
- 2. 「行(おこない)は恭(きょう)に過(す)ぎ、喪(そう)は哀(あい)に過(す)ぎ、用(よう)は儉(けん)に過(す)ぐ」 – あなたの美徳を、あえて「少し過ぎる」くらいに実践してみよう: 大象伝が示すように、この「小過」の時には、謙虚さ、誠実な感情表現、そして質素倹約といった美徳を、むしろ「少し過ぎる」くらいに意識して実践することが、バランスを保ち、周囲からの信頼を得る道となります。わたしたちも、日々の行動において、相手への敬意を「これでもか」というほど示したり、物事を大切に使い、無駄を徹底して省いたりする。その「行き過ぎた美徳」が、かえってわたしたちの内なる輝きを増し、「益々善成」の確かな土台を築いてくれるでしょう。
- 3. 「飛鳥(ひちょう)之(これ)に音(おと)を遺(のこ)す」 – 天からの小さな「警告」や「サイン」に耳を澄ませて: 卦辞にある「飛鳥之に音を遺す」とは、わたしたちが何かに夢中になったり、勢いづいていたりする時に、ふと聞こえてくる「ちょっと待って」「本当にそれで大丈夫?」という、天からの小さな警告や、内なる直感の声かもしれません。日々よくなるためには、そのような微細なサインにも敏感に気づき、時には立ち止まって自分自身を見つめ直す、謙虚な姿勢が大切です。
- 4. 「小事(しょうじ)には可(か)なり」 – 大きなことよりも、目の前の「小さなこと」に心を込めて: 「小過」の時は、大きな成果や派手な成功を求めるには適していません。むしろ、日々の生活の中にある「小さなこと」――例えば、家族との会話、仕事の細やかな作業、自分自身の心身のケアといった――に、丁寧に心を込めて取り組むことが推奨されます。その一つひとつの小さな積み重ねが、やがて大きな力となり、わたしたちの人生を静かに、しかし確実に「益々よく」していくのです。
雷山小過の時は、わたしたちの謙虚さ、慎重さ、そして日常の小さなことへの誠実さが試される時です。しかし、この卦は決してわたしたちを萎縮させるものではありません。むしろ、その「小さな行き過ぎ」への気づきを通して、わたしたちが本当に大切にすべきこと、そして地に足のついた確かな成長とは何かを、深く教えてくれているのです。この卦の智慧を胸に、わたしたちもまた、日々の小さな一歩を大切にしながら、謙虚に、そして誠実に、道を歩んでいきましょう。