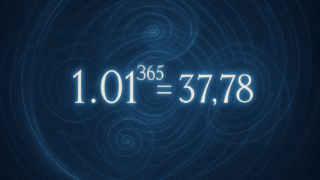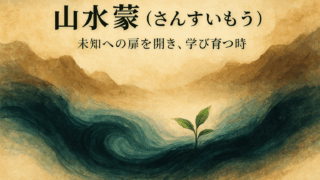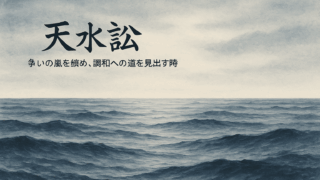【易経 】第5卦「水天需(すいてんじゅ)」– 時を待ち、心を養い、希望の雨を呼ぶ

1. 卦象: ䷄
2. 卦名: 水天需(すいてんじゅ)
3. 【この卦のメッセージ】
上卦:坎(かん) – 水、険難、陥る、悩み、雲
下卦:乾(けん) – 天、創造、剛健、父性、龍
全体のイメージ: 力強く、どこまでも昇りゆこうとする天(乾)のエネルギーが、その行く手前方に、険しい水(坎)や厚い雲が立ち込めているのに遭遇している。この「水天需」の姿は、まさに前途に困難や障害が予測され、進みたくても進めない、慎重に「待つ」ことを余儀なくされている状況を象徴しています。「需」という文字は、元来、雨乞いの儀式で雨が降るのを待つ巫女の姿を表すとも言われ、「待つ」「必要とする」「求める」といった意味合いを持ちます。 しかし、この「待つ」は、決して無為に時間を過ごすことではありません。天の上に雲が立ち込め、やがて恵みの雨が降るように、この待ち時間の中には、未来への大きな可能性と、それを実らせるための準備期間という、積極的な意味が込められているのです。
卦辞– この卦全体のテーマ
1. 原文(漢文): 需。有孚、光亨。貞吉。利渉大川。
2. 書き下し文: 需(じゅ)は孚(まこと)有り。光(おお)いに亨(とお)る。貞(ただ)しければ吉(きち)。大川(たいせん)を渉(わた)るに利(よろ)し。
3.現代語訳: 需の時は、誠実な心を持っていれば、その願いは光明に照らされ、大きく通る。正しい道を守り続ければ吉である。そして(時が至れば)大きな川を渡るような困難な事業も成し遂げると良い。
ポイント解説:
「需」は「待つ」時ですが、卦辞は驚くほどポジティブです。「孚(まこと)有り」とは、内なる誠実さ、確信、そして天への信頼を意味します。この誠実な心を持って待ち続ければ、やがて状況は好転し、光り輝くような成功(光亨)が得られると約束しています。「貞吉」は、その間も正しい道徳や姿勢を貫くことの重要性を示します。そして特筆すべきは、「利渉大川(大きな川を渡るのに利あり)」。これは、困難な待ちの期間を誠実に過ごし、十分に力を蓄えたならば、やがて大きな困難を乗り越え、大事業を成し遂げるチャンスが到来することを力強く示唆しているのです。つまり、「待つ」ことは、未来への飛躍のための準備期間なのです。
爻辞(こうじ)– 各爻(こう)が示す変化の機微と物語
初九
原文:需于郊。利用恆。无咎。
書き下し文:郊(こう)に需(ま)つ。恒(つね)に用(もち)うるに利(よろ)し。咎(とが)なし。
現代語訳:郊外の広々とした場所で待つ。常に変わらぬ平常心を保つのが良い。そうすれば咎めはない。
ポイント解説:
まだ危険(水)からは遠い、比較的安全な郊外で待つ段階です。焦って危険に近づく必要はありません。ここでは、心を平静に保ち、普段通りの生活を送りながら(恒に用うる)、じっくりと時の至るのを待つのが最善です。そうすることで、無用な災いを避け、咎めなく過ごせます。
九二
原文:需于沙。小有言、終吉。
書き下し文:沙(すな)に需(ま)つ。小(すこ)しく言(げん)有(あ)れども、終(つい)には吉(きち)。
現代語訳:砂地のような少し不安定な場所で待つ。多少の悪口や批判(小さな言)があるかもしれないが、最終的には吉となる。
ポイント解説:
危険(水)に少し近づいた、砂地のような場所で待つ状況です。足場がやや不安定で、周囲から「なぜ動かないのか」「大丈夫なのか」といった、些細な批判や噂話(小しく言有り)が聞こえてくるかもしれません。しかし、動揺せず、誠実な心を保ち続ければ、やがてそれらの声も消え、最終的には良い結果(終に吉)が得られます。周囲の雑音に惑わされず、自分の信念を貫く時です。
九三
原文: 需于泥。致寇至。
書き下し文: 泥(でい)に需(ま)つ。寇(こう)の至(いた)るを致(いた)す。
現代語訳:泥濘(ぬかるみ)のような危険な場所で待つ。それは自ら賊(災い)を招き寄せることになる。
ポイント解説:
危険(水)のすぐ手前、泥のような非常に不安定で危険な場所に身を置いて待っている状態です。このような場所に留まることは、自ら災難(寇)を引き寄せてしまうことになります。不用意に危険に近づきすぎたり、状況判断を誤ったりすることへの強い警告です。すぐにその場を離れ、安全な場所へ移るべきです。
六四
原文:需于血。出自穴。
書き下し文:血(ち)に需(ま)つ。穴(けつ)より出(い)づ。
現代語訳:血を見るような危険な状況の中で待っている。しかし、やがてその窮地(穴)から脱出することができる。
ポイント解説:
まさに危険(坎水)の真っ只中、血を見るような非常に困難で緊迫した状況に陥っています。しかし、この爻は陰爻でありながら陽位にあり、柔順でありながらも困難に対処しようとする意志を示します。絶望的な状況に見えても、冷静さを失わず、柔軟に対応することで、やがてその苦境(穴)から抜け出すことができるという、かすかな希望の光を示しています。諦めない心が重要です。
九五
原文:需于酒食。貞吉。
書き下し文:酒食(しゅし)に需(ま)つ。貞(てい)なれば吉(きち)。
現代語訳:酒や食事を楽しみながら、ゆったりと待つ。正しい道を守っていれば吉である。
ポイント解説:
危険が去り、安心して飲食を楽しみながら、ゆったりとした気持ちで待つことができる、非常に恵まれた状態です。これは、これまでの誠実な待ちの姿勢と、内なる徳がもたらした結果でしょう。この安定した状況にあっても、驕ることなく、正しい道(貞)をしっかりと守り続けることで、さらなる吉運(吉)を維持し、享受することができます。心豊かに、しかし油断なく待つ時です。
上六
原文:入于穴。有不速之客三人來。敬之終吉。
書き下し文:穴(あな)に入(い)る。速(すみ)やかならざるの客(かく)三人(さんにん)来(きた)る。之(これ)を敬(うやま)えば終(つい)には吉(きち)。
現代語訳:待ちきれず、あるいは状況を見誤り)自ら穴(困難)に入ってしまう。そこに招かれざる客が三人やってくる。しかし、彼らを敬意をもって迎え入れれば、最終的には吉となる。
ポイント解説:**
需の時の最後の段階。待ちきれなかったり、状況判断を誤ったりして、自ら困難な状況(穴)に足を踏み入れてしまうことを示します。そこに、予期せぬ厄介な客(不速の客三人)がやってきて、事態はさらに複雑になるかもしれません。しかし、そのような状況に陥っても、パニックにならず、相手を敬う心(之を敬えば)をもって誠実に対応すれば、最終的にはその困難を乗り越え、良い結果(終に吉)を得ることができます。最後まで希望を捨てず、誠意を尽くすことの大切さを教えています。
【水天需(すいてんじゅ)の彖伝】〜全体像〜
原文 彖曰。需、須也。險在前也。剛健而不陷、其義不困窮矣。需有孚、光亨貞吉。位乎天位、以正中也。利渉大川、往有功也。
書き下し文 彖(たん)に曰(いわ)く、需(じゅ)は、須(ま)つなり。險(けん)前(まえ)に在(あ)るなり。剛健(ごうけん)にして陷(おちい)らざるは、其(そ)の義(ぎ)困窮(こんきゅう)せざればなり。需(じゅ)は孚(まこと)有(あ)り、光(おお)いに亨(とお)りて貞(てい)に吉(きち)とは、天位(てんい)に位(くらい)して、以(もっ)て正中(せいちゅう)なればなり。大川(たいせん)を渉(わた)るに利(よろ)しとは、往(ゆ)きて功(こう)有(あ)ればなり。
現代語訳 彖伝は言う。需とは、待つということである。険しい困難が目の前にあるからだ。しかし、(内なる)剛健な徳によって、その困難に陥ることがないのは、その本質が困窮するようなものではないからである。「需は誠実さがあれば、その願いは光り輝き、大きく通って、正しさを守ることで吉となる」というのは、(九五の君主が)天の位にあって、正しく中庸の道を得ているからである。「大きな川を渡るのに良い」というのは、進み行けば必ず功績があるからである。
ポイント解説
「待つ」という状況が生まれるのは、多くの場合、目の前に何らかの困難や障害があるからです。「彖伝」は、まずその現実を直視することから始めます。なぜ今、待たなければならないのか。その「險」の正体は何なのか。それを冷静に、そして客観的に分析すること。それが、賢明な「待ち方」の第一歩です。問題を曖昧にしたまま、ただ時間を過ごすのは、本当の意味での「需」ではありません。
「待つ」時間において、最も大切な心のあり方は、「孚(まこと)」、すなわち誠実さです。目標に対して、自分自身に対して、そして周りの人々に対して、誠実であり続けること。その一貫した誠実な姿勢が、やがては信頼を生み、光り輝くような形で、あなたの願いを大きく成就(光亨)させるでしょう。そして、その誠実さを最後まで貫き通すこと(貞)が、最終的な成功(吉)を確かなものにするのです。待っている間も、決して心を腐らせず、誠実さを磨き続けることです。
大象伝(たいしょうでん)– この卦の形から学ぶ、理想のあり方
原文(漢文): 象曰。雲上于天、需。君子以飲食宴樂。
書き下し文: 象(しょう)に曰(いわ)く、雲(くも)天(てん)に上(のぼ)るは需(じゅ)なり。君子(くんし)以(もっ)て飲食(いんしょく)し宴樂(えんらく)す。
現代語訳:象伝は言う。雲が天に昇り、やがて雨をもたらそうとしているのが需の形である。君子(人格者)はこれに倣(なら)い、(雨を待つ間)飲食を楽しみ、宴を開いて心安らかに過ごす。
ポイント解説:
天の上に雲が立ち昇り、恵みの雨が降るのを待つ。これが「需」の象徴です。君子は、この雨(好機や解決)を焦って求めるのではなく、その時が来るまで、飲食を楽しみ、宴を開くように、心身を養い、精神的なゆとりを持って、泰然自若として待つのです。「飲食宴樂」とは、単なる享楽ではなく、来るべき時に備えてエネルギーを蓄え、心を豊かに保ち、そして天の時を信頼して待つ、という積極的で賢明な「待ち」の姿勢を意味しています。
むすび
水天需の卦は、わたしたちが人生で直面する「待つべき時」を、いかに賢く、そして豊かに過ごすかという、深い智慧を授けてくれます。
- 1. 「待つ」ことは「何もしない」ことではない – 内なる力を養う、積極的な時間と捉えよう: 目標に向かって進んでいる時、予期せぬ障害や停滞期は必ず訪れます。そんな時、水天需は「焦らず待ちなさい」と教えてくれます。しかし、それは決して諦めや怠惰ではありません。むしろ、その待ち時間を、自分自身の実力を高め、知識を深め、心身を整えるための「積極的な充電期間」と捉えましょう。内なる力を養うことで、次にチャンスが来た時に、力強く飛躍できるのです。
- 2. 「孚(まこと)」の心を胸に、希望の光を灯し続けよう: 卦辞が示すように、待つ時に最も大切なのは「孚(まこと)」、すなわち誠実な心、内なる真実、そして未来への信頼です。どんなに先が見えないように感じても、「必ず道は開ける」「この経験は無駄にはならない」と、自分自身と未来を信じ続けること。その誠実な心が、やがて「光亨(光り輝く成功)」を引き寄せるのです。
- 3. 「飲食宴樂」の智慧 – 待つ間も、心と体を健やかに養おう: 大象伝が教えるように、待つ間は、自分自身を大切に「養う」時です。バランスの取れた食事を楽しみ、質の高い睡眠をとり、心をリフレッシュするような趣味や活動(宴樂)に時間を使いましょう。心身が健やかで、エネルギーに満ちていてこそ、いざという時に最高のパフォーマンスを発揮できます。「待つ」時間を、自分を磨き、癒やす貴重な機会とするのです。
- 4. 状況を見極め、適切な「待ち場所」を選び、そして時が来たら「大川を渉る」勇気を: 爻辞は、待つ場所や状況によって、その結果が大きく変わることを示しています。危険な場所(泥)からは速やかに離れ、安全な場所(郊)で力を蓄え、そして時には周囲の雑音(沙での言)に惑わされず、信念を貫く。そして、卦辞が最後に示すように、十分に準備が整い、時が満ちたと判断したならば、勇気を持って困難な挑戦(大川を渉る)に踏み出すのです。待つことと行動することの、絶妙なバランスが求められます。
水天需の時は、わたしたちの忍耐力、信頼、そして未来を見通す智慧が試される時です。しかし、この「待つ」という行為の中にこそ、わたしたちが内面的に大きく成長し、より豊かな実りを得るための、かけがえのないチャンスが隠されています。焦らず、騒がず、しかし希望を胸に、心豊かにその時を待ちましょう。
必ずや、恵みの雨がわたしたちの大地を潤す日がやってきます。