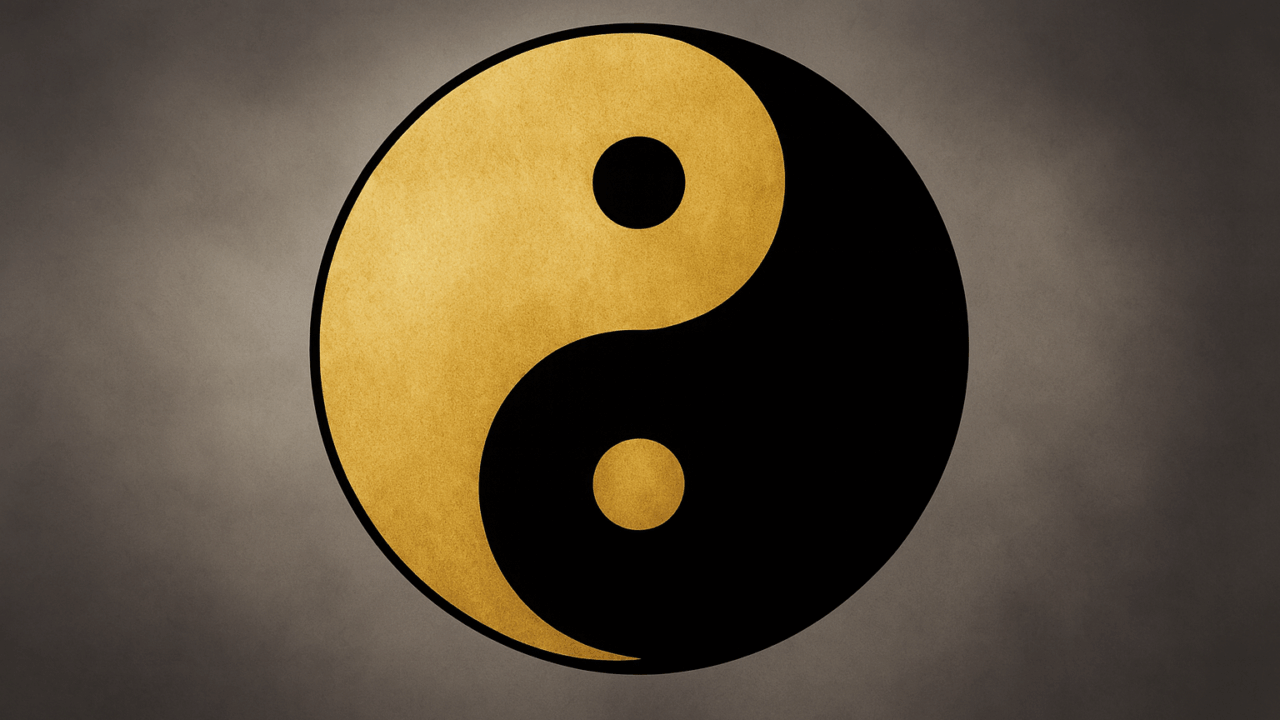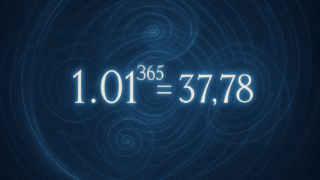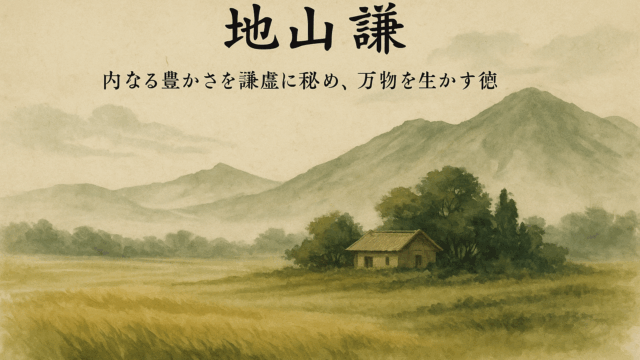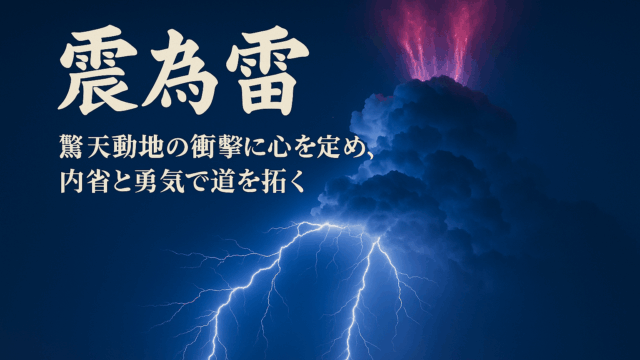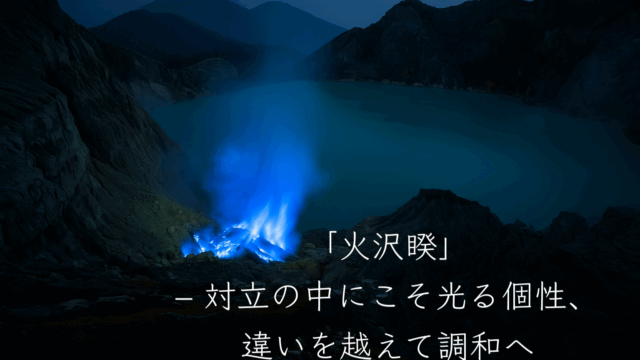【易経】「文言伝」– 乾坤の徳に学び、君子たる道を探る
易経の源流 – 「文言伝」が解き明かす、天と地の深遠な智慧
ブログを訪れてくださり、ありがとうございます。
今回は易経の解説書「十翼」の中でも、ひときわ深い哲学的思索に満ちた「文言伝(ぶんげんでん)」の記事にです。
「文言伝」は、他の伝とは異なり、ただひたすらに「乾」と「坤」の二卦についてのみ、その言葉の一つひとつを、その徳のあり方を、繰り返し、様々な角度から、美しく、そして厳しく解説していきます。それは、わたしたち人間が目指すべき理想の姿、すなわち「君子」とはいかにして天の創造力と地の受容力を自己の内に体現し、生きていくべきかを説き明かす、魂の教科書なのです。
この記事では、まず「文言伝」の全文を、「原文」「書き下し文」「現代語訳」の形で、その格調高い言葉の世界をありのままに感じていただきます。そして最後に、この乾坤の二元論から、かけがえのない智慧を一緒に読み解いていきましょう。
【文言伝】
乾卦 原文
元者、善之長也。亨者、嘉之會也。利者、義之和也。貞者、事之幹也。君子體仁足以長人、嘉會足以合禮、利物足以和義、貞固足以幹事。君子行此四德者、故曰、乾、元亨利貞。 初九曰、潛龍勿用。何謂也。子曰、龍德而隱者也。不易乎世、不成乎名。遯世无悶、不見是而无悶。樂則行之、憂則違之。確乎其不可拔、潛龍也。 九二曰、見龍在田、利見大人。何謂也。子曰、龍德而正中者也。庸言之信、庸行之謹。閑邪存其誠、善世而不伐、德博而化。易曰、見龍在田、利見大人。君德也。 九三曰、君子終日乾乾、夕惕若厲无咎。何謂也。子曰、君子進德脩業。忠信、所以進德也。脩辭立其誠、所以居業也。知至至之、可與幾也。知終終之、可與存義也。是故居上位而不驕、在下位而不憂。故乾乾因其時而惕、雖厲无咎矣。 九四曰、或躍在淵、无咎。何謂也。子曰、上下无常、非為邪也。進退无恆、非離群也。君子進德脩業、欲及時也、故无咎。 九五曰、飛龍在天、利見大人。何謂也。子曰、同聲相應、同氣相求。水流濕、火就燥。雲從龍、風從虎。聖人作而萬物覩。本乎天者親上、本乎地者親下。則各從其類也。 上九曰、亢龍有悔。何謂也。子曰、貴而无位、高而无民、賢人在下位而无輔、是以動而有悔也。 潛龍勿用、下也。見龍在田、時舍也。終日乾乾、行事也。或躍在淵、自試也。飛龍在天、上治也。亢龍有悔、窮之災也。乾元用九、天下治也。 潛龍勿用、陽在下也。見龍在田、德施普也。終日乾乾、反復道也。或躍在淵、進无咎也。飛龍在天、大人造也。亢龍有悔、與時偕極也。乾元用九、乃見天則。 乾元者、始而亨者也。利貞者、性情也。乾始能以美利利天下、不言所利、大矣哉。大哉乾乎、剛健中正、純粹精也。六爻發揮、旁通情也。時乘六龍、以御天也。雲行雨施、天下平也。 君子以成德為行、日可見之行也。潛之為言也、隱而未見、行而未成、是以君子弗用也。 君子學以聚之、問以辨之、寬以居之、仁以行之。易曰、見龍在田、利見大人。君德也。 九三重剛而不中、上不在天、下不在田。故乾乾因其時而惕、雖厲无咎。 九四重剛而不中、上不在天、下不在田、中不在人。故或之。或之者、疑之也、故无咎。 夫大人者、與天地合其德、與日月合其明、與四時合其序、與鬼神合其吉凶。先天而天弗違、後天而奉天時。天且弗違、而況於人乎、況於鬼神乎。 亢之為言也、知進而不知退、知存而不知亡、知得而不知喪。其唯聖人乎。知進退存亡而不失其正者、其唯聖人乎。
【乾卦書き下し文】
元(げん)は、善(ぜん)の長(ちょう)なり。亨(こう)は、嘉(か)の会(かい)なり。利(り)は、義(ぎ)の和(わ)なり。貞(てい)は、事(こと)の幹(かん)なり。君子(くんし)は仁(じん)を體(たい)して以て人(ひと)に長(ちょう)たるに足(た)り、嘉会(かかい)以て禮(れい)に合(がっ)するに足り、物(もの)を利(り)して以て義(ぎ)を和(わ)するに足り、貞固(ていこ)にして以て事(こと)を幹(つかさど)るに足る。君子(くんし)此(こ)の四德(しとく)を行(おこな)う者(もの)、故(ゆえ)に曰く、乾は元亨利貞(げんこうりてい)、と。 初九(しょきゅう)に曰(いわ)く、潜龍(せんりゅう)用(もち)うる勿(なか)れ。何(なに)をか謂(い)う。子(し)曰(いわ)く、龍德(りゅうとく)有(あ)りて隱(かく)るる者(もの)なり。世(よ)に易(か)えられず、名(な)を成(な)さず。世(よ)を遯(のが)れて悶(うれ)うること无(な)く、是(ぜ)とせられざるを見(み)ても悶うること无し。樂(たの)しめば則(すなわち)之(これ)を行(おこな)い、憂(うれ)うれば則ち之に違(たが)う。確乎(かくこ)として其(そ)れ抜(ぬ)く可(べか)からざるは、潜龍(せんりゅう)なり。 九二(きゅうじ)に曰く、見龍(けんりゅう)田(でん)に在(あ)り、大人(たいじん)を見(み)るに利(よろ)し。何(なに)をか謂う。子曰く、龍德有りて正中(せいちゅう)なる者なり。庸言(ようげん)之(これ)を信(しん)にし、庸行(ようこう)之を謹(つつし)む。邪(じゃ)を閑(ふせ)ぎて其(そ)の誠(まこと)を存(そん)し、世(よ)を善(よ)くして伐(ほこ)らず、德(とく)博(ひろ)くして化(か)す。易(えき)に曰(いわ)く、見龍(けんりゅう)田に在り、大人を見るに利し、とは君德(くんとく)なり。 九三(きゅうさん)に曰く、君子(くんし)終日(しゅうじつ)乾乾(けんけん)し、夕(ゆうべ)に惕若(てきじゃく)たれば厲(あやう)うけれども咎(とが)无(な)し。何をか謂う。子曰く、君子(くんし)は德(とく)を進(すす)め業(ぎょう)を脩(おさ)む。忠信(ちゅうしん)は、德を進むる所以(ゆえん)なり。辭(じ)を脩(おさ)め其(そ)の誠(まこと)を立(た)つるは、業(ぎょう)に居(お)る所以なり。至(いた)るを知(し)りて之に至(いた)るは、與(とも)に幾(き)す可(べ)きなり。終(おわ)るを知りて之に終るは、與に義(ぎ)を存(そん)す可きなり。是(こ)の故(ゆえ)に上位(じょうい)に居(お)りて驕(おご)らず、下位(かい)に在(あ)りて憂(うれ)えず。故(ゆえ)に乾乾(けんけん)として時(とき)に因(よ)りて惕(おそ)るれば、厲(あやう)しと雖(いえど)も咎(とが)无(な)し。 九四(きゅうし)に曰く、或(あるい)は躍(おど)りて淵(ふち)に在(あ)り、咎(とが)无(な)し。何をか謂う。子曰く、上下(じょうげ)常(つね)无(な)きは、邪(じゃ)を為(な)すに非(あら)ざるなり。進退(しんたい)恆(つね)无(な)きは、群(ぐん)を離(はな)るるに非ざるなり。君子(くんし)は德を進め業を脩め、時(とき)に及(およ)ばんことを欲(ほっ)す、故に咎无し。 九五(きゅうご)に曰く、飛龍(ひりゅう)天(てん)に在(あ)り、大人(たいじん)を見るに利し。何をか謂う。子曰く、同聲(どうせい)相(あい)應(おう)じ、同氣(どうき)相求(あいもと)む。水(みず)は濕(うるお)えるに流(なが)れ、火(ひ)は燥(かわ)けるに就(つ)く。雲(くも)は龍(りゅう)に從(したが)い、風(かぜ)は虎(とら)に從う。聖人(せいじん)作(おこ)りて万物(ばんぶつ)覩(み)る。天(てん)に本(もと)づく者(もの)は上(かみ)に親(した)しみ、地(ち)に本づく者は下(しも)に親しむ。則(すなわち)各(おのおの)其(そ)の類(るい)に從うなり。 上九(じょうきゅう)に曰く、亢龍(こうりゅう)悔(くい)有(あ)り。何をか謂う。子曰く、貴(たっと)くして位(くらい)无(な)く、高(たか)くして民(たみ)无く、賢人(けんじん)下位(かい)に在(あ)りて輔(たす)け无(な)し、是(ここ)を以て動(うご)けば悔(くい)有(あ)るなり。 「潜龍(せんりゅう)用(もち)うる勿(なか)れ」とは、下(しも)なればなり。「見龍(けんりゅう)田(でん)に在(あ)り」とは、德施(とくし)普(あまね)ければなり。「終日(しゅうじつ)乾乾(けんけん)」とは、道(みち)に反復(はんぷく)すればなり。「或(あるい)は躍(おど)りて淵(ふち)に在(あ)り」とは、進(すす)みて咎(とが)无(な)ければなり。「飛龍(ひりゅう)天(てん)に在(あ)り」とは、大人(たいじん)の造(な)すところなればなり。「亢龍(こうりゅう)悔(くい)有(あ)り」とは、窮(きわ)まればの災(わざわい)なればなり。「乾元(けんげん)用九(ようきゅう)」とは、天下(てんか)治(おさ)まればなり。 「潜龍(せんりゅう)用うる勿れ」とは、陽氣(ようき)潜藏(せんぞう)すればなり。「見龍田に在り」とは、天下(てんか)文明(ぶんめい)なればなり。「終日乾乾」とは、時(とき)と偕(とも)に行(ゆ)けばなり。「或は躍りて淵に在り」とは、乾道(けんどう)乃(すなわち)革(あらた)まればなり。「飛龍天に在り」とは、乃ち天德(てんとく)に位(くらい)すればなり。「亢龍悔有り」とは、時と偕に極(きわ)まればなり。「乾元用九」とは、乃ち天(てん)の則(のり)を見(み)るなり。 乾(けん)の元(げん)とは、始(はじ)にして亨(とお)る者(もの)なり。利貞(りてい)とは、性情(せいじょう)なり。乾(けん)は始(はじ)めて能(よ)く美利(びり)を以て天下(てんか)を利(り)す、利(り)する所(ところ)を言(い)わず、大(だい)なるかな。大(だい)なるかな乾(けん)や、剛健(ごうけん)中正(ちゅうせい)、純粹(じゅんすい)精(せい)なり。六爻(りくこう)發揮(はっき)し、旁(あまね)く情(じょう)に通(つう)ず。時(とき)に六龍(りくりゅう)に乘(じょう)じ、以て天(てん)を御(ぎょ)す。雲(くも)行(ゆ)き雨(あめ)施(ほどこ)し、天下(てんか)平(たい)らかなり。 君子(くんし)は德(とく)を成(な)すを以て行(おこない)と為(な)す、日(ひ)に行(おこない)を見る可(べ)きなり。潜(せん)とは之(これ)を言(い)うなり、隱(かく)れて未(いま)だ見(あら)われず、行(おこない)て未だ成(な)らず、是(ここ)を以て君子(くんし)は用(もち)いざるなり。 君子(くんし)は學(まな)びて以て之を聚(あつ)め、問(と)いて以て之を辨(わきま)え、寬(かん)を以て之に居(お)り、仁(じん)を以て之を行(おこな)う。易(えき)に曰(いわ)く、見龍(けんりゅう)田(でん)に在(あ)り、大人(たいじん)を見(み)るに利(よろ)し、とは君德(くんとく)なり。 九三(きゅうさん)は重剛(ちょうごう)にして中(ちゅう)ならず、上(かみ)天に在らず、下(しも)田に在らず。故(ゆえ)に乾乾(けんけん)として其(そ)の時(とき)に因(よ)りて惕(おそ)るれば、厲(あやう)しと雖(いえど)も咎(とが)无(な)し。 九四(きゅうし)は重剛にして中ならず、上天に在らず、下田に在らず、中(ちゅう)人(ひと)に在らず。故に或(あるい)はす。或るはすとは、之を疑(うたが)うなり、故に咎无し。 夫(そ)れ大人(たいじん)とは、天地(てんち)と其(そ)の德(とく)を合(がっ)し、日月(じつげつ)と其の明(めい)を合し、四時(しいじ)と其の序(じょ)を合し、鬼神(きしん)と其の吉凶(きっきょう)を合す。天(てん)に先(さき)んじても天(てん)違(たが)わず、天(てん)に後(おく)れても天(てん)の時(とき)を奉(ほう)ず。天(てん)すら且(か)つ違(たが)わず、而(しか)るを況(いわ)んや人(ひと)に於(おい)てをや、況んや鬼神(きしん)に於てをや。 亢(こう)とは之(これ)を言うなり、進(すす)むを知(し)りて退(しりぞ)くを知(し)らず、存(そん)するを知りて亡(ほろ)ぶを知らず、得(う)るを知りて喪(うしな)うを知らず。其(そ)れ唯(た)だ聖人(せいじん)か。進退存亡(しんたいそんぼう)を知(し)りて其(そ)の正(せい)を失(うしな)わざる者(もの)は、其れ唯だ聖人か。
【乾卦 現代語訳】
「元」とは、善の長(かしら)である。「亨」とは、嘉(よ)きものが集まることである。「利」とは、義(ただしいこと)が調和したものである。「貞」とは、物事の根本となる幹である。君子は、仁を体得して人々の長となるに足り、嘉きものの集まりをもって礼儀に合致するに足り、万物を利することで義と調和するに足り、堅固な正しさをもって物事を担当するに足りる。君子とは、この四つの徳を行う者である。だから、(乾の卦辞は)「乾は元亨利貞」というのである。 「初九に曰く、潜龍用うる勿れ」とは、どういう意味か。孔子は言う、「龍の徳を持ちながらも、まだ隠れている者のことである。世の中の変化に動じず、名声を立てようともしない。世間から隠れても悩みはなく、正しいと認められなくても悩みはない。楽しければそれを行い、憂うべき状況であればそれに従わない。その志は確固としていて、引き抜くことはできない。これが潜龍である」。 「九二に曰く、見龍田に在り、大人を見るに利し」とは、どういう意味か。孔子は言う、「龍の徳を持ち、正しく中庸の道にある者のことである。普段の言葉は誠実であり、普段の行いは慎み深い。邪(よこしま)なことを防いで、その誠実さを保ち、世の中を善くしてもその功績を誇らず、その徳は広大で人々を感化する。易に『見龍田に在り、大人を見るに利し』とあるのは、君子の徳のことである」。 「九三に曰く、君子終日乾乾し、夕に惕若たれば厲うけれども咎无し」とは、何をか謂う。子曰く、君子は徳を進め、業を修める。忠と信は、徳を進めるためのものである。言葉を修め、その誠実さを確立することは、事業を安定させる所以である。至るべき時を知ってそこに至る者は、共に物事の兆しについて語ることができるだろう。終わるべき時を知ってそれに終わる者は、共に義理を保つことができるだろう。このようなわけで、高い地位にいても驕らず、低い地位にいても憂えることがない。だから、勤勉に励み、時に応じて警戒すれば、危うい状況であっても咎めはないのである。 「九四に曰く、或は躍りて淵に在り、咎无し」とは、何をか謂う。子曰く、上の位と下の位を行き来して定まらないのは、邪なことをするためではない。進んだり退いたりして一定しないのは、仲間から離反するためではない。君子は徳を進め業を修め、時機を逃さず行動したいと願っているのだ。だから咎めはない。 「九五に曰く、飛龍天に在り、大人を見るに利し」とは、何をか謂う。子曰く、同じ声は互いに応じ合い、同じ気は互いに求め合う。水は湿ったところへ流れ、火は乾いたところへ就く。雲は龍に従い、風は虎に従う。聖人が現れると万物はその徳を見る。天に本づく者は上に親しみ、地に本づく者は下に親しむ。すなわち、各々はその類に従うのである。 「上九に曰く、亢龍悔有り」とは、何をか謂う。子曰く、地位は貴いが、その身を置くべき位がなく、高く昇りつめて民意もなく、賢人が下の位にいても補佐する者がいない。このようなわけで、動けば後悔があるのだ。 「潜龍用うる勿れ」とは、まだ低い地位にいるからである。「見龍田に在り」とは、その徳の施しが普(あまね)く行き渡るからである。「終日乾乾」とは、正しい道を繰り返し行うからである。「或は躍りて淵に在り」とは、進んでも咎めがないからである。「飛龍天に在り」とは、徳の高い大人が事を成すからである。「亢龍悔有り」とは、窮まった時の災いだからである。「乾元用九」とは、天下が治まるからである。 「潜龍用うる勿れ」とは、陽の気がまだ潜み隠れているからである。「見龍田に在り」とは、天下が文明の光で照らされるからである。「終日乾乾」とは、時と共に進んでいくからである。「或は躍りて淵に在り」とは、乾の道がここに革(あらた)まるからである。「飛龍天に在り」とは、すなわち天の徳の位にあるからである。「亢龍悔有り」とは、時と共に極まってしまうからである。「乾元用九」とは、すなわち天の法則を見るからである。 乾の元とは、物事を始めさせ、そして成就させるものである。利と貞とは、人間の本性そのものである。乾は、初めによく美しい利益をもって天下を利するが、その利する所を自ら語ることはない。なんと偉大なことであろうか。偉大なるかな乾は、剛健で中正、純粋で精妙である。六つの爻がその働きを発揮し、あまねく万物の情に通じている。時に応じて六頭の龍に乗り、天を治める。雲がゆき雨が施され、天下は平らかになる。 君子は、徳を完成させることを自らの行いとし、その行いは日々に現れるものである。「潜む」という言葉は、隠れてまだ現れず、行ってもまだ完成しない状態を言う。だから君子は、この段階では行動しないのである。 君子は、学ぶことによって知識を聚(あつ)め、問うことによって物事を弁別し、寛容さをもってその境遇に安んじ、仁の心をもってそれを行う。易に「見龍田に在り、大人を見るに利し」とあるのは、君子の徳のことである。 九三は、陽が重なり中庸を得ていない。上にいても天の位ではなく、下にいても田の位ではない。だから、勤勉に励み、その時に応じて警戒すれば、危うい状況であっても咎めはないのである。 九四は、陽が重なり中庸を得ていない。上は天の位ではなく、下は田の位ではなく、中は人の位ではない。だから「或(あるい)は」と言うのである。「或は」と言うのは、疑い迷うことである。だから咎めはない。 そもそも大人とは、天地とその徳を合わせ、日月とその明るさを合わせ、四季とその秩序を合わせ、鬼神とその吉凶を合わせるような人物である。天の運行より先に動いても天の理に違うことなく、天の運行より後に動いても天の時に従う。天でさえ違うことがないのだから、ましてや人間においてをや、鬼神においてをや(違うことがあろうか)。 「亢(いきすぎ)」という言葉の意味は、進むことを知っていて退くことを知らず、存在することを知っていて滅びることを知らず、得ることを知っていて失うことを知らず、ということである。そのようなことができるのは、ただ聖人だけであろうか。進退存亡を知り、その上で正しさを失わない者、それこそがただ聖人なのである。
坤卦原文
坤、至柔而動也剛、至靜而德方。後得主而有常、含萬物而化光。坤道其順乎。承天而時行。 積善之家、必有餘慶。積不善之家、必有餘殃。臣弒其君、子弒其父、非一朝一夕之故。其所由來者漸矣。由辯之不早辯也。易曰、履霜堅冰至。蓋言順也。 直其正也、方其義也。君子敬以直内、義以方外。敬義立而德不孤。直方大、不習无不利。則不疑其所行也。 陰雖有美、含之、以從王事、弗敢成也。地道也、妻道也、臣道也。地道无成、而代有終也。 天地變化、草木蕃。天地閉、賢人隱。易曰、括囊、无咎无譽。蓋言謹也。 君子黄中通理、正位居體。美在其中、而暢於四支、發於事業。美之至也。 陰疑於陽、必戰。為其嫌於无陽也、故稱龍焉。猶未離其類也、故稱血焉。夫玄黄者、天地之雜也。天玄而地黄。
坤卦書き下し文
坤(こん)は至(いた)って柔(じゅう)にして動(うご)くや剛(ごう)、至って静(しず)かにして德(とく)は方(ほう)なり。後(おく)れて主(しゅ)を得(う)て常(つね)有(あ)り、万物(ばんぶつ)を含(ふく)み而(しか)して化(か)光(おお)いなり。坤道(こんどう)は其(そ)れ順(じゅん)なるか。天(てん)を承(う)けて時(とき)に行(おこな)う。 積善(せきぜん)の家(いえ)には、必(かなら)ず餘慶(よけい)有(あ)り。積不善(せきふぜん)の家には、必ず餘殃(よおう)有り。臣(しん)其(そ)の君(きみ)を弑(しい)し、子(こ)其の父(ちち)を弑するは、一朝一夕(いっちょういっせき)の故(ゆえ)に非(あら)ず。其の由(よ)りて来(きた)る所(ところ)の者(もの)は漸(ぜん)なり。之を辯(べん)ず可(べ)くして早(はや)く辯(べん)ぜざるに由(よ)る。易(えき)に曰(いわ)く、霜(しも)を履(ふ)めば堅冰(けんぴょう)至(いた)る、とは蓋(けだ)し順(じゅん)なるを言(い)うなり。 直(ちょく)は其(そ)の正(せい)なり、方(ほう)は其の義(ぎ)なり。君子(くんし)は敬(けい)以て内(うち)を直(なお)くし、義(ぎ)以て外(そと)を方(ほう)にす。敬義(けいぎ)立(た)ちて德(とく)孤(こ)ならず。「直方大(ちょくほうだい)、習(なら)わずして利(よろ)しからざるなし」とは、則ち其の行(おこな)う所(ところ)を疑(うたが)わざるなり。 陰(いん)は美(び)有(あ)りと雖(いえど)も、之を含(ふく)み、以て王事(おうじ)に従(したが)い、敢(あ)えて成(な)さざるなり。地(ち)の道なり、妻(さい)の道なり、臣(しん)の道なり。地道(ちどう)は成すこと无(な)けれども、代(か)わりて終(おわり)有(あ)るなり。 天地(てんち)変化(へんか)して、草木(そうもく)蕃(しげ)し。天地(てんち)閉(と)ずれば、賢人(けんじん)隱(かく)る。易(えき)に曰(いわ)く、嚢(ふくろ)を括(くく)る、咎(とが)无(な)く譽(ほまれ)无(な)し、とは蓋(けだ)し謹(つつし)むを言うなり。 君子(くんし)は黄中(こうちゅう)理(り)に通(つう)じ、位(くらい)に正(ただ)しく體(たい)に居(お)る。美(び)は其(そ)の中(うち)に在(あ)りて、四支(しし)に暢(の)び、事業(じぎょう)に発(はっ)す。美(び)の至(いた)りなり。 陰(いん)陽(よう)を疑(うたが)えば、必ず戦う。其の无陽(むよう)なるを嫌(きら)うが為(ため)なり、故に龍(りゅう)と稱(しょう)す。猶(な)お未(いま)だ其の類(るい)を離(はな)れざるなり、故に血(けつ)と稱す。夫(そ)れ玄黄(げんこう)とは、天地(てんち)の雜(まじ)わりなり。天(てん)は玄(げん)にして地(ち)は黄(こう)なり。
【坤卦 現代語訳】
坤は、この上なく柔順でありながら、その動きは剛健である。この上なく静かでありながら、その徳は隅々まで行き渡る。後に従うことで主導権を得て、常にその徳を保ち、万物を包容して、その感化は光り輝く。坤の道は、なんと従順なことであろうか。天の働きを受け継いで、時に応じて行動するのである。 善行を積み重ねた家には、必ず子孫にまで及ぶ慶びがある。不善を積み重ねた家には、必ず子孫にまで及ぶ災いがある。臣下がその君主を殺し、子がその父を殺すのは、一朝一夕の出来事ではない。その原因が生まれてくるまでには、徐々に進行してきたのである。それは、弁別すべき時に、早く弁別しなかったことによる。易に、「霜を履めば、やがて堅い氷がやって来る」とあるのは、物事が順を追って進行することを言っているのである。 「直」とは、その内面が真っ直ぐなことである。「方」とは、その外面が義にかなっていることである。君子は、敬いの心をもって内面を真っ直ぐにし、義の心をもって外面を正しくする。敬と義が確立されれば、その徳は孤立することはない。「真っ直ぐで、正しく、大らかであれば、特に学ばなくても不利益なことはない」とは、すなわち、自分の行うべきことについて疑いがないということである。 陰(坤)は、それ自体に素晴らしい美徳を持ってはいるが、それを内に含んで、君主の事業に従い、敢えて自らが完成させようとはしない。これが、地の道であり、妻の道であり、臣下の道である。地の道は、自ら何かを完成させることはないが、天に代わって物事を最後まで成し遂げるのである。 天地が変化すれば、草木は盛んに茂る。天地が閉ざされれば、賢人は世を隠れる。易に、「嚢の口を括るようにすれば、咎めもなく、誉れもない」とあるのは、すなわち慎むことを言っているのである。 君子は、黄色(中庸の徳)を内に持ち、道理に通じ、正しい位にいて、その本分に安んじている。美徳は内面にありながら、その影響は四肢にまで伸びやかに行き渡り、事業となって現れる。これこそ、美の極致である。 陰が陽に対して分不相応な疑いを抱けば、必ず戦いが起こる。それは、自分が陽に従うべき存在であることを嫌うからである。だから(戦う陰を)「龍」と称するのである。しかしまだその同類から離れきってはいない。だから(その血の色を)「血」と称するので-ある。そもそも玄黄(黒と黄色)とは、天と地の混じり合った色である。天は玄(黒)であり、地は黄である。
文言伝が示す「君子の道」
「文言伝」は、乾坤二卦を通して、わたしたちが目指すべき理想の人間像、すなわち「君子」の生き方を、深く、そして多角的に示してくれます。その言葉の一つひとつが、わたしたちの「日々新たに、益々よくなる」ための、かけがえのない道標となるでしょう。
1. 「乾の四徳」を人生の羅針盤とする
- 文言伝の言葉: 「元者、善之長也。亨者、嘉之會也。利者、義之和也。貞者、事之幹也。」(元は、善の長なり…)
- わたしたちへのヒント: 乾の持つ「元・亨・利・貞」の四つの徳は、わたしたちが「益々善成」を実践していく上での、最高の行動指針です。
- 元(始まり): 常に善なる思いをもって、物事を始めよう。
- 亨(通る): 喜びをもって人と交わり、その輪を広げていこう。
- 利(調和): 私利私欲ではなく、全体の利益と調和を考えて行動しよう。
- 貞(根本): 正しい道を踏み外しそうになっても、常に物事の本質、根本に立ち返ろう。 この四つの徳を心に刻み、日々の選択の基準とすることで、わたしたちの人生は、自ずと健やかで、実り豊かなものへと導かれていくでしょう。
2. 龍の成長物語に、自分の「時」を見出す
- 文言伝の言葉: 「潛龍勿用」「見龍在田」「飛龍在天」「亢龍有悔」…
- わたしたちへのヒント: 文言伝が描く、龍がその成長段階に応じて姿を変えていく物語は、わたしたち自身の人生のステージを客観視するための、素晴らしいメタファーです。
- 今は力を蓄えるべき「潜龍」の時か? であれば、焦らず学び、内面を充実させる。
- 世に出て活動を始めるべき「見龍」の時か? であれば、良き師や仲間を求め、誠実に行動する。
- リーダーとして能力を最大限に発揮すべき「飛龍」の時か? であれば、天の時を得たことに感謝し、その力を天下のために用いる。
- あるいは、頂点を極め、退くことを考えるべき「亢龍」の時か? であれば、驕ることなく、次の世代に道を譲る準備をする。 自分の「時」を正しく認識し、その時にふさわしい行動を取ること。それこそが、易経が教える、最も賢明な生き方なのです。
3. 「坤の徳」に、真の強さとしなやかさを学ぶ
- 文言伝の言葉: 「坤、至柔而動也剛」「後得主而有常」「承天而時行」
- わたしたちへのヒント: 力強く前進する「乾」の徳だけでなく、この「坤」の徳を学ぶことは、わたしたちの「益々善成」を、より深く、より安定したものにしてくれます。
- 柔よく剛を制す: 坤は、この上なく柔順でありながら、その動きは力強い。それは、全てを受け入れる包容力こそが、最終的に物事を動かす真の強さであることを教えています。
- 後れて主を得る: 常に先頭に立とうとするのではなく、一歩引いて状況を見極め、他者を立てることで、かえって信頼を得て、物事の主導権を握ることができる。
- 天を承けて時に行く: 自分の我を通すのではなく、天の時、すなわち大きな流れや道理を受け入れ、それに従って行動する。その謙虚さが、わたしたちを正しい道へと導きます。
4. 善を積み、悪を避ける – 日々の小さな選択が、未来を創る
- 文言伝の言葉: 「積善之家、必有餘慶。積不善之家、必有餘殃。」(積善の家には、必ず余慶有り…)
- わたしたちへのヒント: 繫辞下伝にも通じるこの教えは、文言伝において、よりはっきりと示されます。わたしたちの日々の小さな善行、あるいは不善の行いは、決してその場限りで消えることはありません。それは確実に積み重なり、やがては自分自身、そして子孫にまで及ぶ、大きな結果(慶び、あるいは災い)となって現れる。この因果の法則を深く心に刻む時、わたしたちは、日々の小さな選択を、より一層、真剣に、そして誠実に行うようになるでしょう。
「文言伝」は、わたしたちに、ただ生きるのではなく、**「いかに善く生きるか」**という、人生の最も根源的な問いを投げかけます。天の如く健やかに、地の如く穏やかに。その両方の徳を、わたしたちの内なる「君子」として統合し、体現していく。それこそが、「文言伝」が示す、究極の姿なのです。