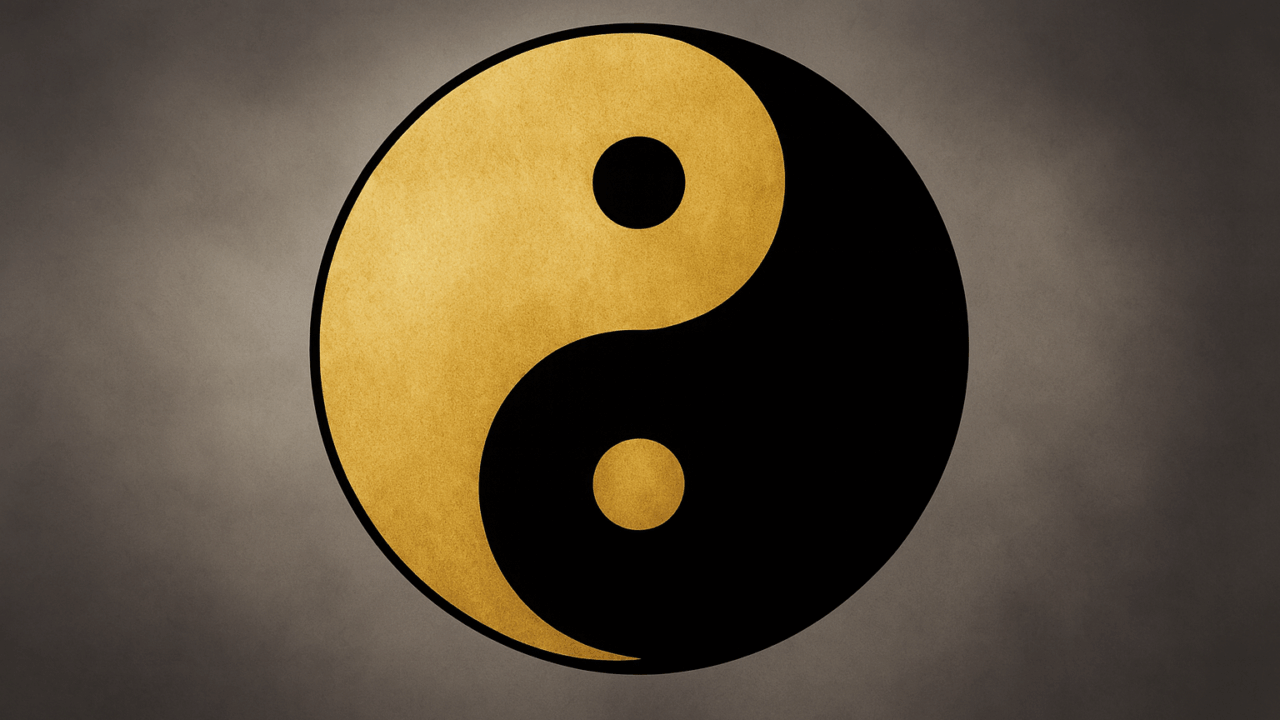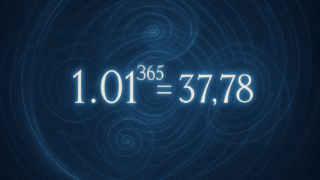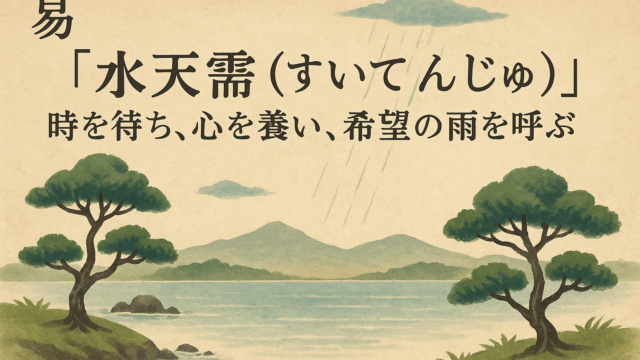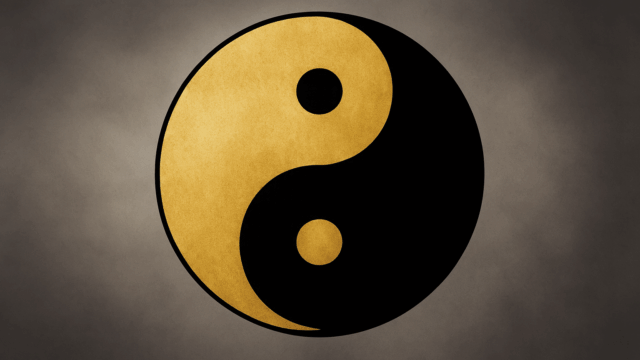【易経】「説卦伝」全文・現代語訳と解説 – 八卦の象徴を知り、『易は逆数なり』の智慧で未来を拓く
八卦の「個性」を深く知る旅へ – 「説卦伝」
ブログを訪れてくださり、ありがとうございます。 わたしたちはこれまで、「八卦」という、宇宙の万物を構成する八つの基本エネルギーについて、一つひとつ探求してきました。天、地、雷、風、水、火、山、沢…。しかし、なぜ天は「父」であり「馬」なのか、沢はなぜ「少女」であり「口」なのでしょうか。その背後には、どのような深い意味が隠されているのでしょうか。
その謎を解き明かし、わたしたちが易経という広大な叡智の海をさらに深く航海するための、詳細な「海図」とも言える書物があります。それが、易経を構成する補助的な解説書「十翼(じゅうよく)」の中でも、特に象徴性を豊かに説き明かす**「説卦伝(せっかでん)」**です。
この記事では、「説卦伝」の言葉を一つひとつ丁寧に紐解きながら、そこに秘められた宇宙と人間との響き合いを感じ、そして最後に、この伝が示す**「易は逆数なり」**という、わたしたちの時間と未来に対する捉え方を根底から変えるかもしれない、深遠な智慧について、皆さんと共に深く探求していきたいと思います。
「説卦伝」とは何か? – わたしたちの世界と心を映す、象徴のネットワーク
「説卦伝」は、その名の通り、「卦(八卦)について説き明かす」伝です。八卦が持つ、自然、性質、家族、身体、動物といった、多岐にわたる豊かな象徴のネットワークを、体系的に、そして詩的に解説してくれています。
もし、易経全体が一つの深遠な言語であるとするならば、「説卦伝」は、わたしたちがその言語を自在に使いこなし、六十四卦の物語をより深く、より色彩豊かに読み解くための、かけがえのない**「象徴の辞書」**と言えるでしょう。 この「説卦伝」を学ぶことで、わたしたちは、単に卦の意味を暗記するのではなく、なぜその卦がそのような意味を持つのか、その根底にある古代の人々の世界観や自然観を、直感的に感じ取ることができるようになります。それは、わたしたちの日常のあらゆる瞬間に「易の叡智」を見出すための、豊かで美しい視点を与えてくれるのです。
「説卦伝」全文・現代語訳の智慧
それでは、「説卦伝」の言葉を、伝統的な章立てに沿って、その「原文」「書き下し文」「現代語訳」、そしてヒントとしての「解説」と共に、じっくりと味わっていきましょう。
第一章:聖人の易の作り方
- 原文: 昔者聖人之作易也、幽贊於神明而生蓍、參天兩地而倚數、觀變於陰陽而立卦、發揮於剛柔而生爻、和順於道德而理於義、窮理盡性以至於命。
- 書き下し文: 昔者(むかし)聖人(せいじん)の易(えき)を作(つく)るや、神明(しんめい)を幽贊(ゆうさん)して蓍(めどぎ)を生(しょう)じ、天(てん)に參(さん)し地(ち)に両(りょう)して數(すう)を倚(よ)せ、陰陽(いんよう)の変(へん)を観(み)て卦(か)を立(た)て、剛柔(ごうじゅう)を発揮(はっき)して爻(こう)を生(しょう)じ、道徳(どうとく)に和順(わじゅん)して義(ぎ)に理(おさ)め、理(り)を窮(きわ)め性(せい)を尽(つ)くして以(もっ)て命(めい)に至(いた)る。
- 現代語訳: 昔、聖人が易をお作りになった時、神明(人知を超えた働き)の助けを得て蓍(めどぎ:占いに用いる筮竹)を生み出し、天の三つの徳と地の二つの徳に則って数を立て、陰と陽の変化を観察して卦を立て、剛と柔の働きを発展させて爻を生じ、道徳の理に従って物事の義(ただしさ)を定め、物事の道理を極め、人間の本性を尽くして、天命を悟る境地に至ったのである。
- 【ヒント】: わたしたちの「益々善成」の旅もまた、この聖人の易の作り方に倣うことができます。まず、自分の内なる声や直感(神明)に耳を澄まし、天の理想(天に參し)と地の現実(地に両して)をよく見極め、陰陽のバランス(変を観て)を考え、時には力強く(剛)、時にはしなやかに(柔)、具体的な行動(爻を生じ)を起こす。その全てが、道徳(正しい道)に和順し、道理を極め、自分自身の本性(性)を最大限に輝かせることで、天から与えられた使命(命)を全うする道へと繋がっていくのです。
第二章:天地自然と八卦
- 原文: 昔者聖人之作易也、將以順性命之理。是以立天之道、曰陰與陽。立地之道、曰柔與剛。立人之道、曰仁與義。兼三才而兩之、故易六畫而成卦。分陰分陽、迭用柔剛、故易六位而成章。
- 書き下し文: 昔者聖人の易を作るや、將(まさ)に以て性命(せいめい)の理(り)に順(したが)わんとす。是(ここ)を以て天の道を立てて、陰(いん)と陽(よう)と曰(い)う。地の道を立てて、柔(じゅう)と剛(ごう)と曰う。人の道を立てて、仁(じん)と義(ぎ)と曰う。三才(さんさい)を兼(か)ねて之(これ)を両(ふたつ)にし、故(ゆえ)に易は六畫(りっかく)にして卦(か)を成(な)す。陰に分かり陽に分かり、迭(たが)いに柔剛(じゅうごう)を用い、故に易は六位(りくい)にして章(しょう)を成す。
- 現代語訳: 昔、聖人が易をお作りになったのは、万物の本性と天命の道理に従うためであった。そこで、天の道として「陰」と「陽」を立て、地の道として「柔」と「剛」を立て、人の道として「仁」と「義」を立てた。この天・地・人という三つの才(三才)を兼ね、それぞれに陰陽二つの側面があるため、易は六本の爻(六畫)によって一つの卦が完成する。陰と陽に分かれ、柔と剛が交互に作用することで、易は六つの爻位によって一つのまとまり(章)を成すのである。
- 【ヒント】: わたしたちもまた、この「天・地・人」の三つの道の調和の中にあります。天の道(理想、精神性)を高く掲げ、地の道(現実、行動)をしっかりと踏みしめ、そして人の道(人間関係、仁義)を大切にする。この三つのバランスを意識することが、わたしたちの人生を、より豊かで、安定的で、そして意味深いものにしてくれるでしょう。
第三章:易の根本原理
- 原文: 天地定位、山澤通氣、雷風相薄、水火不相射、八卦相錯。數往者順、知來者逆、是故易逆數也。
- 書き下し文: 天地(てんち)位(くらい)を定(さだ)め、山澤(さんたく)氣(き)を通(つう)じ、雷風(らいふう)相(あい)薄(せま)り、水火(すいか)相(あい)射(いと)わず、八卦(はっけ)相(あい)錯(まじ)わる。往(おう)を數(かぞ)うるは順(じゅん)、来(らい)を知(し)るは逆(ぎゃく)、是(こ)の故(ゆえ)に易(えき)は逆數(ぎゃくすう)なり。
- 現代語訳: 天と地はその位置を定め(上下)、山と沢は互いに気を通じ合わせ、雷と風は互いに作用し合い、水と火は互いにその働きを否定し合わず(それぞれが役割を果たし)、こうして八卦は互いに交錯し、万物を生み出す。過去の出来事を数え上げるのは順方向の思考であり、未来の出来事を知ろうとするのは逆方向の思考である。このような理由から、易は未来から今を推し量る「逆数」なのである。
- 【ヒント】: この章には、後ほど詳しく触れる、易の核心とも言える「易は逆数なり」という言葉が含まれています。ここではまず、自然界のあらゆるものが、対立しながらも互いに関わり合い、影響を与え合うことで、一つの大きな調和を生み出していることを感じることができます。わたしたちの人生もまた、様々な出来事や人々との関わり合い(相錯わる)の中で、豊かに創造されていくのです。
第四章:八卦と動物
- 原文: 雷以動之、風以散之、雨以潤之、日以烜之、艮以止之、兌以說之、乾以君之、坤以藏之。
- 書き下し文: 雷(らい)は以(もっ)て之(これ)を動(うご)かし、風(ふう)は以て之を散(さん)じ、雨(あめ)は以て之を潤(うるお)し、日(ひ)は以て之を烜(けん)し、艮(ごん)は以て之を止(とど)め、兌(だ)は以て之を説(よろこ)ばし、乾(けん)は以て之に君(きみ)たり、坤(こん)は以て之を藏(ぞう)す。
- 現代語訳: 雷(震)は物事を動かし、風(巽)は物事を隅々まで行き渡らせ、雨(坎)は物事を潤し、日(離)は物事を照らし乾かす。艮(山)は物事を止め、兌(沢)は物事を喜ばせ、乾(天)は物事の君主となり、坤(地)は物事を内にかくまい蓄える。
- 【ヒント】: この八つの動詞は、わたしたちが活用できる、基本的なアクションプランです。時には決断し「動かし」、時にはメッセージを「散じ」、時には心を「潤し」、時には情熱で「烜し」、時にはじっと「止め」、時には素直に「説ばし」、時には全体を「君し」、そして時には力を「藏す」。状況に応じて、これらの力を使い分ける智慧を養いましょう。
第五章:八卦と身体
- 原文: 帝出乎震、齊乎巽、相見乎離、致役乎坤、說言乎兌、戰乎乾、勞乎坎、成言乎艮。
- 書き下し文: 帝(てい)震(しん)に出(い)で、巽(そん)に齊(ととの)い、離(り)に相見(あいみ)え、坤(こん)に役(えき)を致(いた)し、兌(だ)に言(げん)を説(よろこ)び、乾(けん)に戦い、坎(かん)に労(ろう)し、艮(ごん)に言(げん)を成(な)す。
- 現代語訳: 天帝(万物の主宰者)は、東方の震(春)で活動を開始し、東南の巽で万物を整え、南の離(夏)でその姿を明らかにし、西南の坤(晩夏)で働きを終え養い、西の兌(秋)で収穫を喜び語り、西北の乾で陰の気と戦い、北の坎(冬)で労をねぎらい休み、そして東北の艮(晩冬)で一年の働きを終え、また新たな始まりに備える。
- 【ヒント】: これは、一年の季節のサイクルを八卦で表したものです。わたしたちの人生やプロジェクトにも、このようなサイクルがあります。活動を開始する時(震)、物事を整える時(巽)、成果が明らかになる時(離)、努力が実を結ぶ時(坤)、収穫を喜ぶ時(兌)、次の段階への備えをする時(乾)、休息しエネルギーを蓄える時(坎)、そして一つのサイクルを終え、次への準備をする時(艮)。今、自分がどの季節にいるのかを意識することで、より適切な行動を選択できます。
第六章:八卦の力強い働き
- 原文: 神也者、妙萬物而為言者也。動萬物者、莫疾乎雷。橈萬物者、莫疾乎風。燥萬物者、莫熯乎火。 說萬物者、莫說乎澤。潤萬物者、莫潤乎水。終萬物始萬物者、莫盛乎艮。
故水火相逮、雷風不相悖、山澤通氣、然後能變化、既成萬物也。 - 書き下し文: 神(しん)なる者(もの)は、万物(ばんぶつ)を妙(みょう)にして言(げん)を為(な)す者(もの)なり。万物(ばんぶつ)を動(うご)かす者(もの)は、雷(らい)より疾(と)きは莫(な)し。万物(ばんぶつ)を橈(たわ)むる者(もの)は、風(ふう)より疾(と)きは莫(な)し。万物(ばんぶつ)を燥(かわ)かす者(もの)は、火(ひ)より熯(かん)なるは莫(な)し。万物(ばんぶつ)を説(よろこ)ばす者(もの)は、澤(さわ)より説(よろこ)ばしきは莫(な)し。万物を喜ばせるものとしては、沢(兌)ほど喜ばしいものはない。万物(ばんぶつ)を潤(うるお)す者(もの)は、水(みず)より潤(うるお)すは莫(な)し。万物(ばんぶつ)を終(お)え万物(ばんぶつ)を始(はじ)むる者(もの)は、艮(ごん)より盛(さか)んなるは莫(な)し。 故(ゆえ)に水火(すいか)相(あい)逮(およ)び、雷風(らいふう)相(あい)悖(もと)らず、山澤(さんたく)氣(き)を通(つう)じ、然(しか)る後(のち)能(よ)く変化(へんか)し、既(すで)にして万物(ばんぶつ)を成(な)すなり。
- 現代語訳: 神(人知を超えた働き)とは、万物を不思議なほど巧みに動かし、その道理を言葉として示すものである。万物を奮い立たせ、動かすものとしては、雷(震)ほど速く力強いものはない。万物をしなやかに靡(なび)かせ、動かすものとしては、風(巽)ほど速やかに浸透するものはない。万物を乾燥させるものとしては、火(離)ほど熱く乾かすものはない。 万物を潤し、生命を与えるものとしては、水(坎)ほど潤すものはない。万物を終わらせ、そしてまた新たに万物を始めさせることにおいて、艮(山)ほど盛んな働きをするものはない。このようにして、水と火は互いにその働きを及ぼし合い、雷と風は互いに背き合うことなく、山と沢はその気を通じ合わせ、そうして初めて万物は変化し、成長し、完成していくのである。
【ヒント】: わたしたちの世界は、目に見えるものだけでなく、人知を超えた不思議な神妙な働きによって動かされています。それは、わたしたちの直感や、偶然の出会い、あるいは心の奥底から湧き上がる衝動といった形で現れるかもしれません。
それぞれには役割があるからこそ、相反するエネルギーが対立するのではなく、互いの性質を尊重し、影響を与え合い、そして調和することで、初めて真の「変化」と「創造」が生まれるのです。わたしたちもまた、自分の中の様々な側面(剛と柔、行動と静止、喜びと内省など)を調和させ、他者との響き合いの中でこそ、豊かに成就していくのでしょう。
第七章:八卦の徳(とく)を定義する
- 原文:乾健也。坤順也。震動也。巽入也。坎陷也。離麗也。艮止也。兌説也。
- 書き下し文:乾は健なり。坤は順なり。震は動なり。巽は入なり。坎は陷なり。離は麗なり。艮は止なり。兌は説なり。
- 現代語訳:乾は「健やかに進む力」を表し、
坤は「従順で受け入れる性質」を持つ。
震は「動き」、巽は「入り込む力」、
坎は「陥る」、離は「明るく照らす」、
艮は「止まる」、兌は「喜びをもたらす」。 - ④ ポイント解説
- 八卦の**核心的性質(徳)**を一語で定義した章。
- これは後の章に出てくる「象(自然現象)」や「人倫(社会的役割)」の基礎になる。
- ••特に「乾=健」「坤=順」は、易経において最も重要な徳の対比。
第八章:八卦の動物的象徴
- 原文:乾為馬,坤為牛,震為龍,巽為雞,坎為豕,離為雉,艮為狗,兌為羊。
- 書き下し文:乾は馬と為(な)し、坤は牛と為す。震は龍と為し、巽は鶏と為す。坎は豕(いのこ)と為し、離は雉(きじ)と為す。艮は狗(いぬ)と為し、兌は羊と為す。
- 現代語訳:乾は馬を象徴し、坤は牛を象徴する。
震は龍、巽は鶏、坎は豚、離は雉、艮は犬、兌は羊を象徴している。 - ④ ポイント解説:
この章は八卦を動物に比喩することで、性質をイメージ化しています。
たとえば:
乾=馬:力強くまっすぐ進む、雄々しい。
坤=牛:おとなしく、従順で、耐え忍ぶ。
震=龍:雷のごとく動き出す、突然変化の象徴。
巽=鶏:朝を告げる、情報の伝達、軽やかさ。
坎=豕(いのこ):危険や深みを表す陰の象徴。
離=雉:照らす、美しさ、機敏な動き。
艮=狗(いぬ):見張り、守る者、止まる力。
兌=羊:柔和、群れ、楽しさと調和。
••単なる動物占いではなく、自然界における八卦の動きと人間の性格や資質を結びつけた深い象徴表現です。
第九章:八卦と身体・方位との対応
- 原文:乾為首,坤為腹,震為足,巽為股,坎為耳,離為目,艮為手,兌為口。
- 書き下し文:乾は首と為(な)し、坤は腹と為し、震は足と為し、巽は股(もも)と為す。
坎は耳と為し、離は目と為し、艮は手と為し、兌は口と為す。 - 現代語訳:乾は頭(首)を表し、坤は腹を表す。
震は足、巽は太もも、坎は耳、離は目、艮は手、兌は口を象徴している。 - ポイント解説:この章は、八卦を人体の各部位に割り当てる比喩であり、陰陽五行思想や古代中国医学、風水、武術などでも多く活用される対応論の基盤です。
- 各卦が「身体のどの機能・動作」に対応しているかを通して、人間と宇宙(大宇宙と小宇宙)の一致という東洋思想の核心に触れます。
| 卦 | 象徴する身体部位 | 解説(イメージ) |
| 乾 ☰ | 首(頭) | 主体性・理性・創造の源、支配者の器官 |
| 坤 ☷ | 腹 | 受容・包容・命を育む中心部 |
| 震 ☳ | 足 | 動き出し、前進の起点 |
| 巽 ☴ | 股(もも) | 柔軟性・方向転換・支えとなる部位 |
| 坎 ☵ | 耳 | 情報受容、感覚の入り口(危機察知) |
| 離 ☲ | 目 | 視覚・洞察・明晰さの象徴 |
| 艮 ☶ | 手 | 行動・実践・触れる力 |
| 兌 ☱ | 口 | 発信・表現・楽しみの出入り口 |
【第十章】八卦の象徴
原文: 乾、天也、故稱乎父。坤、地也、故稱乎母。
書き下し文: 乾(けん)は天(てん)なり、故(ゆえ)に父(ちち)と稱(しょう)す。坤(こん)は地(ち)なり、故に母(はは)と稱す。
現代語訳: 乾は天である。ゆえに父と称される。坤は地である。ゆえに母と称される。
原文: 震一索而得男、故謂之長男。巽一索而得女、故謂之長女。坎再索而得男、故謂之中男。離再索而得女、故謂之中女。艮三索而得男、故謂之少男。兌三索而得女、故謂之少女。
書き下し文: 震(しん)は一索(いっさく)して男(なん)を得(う)、故(ゆえ)に之(これ)を長男(ちょうなん)と謂(い)う。巽(そん)は一索(いっさく)して女(じょ)を得(う)、故に之を長女(ちょうじょ)と謂う。坎(かん)は再索(さいさく)して男を得、故に之を中男(ちゅうなん)と謂う。離(り)は再索して女を得、故に之を中女(ちゅうじょ)と謂う。艮(ごん)は三索(さんさく)して男を得、故に之を少男(しょうなん)と謂う。兌(だ)は三索して女を得、故に之を少女(しょうじょ)と謂う。
現代語訳: 震は(父である乾の初爻を母である坤に求めて)初めて男の子を得たものであるから、これを長男という。巽は初めて女の子を得たものであるから、これを長女という。坎は二度目に男の子を得たものであるから、これを中男という。離は二度目に女の子を得たものであるから、これを中女という。艮は三度目に男の子を得たものであるから、これを少男という。兌は三度目に女の子を得たものであるから、これを少女という。
「易は逆数なり」– 未来から「今」へと流れる時間
さて、この記事の核心として、説卦伝が示す最も深遠な智慧の一つ、「易は逆数なり」という言葉について、改めて深く探求したいと思います。
わたしたちは通常、時間を「過去」→「現在」→「未来」へと流れる、一本の不可逆な矢のように感じています。過去は変えられず、未来はまだ何も書かれていない、未知の領域だと。 しかし、「易は逆数なり」という言葉は、全く異なる時間観をわたしたちに提示します。それは、未来はすでに、ある種の可能性のエネルギーとして存在しており、そこから「現在」というわたしたちのいる一点に向かって、絶えず流れ込んできている、という考え方です。
未来は、わたしたちがこれから手探りで作っていくものではなく、むしろ、遠くから寄せてくる波のようなものです。そして、易経の卦は、その**「これからやって来る波の性質(未来の気配)」**を、わたしたちに教えてくれる、高感度のセンサーなのです。
例えば、「地雷復」の卦が出れば、「今はまだ寒くとも、足元から再生と春のエネルギーの波がやって来ていますよ」と教えてくれる。「水火既済」の卦が出れば、「今は完成の頂点ですが、満ちれば欠けるという、次なる乱れの波の気配に備えなさい」と警告してくれる。
つまり、「易は逆数なり」とは、未来から流れ来るその気配を読み取り、そこから逆算して、「では、その未来を迎えるために、今、何をすべきか」「どのような心のあり方でいるべきか」を賢明に判断するための、究極の未来志向の智慧なのです。
これは、ただ運命を言い当てる「占い」とは根本的に異なります。それは、**わたしたちの前に広がる複数の未来の可能性の波の中から、わたしたちが「日々新たに、益々よくなる」という羅針盤に従って、最も善き波を選び取り、それに主体的に乗りこなしていくための、積極的な「航海術」**と言えるでしょう。 わたしたちの心で「今」を誠実に生きる時、わたしたちは、未来から流れ来る、最も輝かしく、最も豊かな波と、自ずと共鳴し、合流していくことができるのです。
【むすび】「説卦伝」の智慧を手に、未来の風を読んで、船を進めよう
「説卦伝」は、単なる八卦の象徴の解説書ではありません。それは、この世界の森羅万象とわたしたち自身が、いかに深く、そして美しく響き合っているかを教えてくれる、壮大な調和の書です。
そして、その核心にある「易は逆数なり」という智慧は、わたしたちを、過去に縛られ、未来を恐れる生き方から解放し、未来から吹いてくる希望の風を読み、それに乗って「今」を創造していく、より自由で、力強い生き方へと導いてくれます。
このブログの読者の皆様、そしてわたし自身。この古代の叡智を手に、未来からわたしたちへと絶えず流れ来る、より善き可能性の波を感じ取り、それに合わせてわたしたち自身の帆を張り、希望に満ちた素晴らしい人生の船旅を、今日からまた、続けていきましょう。
おまけ 各卦の象徴
乾のさらなる象徴
原文: 乾為天、為圜、為君、為父、為玉、為金、為寒、為冰、為大赤、為良馬、為老馬、為瘠馬、為駁馬、為木果。
書き下し文: 乾(けん)は天(てん)と為(な)し、圜(えん)と為し、君(きみ)と為し、父(ちち)と為し、玉(ぎょく)と為し、金(きん)と為し、寒(かん)と為し、冰(ひょう)と為し、大赤(たいせき)と為し、良馬(りょうば)と為し、老馬(ろうば)と為し、瘠馬(せきば)と為し、駁馬(ばくば)と為し、木果(もっか)と為す。
現代語訳: 乾は、天であり、円いものであり、君主であり、父であり、玉であり、金であり、寒さであり、氷であり、深い赤色であり、良い馬であり、老いた馬であり、痩せた馬であり、まだらの馬であり、木の実である。
坤の象徴
原文: 坤為地、為母、為布、為釜、為吝嗇、為均、為子母牛、為大輿、為文、為衆、為柄。其於地也、為黑。
書き下し文: 坤(こん)は地(ち)と為(な)し、母(はは)と為し、布(ぬの)と為し、釜(ふ)と為し、吝嗇(りんしょく)と為し、均(きん)と為し、子母牛(しぼぎゅう)と為し、大輿(たいよ)と為し、文(ぶん)と為し、衆(しゅう)と為し、柄(え)と為す。其(そ)の地(ち)に於(お)けるや、黑(くろ)と為(な)す。
現代語訳: 坤は、地であり、母であり、布であり、釜であり、物惜しみすることであり、均しいことであり、子を連れた母牛であり、大きな車であり、文様であり、多くの人々であり、器物の取っ手である。その地の色においては、黒である。
震の象徴
原文: 震為雷、為龍、為玄黄、為旉、為大塗、為長子、為決躁、為蒼筤竹、為萑葦。其於馬也、為善鳴、為馵足、為作足、為的顙。其於稼也、為反生。其究為健。為蕃鮮。
書き下し文: 震(しん)は雷(らい)と為(な)し、龍(りゅう)と為し、玄黄(げんこう)と為し、旉(ふ)と為し、大塗(たいと)と為し、長子(ちょうし)と為し、決躁(けつそう)と為し、蒼筤竹(そうろうちく)と為し、萑葦(かんい)と為す。其(そ)の馬(うま)に於(お)けるや、善(よ)く鳴(な)くものと為(な)し、馵足(しゅそく)なるものと為し、作足(さくそく)なるものと為し、的顙(てきそう)なるものと為す。其(そ)の稼(か)に於けるや、反(はん)生(せい)と為す。其(そ)の究(きわ)まりは健(けん)と為す。蕃鮮(はんせん)と為す。
現代語訳: 震は、雷であり、龍であり、黒みがかった黄色であり、花が大きく開くことであり、大通りであり、長男であり、決断力があって躁(さわ)がしいことであり、青々とした竹であり、アシやヨシ(という植物)である。馬においては、よく鳴く馬、後ろ左足が白い馬、前足がはね上がる馬、額に白い模様のある馬である。農作物においては、一度枯れたように見えてまた芽を出すものである。その極まるところは健やかさとなる。そして、草木が盛んに生い茂る様である。
巽の象徴
原文: 巽為木、為風、為長女、為繩直、為工、為白、為長、為高、為進退、為不果、為臭。其於人也、為寡髮、為廣顙、為多白眼、為近利市三倍。其究為躁卦。
書き下し文: 巽(そん)は木(き)と為(な)し、風(ふう)と為し、長女(ちょうじょ)と為し、繩直(じょうちょく)と為し、工(こう)と為し、白(しろ)と為し、長(なが)しと為し、高(たか)しと為し、進退(しんたい)と為し、果(か)ならずと為し、臭(におい)と為す。其(そ)の人間(ひと)に於(お)けるや、寡髮(か はつ)と為し、廣顙(こうそう)と為し、多白眼(たはくがん)と為し、近利(きんり)市(し)三倍(さんばい)と為す。其(そ)の究(きわ)まりは躁卦(そうか)と為す。
現代語訳: 巽は、木であり、風であり、長女であり、墨縄のように真っ直ぐなものであり、大工仕事であり、白であり、長いものであり、高いものであり、進んだり退いたりすることであり、決断力がないことであり、匂いである。人においては、髪の薄い人、額の広い人、白目の多い人、商売で三倍の利益を得ようとする抜け目のない人である。その極まるところは、躁がしい卦となる。
坎の象徴
原文: 坎為水、為溝瀆、為隱伏、為矯輮、為弓輪。其於人也、為加憂、為心病、為耳痛、為血卦、為赤。其於馬也、為美脊、為亟心、為下首、為薄蹄、為曳。其於輿也、為多眚。為通、為月、為盜。其於木也、為堅多心。
書き下し文: 坎(かん)は水(すい)と為(な)し、溝瀆(こうとく)と為し、隱伏(いんぷく)と為し、矯輮(きょうじゅう)と為し、弓輪(きゅうりん)と為す。其(そ)の人間(ひと)に於けるや、加憂(かゆう)と為し、心病(しんびょう)と為し、耳痛(じつう)と為し、血卦(けっか)と為し、赤(あか)と為す。其(そ)の馬(うま)に於けるや、美脊(びせき)と為し、亟心(きょくしん)と為し、下首(かしょう)と為し、薄蹄(はくてい)と為し、曳(えい)と為す。其(そ)の輿(よ)に於けるや、多眚(たせい)と為す。通(つう)と為し、月(つき)と為し、盜(とう)と為す。其(そ)の木(き)に於けるや、堅(かた)くして心(しん)多(おお)きものと為す。
現代語訳: 坎は、水であり、みぞであり、隠れ伏すことであり、曲がったものをまっすぐにすることであり、弓や車輪である。人においては、憂いを加えること、心の病、耳の痛み、血の卦、赤色である。馬においては、背中の美しい馬、気の強い馬、頭を垂れた馬、蹄の薄い馬、引きずるように歩く馬である。車においては、災いの多い車である。また、通じること、月、盗人である。木においては、堅くて芯の多い木である。
離の象徴
原文: 離為火、為日、為電、為中女、為甲冑、為戈兵。其於人也、為大腹。為乾卦。為鼈、為蟹、為蠃、為蚌、為龜。其於木也、為科上槁。
書き下し文: 離(り)は火(ひ)と為(な)し、日(ひ)と為し、電(いなずま)と為し、中女(ちゅうじょ)と為し、甲冑(かっちゅう)と為し、戈兵(かへい)と為す。其(そ)の人間(ひと)に於けるや、大腹(たいふく)と為す。乾卦(けんか)と為す。鼈(べつ)、蟹(かい)、蠃(ら)、蚌(ぼう)、龜(き)と為す。其(そ)の木(き)に於けるや、科(から)にして上(うえ)槁(か)れたるものと為す。
現代語訳: 離は、火であり、太陽であり、稲妻であり、中女であり、甲冑であり、戈(ほこ)や兵器である。人においては、お腹の大きい人である。また、乾く卦である。動物では、スッポン、カニ、タニシ、ドブガイ、カメのような、硬い甲羅を持つものである。木においては、中が空洞で、上が枯れている木である。
艮の象徴
原文: 艮為山、為徑路、為小石、為門闕、為果蓏、為閽寺、為指、為狗、為鼠、為黔喙之屬。其於木也、為堅多節。
書き下し文: 艮(ごん)は山(やま)と為(な)し、徑路(けいろ)と為し、小石(しょうせき)と為し、門闕(もんけつ)と為し、果蓏(かだ)と為し、閽寺(こんじ)と為し、指(ゆび)と為し、狗(いぬ)と為し、鼠(ねずみ)と為し、黔喙(けんかい)の屬(ぞく)と為す。其(そ)の木(き)に於けるや、堅(かた)くして節(ふし)多(おお)きものと為す。
現代語訳: 艮は、山であり、小道であり、小さな石であり、門や物見やぐらであり、木になる果実や草になる果実であり、門番であり、指であり、犬であり、ネズミであり、くちばしが黒い種類の鳥である。木においては、堅くて節の多い木である。
兌の象徴
原文: 兌為澤、為少女、為巫、為口舌、為毀折、為附決。其於地也、為剛鹵。為妾、為羊。
書き下し文: 兌(だ)は澤(さわ)と為(な)し、少女(しょうじょ)と為し、巫(ふ)と為し、口舌(こうぜつ)と為し、毀折(きせつ)と為し、附決(ふけつ)と為す。其(そ)の地(ち)に於(お)けるや、剛鹵(ごうろ)と為す。妾(しょう)と為し、羊(ひつじ)と為す。
現代語訳: 兌は、沢であり、少女であり、巫女(みこ)であり、言葉や口論であり、破壊し折れることであり、付着し決壊することである。土地においては、塩分を含んだ固い土地である。また、妾(めかけ)であり、羊である。